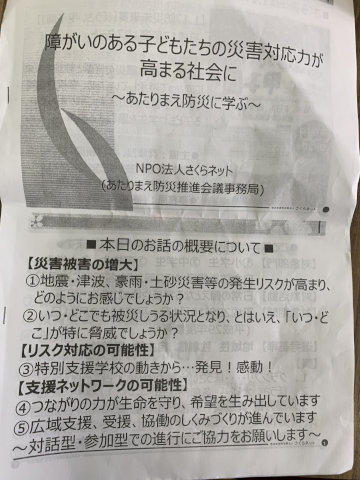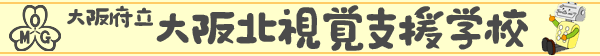1月17日 アウィーナ大阪にて府支P冬季研修会
テーマ「障がいのある子どもたちの災害対応力が高まる社会に」
講師 NPO法人 さくらネット代表理事 石井 布紀子様
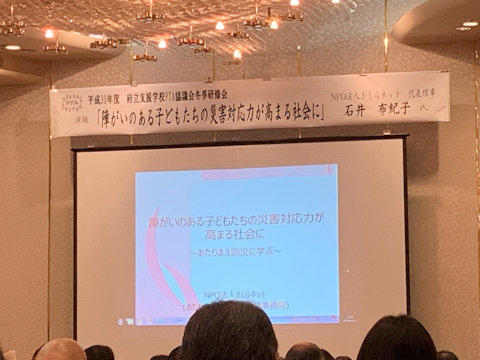
昨年の地震、台風との災害では登校中の時間帯の時もあり、非常に怖い思いや不安な時間を過ごされたことと思います。
今回は、災害時の備えのヒントになればと思っています。
-
SOSを送る場所
日頃から連絡を取り合おう。電車やバスなど同じ時間帯に乗っている人がいるのか?などを知っておく事で、いざという時に普段と同じ様に連絡を取り合い助け合う事ができます。
2.安心ゾーン
日頃、学校で過ごす事が多い子どもたちです。校内のどこが安心ゾーンなのか?を知っておく事が安心へつながります。教室で災害が起こるとは限りません。そんな時にどこへ移動すれば安心なのか?これは、学校のみならず自宅などでも同じだと思います。見えない、見えにくいからこそ、知っておく事で不安材料を減らす事に繋がると思います。
3.備蓄品
本校にもあります、備蓄教室。本校で管理している備蓄品はありますが、保護者が管理する備蓄品の用意。リュックなどの中に、おむつや子どもが落ち着ける物を入れておきます。おもちゃや、お菓子などなんでも構わないとのこと。この備蓄品は、保護者が管理します。学校+PTAで協力し備えを考えていきましょう。
災害が学校以外で起こったとき
放課後等デイサービスなどに子どもがいる場合、学校は連絡先がわかるのか?
通学バス乗車中、学校へ移動出来ない場合はどこへ避難するのか?
授業中に災害が起こった場合、学校が避難所となります。地域住民の方々とどのように過ごすのか?
今回、改めて考えさせられました。広域な区域だからこそ、いろんな場合が考えられ、連絡が取りにくい状況になると思います。
子どもたちの不安材料を少しでも減らせるように一緒に考えていきましょう。
研修会で配られたプリントは、PTAルームに保管しています。読んでみてください。