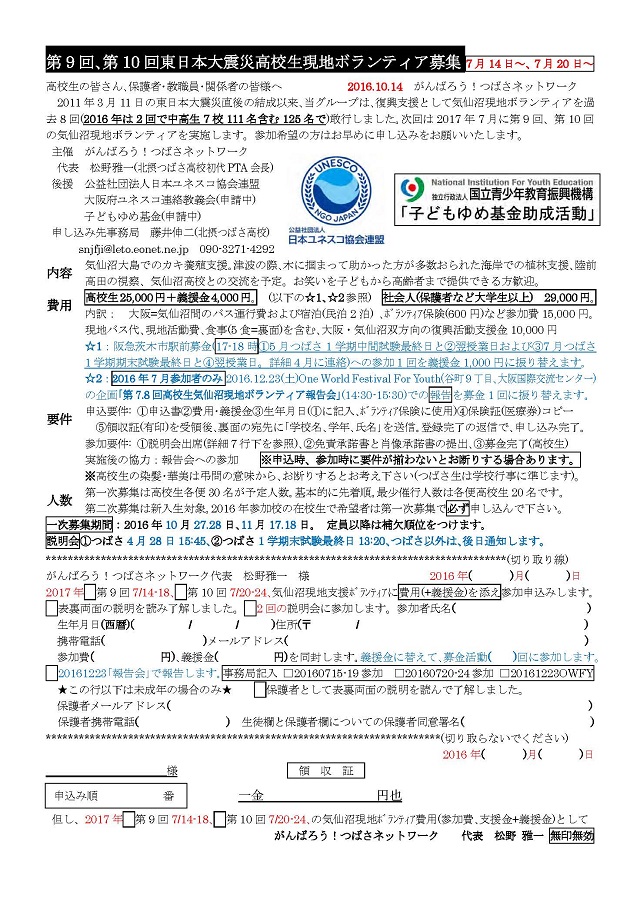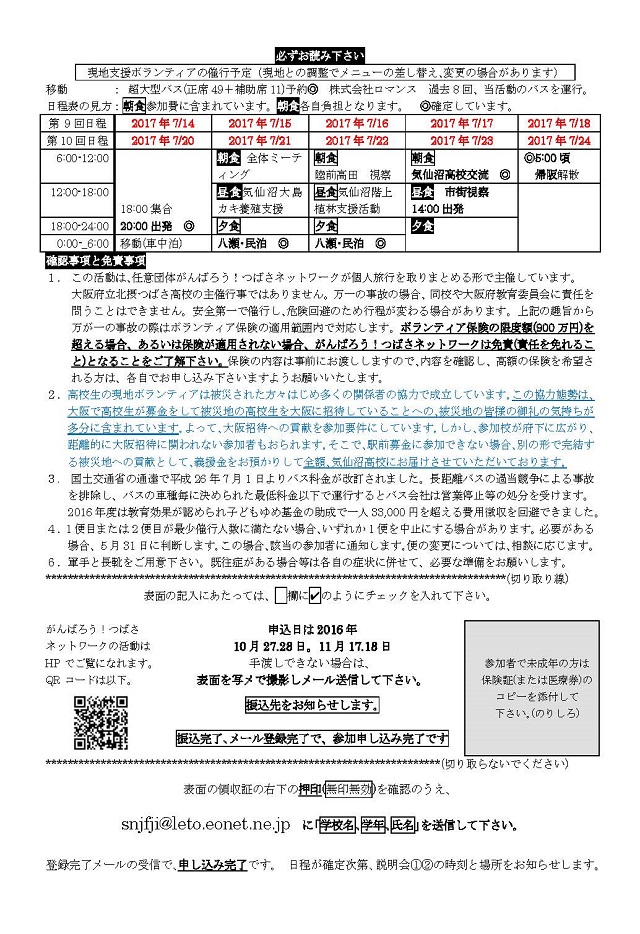| 第一日 2017年7月14日(金)18:00集合 北摂つばさ高校にて | 第二日 2017年7月15日(土)10:30 リアスアーク美術館 聞き取り 見学 | ||
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
| 現地ボランティアの顧問である坂口一美さんからの聞き取り 記念撮影 この後バス旅14時間! | 到着後、リアスアーク美術館で山内宏泰様より聞き取り、この後、見学。 | ||
| 第二日 2017年7月15日(土)12:30 気仙沼市階上地区 聞き取り 見学 植林活動 | |||
 (2) (Custom).jpg) |
|||
| 階上地区の岬の祠の前にある木に8名の方が掴まることで、津波をやり過ごすことができた。そのために海岸沿いに植林して松原の復活を目指している。菅原信治さん。 | |||
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
| 気仙沼市階上地区のかつての住宅地は津波で平原になっており、かさ上げ工事が行われている。今回は、海辺に森を作ろう会に協力して、50名で100本の木を植林している。 | |||
 (2).jpg) .jpg) |
.jpg) |
||
| 雑草が伸びて日光を遮ると、苗は光合成をすることができず、根をはることができなくなり、やがて枯れてしまう。木を育てるために、人海戦術による雑草の除草は大変喜ばれる。 | |||
 (3).jpg) |
|||
| 観光地の岩井崎を指しながら、こちらに続く砂浜は津波でえぐられたことを説明されている。この写真の左には、上層階に車が突き刺さっていた気仙沼向洋高校の校舎。 | |||
 (3).jpg) |
|||
| 海辺に森を作ろう会を支援しての植林活動を終えての記念撮影。 | |||
| 気仙沼ボランティア Matsukura Yoshie 私は高校3年生になって、初めて気仙沼ボランティアに参加しました。大阪へ帰っている今私が思っていることは「どうして今まで参加しなかったんだろう」ということです。それくらい大阪にいては経験することの出来ないようなことを経験させてもらいました。 震災当時私は小学生で、大阪でも結構揺れたなという印象でした。テレビでは連日津波の映像が流れていまりした。それから7年が経ち、正直ほとんど復興していると思っていました。確かに復興しているところも沢山あって普通に生活している部分もあると思いますが、実際に見るとまだかさ上げの途中の部分がたくさんありました。何かあった部分に何もなくなっている、大阪に住んでいる私にとっては身近に感じることが出来ていませんでしたが「ああまだ復興は終わってないんだな」と感じました。 まず1日目にはリアスアーク美術館へ行きました。そこで写真を撮った方の話を聞かせてもらいました。テレビでは津波で流されたもののことを“ガレキ”と言います。だから私もそれを“ガレキ”だと思っていました。けれど話を聞いて被災された方が流されたもののこもを“ガレキ”と呼ばれることが嫌なことを知りました。瓦礫の意味は「役にたたないもの、価値のないもの」という意味だそうです。自分たちの町のもの、そこに確かにあった生活物を“意味のないもの”と言われたらどんなにつらいだろうと思いました。私は2度と“ガレキ”と呼びたくないと思います。 次に海辺の森を作ろうの会で植林活動に参加させてもらいました。当時木に捕まって助かった人が何人もいるということで未来に繋げる木を植える活動だそうです。少し移動して海側に行くと実際に人が助かったケヤキの木を間近で見ました。海が近いのにそこでしっかりと根をはり何人もの人を助けた立派な木でした。気仙沼では約40年に1度津波が来るそうです。私はその頻度にとても驚きました。平均寿命が80を過ぎているとはいえ人生で1度か2度は津波がくる恐れがあるということだからです。木が人を助けれるまでにはたくさんの時間が必要ですが、それをずっとずっと未来に繋げることが出来る活動に参加出来ることが出来てとても良かったです。 2日目は陸前高田へ行きました。震災の被害をそのまま残した道の駅は色々なものが歪んだり中がぐちゃぐちゃになっていて自分がここにいたらどうなっていただろうと怖くなりました。津波の高さは14m〜15mきていてその高さの波が来ていて冷静に判断出来ることが出来るのだろうかと感じました。その後河野さんのガイドで奇跡の一本松などの説明をしていただきました。残っている一本松はレプリカだそうで、1億5000万円かけて作られたそうです。ガイドさんも言ってはったけど、確かにそれが残ることは意味があることなのかもしれないけれどその1億5000万円があればもっと他のことにお金を使えたのではないかな?と私も疑問にも感じました。また、河野さんのお話で印象的だった話があります。それは小学生の子供が津波が迫って逃げている危ないときに後ろからおばあさんが背中を押して助けてその後に流されていってしまったという話です。もし自分がおばあさんだったら自分よりもその小学生を助けれるのか、もし自分がその小学生だったら自分を助けて流されていく人を見てその後どう思うのか。私には想像も出来ないことでした。 次にフェリーで大島に移動して牡蠣の養殖のお手伝いをさせてもらいました。初めて牡蠣を食べさせてもらったり、船に乗りどんな風に養殖しているのかを見せてもらいました。草刈りをしたりシール貼りをしたり、少しでも力になれていたら嬉しいなと思います。 2日間民泊させていただいたお家では、美味しいご飯をたくさんご馳走になりました。出てきた料理には裏の畑で作られた野菜がたくさん使われていてどれも新鮮でとてもおいしかったです。またフラダンスを教えてもらったりしました。フラダンスをしたのは初めてで踊りの内容が手話になっていたのがとても面白いなと感じました。お父さんお母さんはとても優しくて自分の家のように落ち着いたし、帰るときはとても寂しくて、また来れたらいいなと感じれる温かいお家でした。 3日目は気仙沼高校との交流でした。短い間でしたが「夏」をテーマにグループワークをしたり人間知恵の輪をしたりしました。その土地のお祭りの話が出来たり、知恵の輪では凄く苦戦したけど一つの円になることが出来ました!気仙沼高校の人達は凄くしっかりしていてとても良くしてもらいました。気仙沼と大阪はとても離れていてなかなか会えるような距離ではないけどこの交流で出会うことが出来たのはほんとに凄いことだなと思います。 気仙沼ボランティアを通してたくさんのことを経験させてもらいました。現地の方にたくさん元気をもらうばかりで、力になれたりしたことは少ないかもしれないけど今回参加させてもらえてとても良かったと思います。初めて宮城を訪れ、美味しいものをたくさん食べてカモメに直接かっぱえびせんをあげたり楽しいこともたくさん出来ました。 高校生のうちにもう気仙沼ボランティアに参加することは出来ないのがとても残念だけど、また卒業してから個人的に訪れることが出来たらいいなと感じました。まだまだ元通りまでにはなっていないと思うので自分が出来ることをこれからもしたいと思います。気仙沼の方達に感謝でいっぱいのあっという間の現地2泊3日でした。 |
|||
| 気仙沼ボランティアに参加して Iwane Nanami 今回私はこの気仙沼ボランティアに初めて参加しました。友達の勧めや先生の勧めで、実際に現地に行ってみると思っていたよりも過酷で辛い話、そして美術館などでみた写真や当時の物をみてとても衝撃をうけました。 1日目では美術館にいき震災に遭われた方にお話を聞くことができました。今まで`死骸や`瓦礫など私たちが使っていた言葉は被災者の方々にとっては気づつく言いまわしになっていた事を知りとても恥ずかしくなりました。展示されている人形やビデオカメラ、その他たくさんの物へ1つ1つ持ち主の方の思いが書かれていて思い入れのある物なのに展示を許してくれたのは美術館に訪れる観光客や私たちのようなボランティアに来た人に当時がどんな風だったのか、今後どうすればいいのか、などを伝えたかったんだと思うと今回参加しなかった人にもボランティアに参加してほしいと思ったし私もがんばろうと思いました。 その後は海辺の森を守ろう会の方々に協力してもらい果物の木を植えました。三年生の中には木の成長が見れてよかったなど言っている人もいました。何回も参加していて凄いと思い私も来年もいけたらいいなと思いました。その後は実際津波の時に11人ほど助けたという奇跡の一本松を見ることができました。 民泊先では優しく陽気なご夫婦で、とても気持ちよく泊まることができました。そのなかでもお母さんが作る唐揚げはとても絶品でみんな夢中になって食べていました。 2日目は朝から船にのり大島に行きました。牡蠣の養殖をしている家族の所にいき草むしりやシール貼りや船に乗らせてもらい、蒸された牡蠣も食べることができ色々な体験ができて楽しかったです。行きも帰りも山を40分くらい歩ききつかったけど帰りは雨が少し降っていたので涼しく歩きやすかったのでがんばれました。その後また船にのり行き道と同様かもめにかっぱえびせんをあげれて楽しかったです。 民泊先では焼肉だったのですか1人1パックお肉がでてきて大阪とはやっぱり違うんだなと感じました。お父さんの作る春雨サラダやシメのやきそばもとても美味しかったです。最終日は気仙沼高校の生徒さんとの交流でしたが私は体調が悪く交流できなかったので残念でした。でもバスのお見送りの時に向こうの生徒さんがとても元気そうな顔を見ることができてよかったです。帰りのバスでは熱がでて椅子を譲ってもらったり薬を買ってきてもらったりと周りの友達に迷惑をかけてしまいとても申し訳ないと思ったし感謝でしかないです。 今回の気仙沼ボランティアに参加して普段では味わえないような事ができいい経験になったので向こうで感じた事などを周りの人に伝えて、より多くの人に知ってほしいとおもったしより多くの人にボランティアに参加してほしいなと思いました。2泊5日間お疲れ様でした。 |
|||
| 気仙沼ボランティア Kusano Sakura 第9回気仙沼現地ボランティアに初めて参加してきました。この東北プロジェクトは1年の時から知っていましたが、なかなか勇気が出ず参加することができませんでした。3年生になってやっと行くことが出来て本当に良かったなと、とてもいい経験に関わることが出来たなと思いました。 今回現地に行くまでは今どうなっているか全く分かっていなかったし、被災地の状況は約6,7年前のテレビで見る映像しか正直覚えていませんでした。私は当時小学5年生で歌の練習をしている時に起こった地震の事が今でも頭から離れません。大阪では割とすぐに揺れはおさまりましたが、家に帰って地震のニュースを見て驚きしかなかったのを覚えています。 1日目は、南三陸に行きました。バスに乗りながら外を見ると津波で姿を変えた建物がまだいくつか残っていて、震災遺構として残すと聞きました。そしてあちこちにかさ上げしているのを見ました。私はもっと復興作業は進んでいると思っていたけど、実際はそんなに進んでいるわけではなくて、説明してくれた人によるとまた3年半はかかると聞いて地震の爪痕がこんなにも深いんだなと改めて思いました。 次に、当時のリアルな被災状況が展示されているリアス・アーク美術館に向かいました。最初に展示されている写真を撮った学芸員さんのお話を聞きました。テレビやネットの情報だけではきっと知ることが出来ていなかった事を聞くことができました。1番被害がひどい地域でその場にいた方のお話は凄く胸にささりました。写真の横に書いてあった被災者の方々の資料もひとつひとつ言葉に表せないような気持ちになりました。 この日最後に植林活動をしました。津波が来ている間ケヤキの木に掴まって10人の命が助かった、だからそれから植林活動を続けていると知りました。私も2本友達と一緒に植えさせていただきました。来年は来ることができないけど元気に育ってくれたらいいなと思いました。その後ケヤキの木を見に行きましたが、その道中もまだあまり復興が出来ていませんでした。 2日目はまず陸前高田の旧道の駅に行きました。まずそれぞれで黙祷をしました。壁には震災前と後の写真が比較として貼られていました。私は道の駅を見るのが初めてだったので、衝撃でした。どれだけの高さの津波だったかのボードが貼ってありましたが、14.5mという数字を見て信じられませんでした。あんな高い波がきたら助かる確率はほぼないんじゃないかと思いました。旧道の駅の前の入口の所が全てもぎ取られて、中に大きい流木が流されて引っ掛かっているのも見る事ができました。しばらく見たあとガイドの河野さんが来て色々なお話をしてくれました。津波にのまれた小学校の生徒が後ろからおばあさんに「早く行きなさい」と背中を押されてふと後ろを振り返ったら仰向けになって流されていった姿を見てしまったという話は凄く胸が痛みました。小学生の時にそんな経験をしてしまうなんてどれだけ辛かったんだろうと思いました。そしてバスで奇跡の一本松を遠くから見に行きました。今はもう当時のものは枯れてしまったから1億5千万をかけて幹の外側を残しレプリカを作ったという話を聞きました。思い出すという意味で残すのはいいけどもっと他にも使い道があったのではないかとガイドさんも少し話していました。 そして次にフェリーで大島へ移動しました。大島ではカキの養殖場でお手伝いをさせていただきました。カキの試食や袋へのシール貼り、小船に乗ってカキが吊るされているイカダを見に行ったりしました。あんなに間近で養殖途中のカキを見ることは無かったので楽しかったです。フェリーで帰る時に養殖場の方が見えなくなるまで見送ってくださったのが印象的でした。 この日は民泊最後の日でした。民泊というかたちは初めてだったのでほんの少しの不安がありましたが、とても美味しいご飯を用意してくれて、しっかり休憩をとり、とても楽しい2日間をお家で過ごすことができました。お父さんと急遽2人できゅうりを取ったり、お母さんにはフラダンスを教えていただきました。2人ともとても優しくて暖かく接してくれて本当のおじいちゃんおばあちゃんの家に帰ったような気持ちになりました。お見送りをしてもらった時とても寂しくなりました。 3日目は気仙沼高校の生徒との交流をしました。グループワークではみんなもちろん初めて会うのに優しく接してくれてとても話しやすくとても楽しかったです。フリータイムには人間知恵の輪をしました、本番ですぐ解くことができて凄く楽しむ事ができました。バスで帰るとき何人か走って見送ってくれたのは嬉しかったです。 今回3年生で初めて参加することができて本当に良かったです。凄く充実した3日間を過ごすことができました。1日1日が終わるたびに友達と1年生の時から来たらよかったなあと何回もぼやいていました。被災地の現状を知り、約7年前の事も振り返り、まだまだ復興はしきってないけどこれからも私達の世代が出来ることがあればできる限りしたいです。もう来年このボランティアに参加することはできないけど、現地の人が言ってくれたようにまた来たいなと強く思いました。 |
|||
| 第三日 2017年7月16日(日)9:30 岩手県陸前高田市 聞き取り 見学 | |||
 (2) (Custom).jpg) |
|||
| 陸前高田市観光ボランティアの 河野正義さんからの聞き取り 陸前高田復興まちづくり情報館にて。 施設の中央には津波で根こそぎ流された流木が展示されている。 | |||
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
|
| 松原7万本のうち残った、奇跡の一本松 | 旧・道の駅「高田松原」にて | かつて岩手県最大の海水浴場だった | |
| 気仙沼現地ボランティア Hashiguchi Amane 1日目 車中泊しました。 2日目 一番最初に南三陸町の防災庁舎を見学してまずガイドさんが教えてくださったのが東日本大震災で15.7mもの津波が押し寄せてきて低い土地の村などにすぐ波が来てのみ込まれてしまったので震災後は10m土地を盛り上げて村を作り上げているそうで何度も何度も工事していて毎回南三陸町の道を通るたびに道の路線が変わっているそうです。そしてそのあとリアスアーク美術館へ被災状況の学習をしに見学に行きました。 そこでは震災の状況はニュースとかモノクロの新聞でしか見たことがなかったので実際に被害にあった場所で実際にこの目で写真館をみてとても胸が痛くなることがただただありました。まず、実際に被災された山内さんのお話を聞いてとにかく話を聞いてると自然の涙が出てきて実際に津波が来たのを見たことない私にも怖さや市民の人とも助け合いがあってこその避難など、あとはもし自分の友達が家族が大事な人が亡くなってしまったのを目にしたらあなたはどうしますか?死んだことを信じきれないくて立ちなおれていない中ニュースや新聞などで悲しい、受け入れられないという状況で周りの知らない人に死体があるとか言われてどういう気持ちになりますか?と言われた時とても胸が痛みました。自分がその立場になったら絶対に立ち直ることに時間がかかると思います。ですが山内さんは違いました。立ち直ることよりもほかの人を助けることに専念してとてもすごい人だと思いました。写真館で特に胸が痛くなったものが一つだけあり、その1つは小さな女の子が津波に流されて亡くなって見つかった時しっかり抱いていたクマのぬいぐるみを実際にみてもうそれをみただけで頭の中で状況が想像できるような感じがして涙が止まりませんでした。 このあとバスに乗り、気仙沼市階上地区海辺の森を作ろう会にて植林活動をしました。そこではまず最初にお昼ごはんを近くの地福寺で食べました。食べてからまず、イチジクの木の苗を20数本手作業で手分けしてグループごとにして1人2本植えました。次に草刈りで私は草の近くにいくと目が充血して作業が出来なくなってしまうので今回はやめておきました。植林活動をおえ、八瀬へ出発してこの日は終わりました。 3日目 集合場所の月舘小学校に歩いていきました。そしてバスに乗り陸前高田にいき、高田物産協会のガイドさんに一本松などのお話をお話してもらう予定が藤井先生の手違いで送ったFAXが次の日になってしまっていたので数分遅れてガイドさんが来てお話されました。あまりお話しする時間がなく終わってしまったのでもっとちゃんとお話ききたかったです。そのあとフェリーに乗り、カモメにかっぱえびせんあげて楽しんでいるとあっという間に大島浦ノ浜に到着してそれから荷物を牡蠣の養殖をする場所の人がお迎えに来ていて、そのトラックに荷物を乗せてもらい、私たちは歩いて山を越え降りていきました。すごい坂が多くてキツいなって思うことがただただありましたが、いい運動になりました。そのあと販売する牡蠣の商品の袋にシールを貼る流れ作業をしました。そのあと草刈りをしてたくさん草を刈りました。そのあとは舟に乗って牡蠣を育ててる網を見に行きました。そして新鮮な牡蠣を食べてとてもほっぺが落ちそうでした。そしてまた山を越え降りました。で、フェリーに乗って浦ノ浜に戻りました。バスの中でお弁当をたべました。そのあと八瀬に戻って民泊先に帰りました。 4日目 月舘小学校に集合して気仙沼市内のバスで出発しました。気仙沼高校に着いてからまずくじを引いてABCDEFのグループに分かれて座りました。そして班ごとに夏といえば…というテーマで話し合って仲を深めることが出来ました。生徒副会長の人と仲良くなれてめっちゃ優しくておもしろくて私が入ったDグループはみんな明るいメンバーで楽しかったです!Dグループで撮った写真もめっちゃ謎のポーズ考えてくれて面白かったです。気仙沼高校の方と交流できて本当に良かったです。 また機会があれば是非、参加したいと思います。 |
|||
| 気仙沼ボランティア Honda Sakiho 初日はリアスアーク美術館に行き震災が起こった時の写真や展示物などがあり一番に思ったのはテレビでしかみたことなかった光景を実際に震災があった後に撮った写真などがあってテレビ越しでみるよりも感じるものがたくさんありました。流れてきた生活用品や電子レンジなどの展示もあり衝撃を受けることもありました。 その後バスを乗り換え地福寺でお弁当を食べさせてもらいそっから植林活動をしました。いちじくの木をみんなで植えて来年以降まで育つようにとそのような思いで植えました。その後草刈りをする予定でしたが花粉症で酷くてできなかったです。個室の部屋に移って中から草刈りしてるところを見てたら現地の農家の人の5人ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんが来て海の特産物や農家のことや震災の事を色々聞かせてもらいました。マンボウは食べると味がなにもしないと聞き驚きました。ホヤは甘い味がすると聞きました。草刈りができなかった分とてもいい話を聞けて良かったです。 その後八瀬の森にいき民泊に移動しました。家とても近くでかさに驚き旅館かと思うぐらいでかい部屋が10部屋ぐらいあり探検しました。とりあえず鞄などキャリー置いてから採れたてほやほやの、もろこしをゆがいてもらい食べました。その後も夜ご飯を食べとりあえずお米がとても美味しかったです。食べてる時とても会話が弾んですごく楽しい1日目でした。 二日前は民泊先から月舘小学校に集合しばすで陸前高田へいき駅で陸前高田物産協会ガイドの人から震災があって一本松の木が残った場所までいきお話を少しききました。市内見学などもしました。その後フェリーに乗りカモメにかっぱえびせんをあげました。カモメの胴体やくちばしが手に当たることがないので結構楽しみながらいくことが出来ました。最初はカモメにえさをあげるのが怖いとか思ってましたが慣れたら楽しめました。 大島浦ノ浜に着きお弁当を食べました。その後店に出すシール貼りをし綺麗に貼れない部分もありました。隣でシール貼りしていた子供が可愛すぎました。それから草刈りをしました。マスクでしたのでまだまっしでした。後に舟で牡蠣の養殖してるところまだ行きました。目の前でみるのが初めてだったのですごいという気持ちがありました。舟の上無視だらけでした。舟を降りてからゆがいた牡蠣をたべさせてもらいました。鍋の牡蠣とは全然違い美味しかったです。また浦ノ浜に戻りフェリーに乗りカモメ見ながら帰りました。バスで月舘小学校まで行き民泊に行きました。おばあちゃんが待ち構えてくれていてめっちゃ嬉しかったです。お風呂を先に入り夜ご飯食べ家庭菜園してる野菜がいっぱいでてきて美味しかったので家庭菜園したいと思いました。2日目は色々な体験ができたと思いました。 3日目は朝起きて朝ごはんもたべて民泊最終日の朝はみんなで写真をとり春日丘生と北つば生で、手紙を書き渡しました。喜んでくれてよかっです。とても優しいおばあちゃんおじいちゃんでした。卒業したら絶対また行きたいです。最後のお別れの時が一番寂しく感じました。その後月舘小学校からバスで気仙沼高校に移動し交流会をしました。どんな交流会か楽しみでした。生徒会の人などばらばらになり楽しみながら1年2年関係なく笑いながら喋ってました。最後人間ちえなわなどし写真も最後みんなで撮れてわいわいしてました。その後は海の市に行きお昼ご飯とお土産を買いました。色々な人と関われた3日目でした。 この3日目気仙沼現地ボランティアに行ってテレビでみて感じることを実際その場にいた人の撮った写真などで感じることの方が大きかったです。気仙沼の若い人からお年寄りまで色々な人にかかわりたくさんのおはなしをきかせてもらえて来て良かったなと思いました。普段できない体験などをさせてもらったら民泊をしたり他の学校の生徒などと仲良くなれてよかったです。 |
|||
| 第三日 2017年7月16日(日)11:40フェリーに乗船 気仙沼大島にわたって カキ養殖 被災・復興の聞き取り 見学 支援作業 | |||
.jpg) |
.jpg) |
 (3).jpg) |
|
| フェリーの20分間はカモメにえびせんをあげて戯れる、参加者みんなのお楽しみタイム | カキの殻剥き体験のあと、実食!殻付きは初めてという参加者も多く、みんな感激。 | ||
 (3).jpg) |
|||
| 気仙沼大島は三陸海岸で最大の島。津波の時には島の中央部が水没し島が二つになった。この浦の浜を埋め尽くした漂流物は、アメリカ海兵隊がトモダチ作戦として除去してくれた。 | |||
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
| 6年間で復元してきたカキ養殖いかだ | むき身カキのビニール袋にシール貼り | カキ小屋周辺の除草作業 | 殻剥き作業の後の味見に感激 |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
| ローテーションでシール貼り | 雨が降って気温が下がってGOOD | 養殖いかだまで5往復して全員が見学 | 小松武さんからの聞き取り |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
|
| 大阪府ユネスコ連絡協議会の中馬弘毅会長、坂口一美副会長が視察、激励 | フェリーで小松さん家族にお別れ | ||
 (3).jpg) |
|||
| 大阪府ユネスコ連絡協議会の中馬弘毅会長を囲んで記念撮影 | |||
| 初めての気仙沼ボランティア Kanata Yudai 今回、東日本大震災復興支援活動に参加させていただきました。僕は高校1年生ですが、中学3年生の時から地域への活動やボランティア活動や、そして今回の東日本大震災の復興支援活動に参加したいと思っていました。まだ高校を決めていなくて、どこを選ぶか決めていたときに北摂つばさ高校のパンフレットを見ました。それを見ると、すごく良い学校だなと思ったのですが、とくに1番、すごいと思ったのが地域への活動や、ボランティア活動をたくさん行なっているということです。学校もすごくよくて、かつ、僕のやりたいことがあったのでその高校を選びました。それがきっかけで参加したいと思うようになりました。入学してからは被災地への募金活動にも参加してきました。そして、宮城県へ行くことができました。2泊5日、たくさんの経験、学ぶことができ、濃い5日間になりました。 1日目、出発の夜、バスで15時間かけ、宮城県へ行きました。これは旅行ではない、学ぶために行くんだと思いながらバスへ乗りました。バスで長時間乗るのも、東北へ行くのも初めてでした。なので疲れはありました。 ようやく到着して、2日目。外に出ると、大阪にはない景色が広がっていました。東日本大震災が起きてから6年経ってもまだ完全に復興していない町をみて、どれだけ津波や地震が恐ろしいことなのかと驚きました。地震が起きた当時、どんな状況だったのかと、知るため、リアスアーク美術館に行きました。そこには、写真と文章や被災物があります。それを見る前に被災してすぐ危険な状況で写真を撮った、山内さんのお話を聞きました。被災した当時、どんな状況だったのか、お話しした20分間、すごく心にひびいた20分間でした。携帯で録音しとけばよかったと後悔しているくらいです。本当に大切なお話しが聞けました。そして、写真や文章などを見て、もし自分もこうなっていたら、自分はどうしていたのかとか、想像して見ることができ、本当に心にひびきました。 次に気仙沼市階上地区にて植林活動をやりました。菅原さんのお話しを聞きました。津波が来た時、木にしがみついて命が助かったということを言っていました。だからいつ津波がくるかわからないがもっとたくさんの人が、1人でも助かるようにこの活動を始めたと言っていました。そしてたくさんの木を植えました。それで2日目の活動は終了しました。 そして、民泊先へ熊谷つる子さんの家へ行きました。僕は民泊というのは初めてで、すごく心配していたのですが、今思えばなんでこんな心配してたのだろうってくらい、本当に楽しい時間を過ごせました。犬もいたのですがすごく可愛がったです。夜ご飯はBBQでした。まさかBBQと思っていなかったので驚きました。食べ終わってからは、蛍を見に行きました。電灯が1つもない外は星も綺麗で蛍も輝いていました。最高のものを見れました。そして就寝して3日目の朝5時半、外に行くと、大阪にはない最高の自然と景色が見えました。すごく気持ちよかったです。 朝ごはんも美味しくいただいて、2日目の最初は陸前高田旧道の駅へ行きました。旧道の駅は被災したまま残っている建物です。建物を見ると津波がどれくらいの高さで来たのか書いてありました。14.5メートルと書いてあって驚きました。建物の中はボロボロで当時の状況がどれだけすごいことか、感じました。そのあと、協会ガイドで説明を聞きながら奇跡の一本松や被災してそのままの高校を見ました。 次に大島浦ノ浜へ牡蠣の養殖活動をしました。そこでは小松さんのお話や、養殖活動のお手伝いをしました。そして民泊先へ戻り、美味しいお魚料理を食べ3日目が終了しました。そして宮城県最後の日、最後は気仙沼高校へ交流会をしました。最初は緊張して中々話せなかったけど慣れるとものすごく楽しくて、時間が足りないくらい、楽しい時間を過ごせました。そして、お見上げを買い、無事に大阪へと帰りました。2泊5日。最高の思い出、経験、学び、その被災した当時の感触を味わうことができました。活動ではたくさんの方のお話しを聞けることができて、たくさんの体験をさせていただきました。学習では当時の写真や被災物を見てどれだけ津波が恐ろしいものなんだとすごく怖い気持ちでいっぱいになりました。 民泊では本当に楽しい2日目でした。豪華なご飯、そして民泊させていただいた方は優しさに満ち溢れていました。ずっと泊まりたかったです。感謝の気持ちでいっぱいです。東日本大震災が起きて6年が経ちました。6年経った今でもまだ完全に復興していません。今回被災地へ行って地震、津波の恐ろしさや怖さをものすごく実感しました。これから先、いつ地震、津波が起きるかわかりません。いつ来ても大丈夫なように。すぐに逃げれるように。みんな、全員が助かってほしいです。なんなら地震なんて来てほしくないです。今回、東日本大震災復興支援活動に参加し、宮城県の被災地へたずさわることができて、本当に良い思い出を作る、一生忘れられない、心に残るものができました。 また、来年もこの活動はあるといっていたので、ぜひまたみなさんの役に立てたら良いなと思い、また参加したいと思います。 |
|||
| 気仙沼ボランティア Ishizaki Yu 私は今回初めての参加でした。ボランティアに参加していい経験が出来たしすごく勉強になりました。 1日はバスに乗ってすごく楽しかったし友達とお菓子を食べながら喋っていました。私はバスの中ですぐ寝れました。サービスエリアに止まった時に起きたら首が痛かったです。サービスエリアでご飯も食べました。サービスエリアで降りてタヌキがおったので一緒に写真を撮りました。 気仙沼に着いて2日はリアスアーク美術館に行って災害の学習をしました。向こうの人に災害の話をしてくれました。すごく心に響きました。展示を見ました。いろいろあってすごく当時の写真とかを見れました。私はテレビとかしか見たことなかったんですけど当時の写真を見て凄く心に響くものがありました。災害の写真もありました。いろいろあったので見て回りました。でも私は津波のことをあまり詳しくなかったのでここで学ぶことが出来ました。 海辺の森を作ろうって所に行きました。菅原さんの話を聞いて木に登って助かった人がおるって言って何人かが助かったって言っていました。だからみんなで木を植え人を助けてらいいなって思います。みんなでいっぱい木を植えました。木が元気に育ててくれたらいいなって思いました。その後は海に行って木が人を助けたって話をしてくれました。津波に襲われている人を見つけて気に登っていた人が助けたって言う話も聞きました。松の木が人を助けたって言ってました。 それが終わったら民泊に行きました。民泊は8人で行きました。民泊はちょっと緊張していたんですけど民泊の人に優しくしていただいて凄く嬉しかったです。気さくに話しかけくださって凄く緊張が和らぎました。民泊は凄く楽しかったしいろいろしてもらって嬉しかったです。 3日は民泊の人に小学校まで送ってもらってバスに乗って陸前高田に行きました。そこでガイドさんに災害の話をしてもらいました。いろいろ災害のことを教えてもらいました。ここまで波が来たとかを教えてもらいました。たてものが崩れているままで置いてあったりとか木がここまで飛んできたって言う話をしました。いろいろ教えて貰って凄く勉強になりました。その話が終わったあとにフェリーに乗りに行きました。フェリーで大島で行きました。フェリーでカモメが飛んでいてカッパえびせんを買ってカモメにあげてもいいよって言っていました。すごくカモメが飛んでいてカッパえびせんをあげるとめっちゃ食べていました。フェリーが動くとカモメも一緒について来ました。めっちゃいっぱいいました。 フェリーを降りて山登りをしました。友達と喋りながら山登りしました。凄くしんどかったけど頑張って登りました。いろいろ喋りながら登ってちょっと迷子になったけど凄く楽しかったです。それから向こうの人の話を聞いてから昼ごはんを食べました。食べてると雨が降ってきてびしょびしょになりました。それから雨の中で草むしりをしたりシールはりをしたり船で貝の養殖を見たいとかをしました。カモメもいました。船で友達と写真を撮ったりしてました。船で話を聞いたりしてました。船から帰ってきて貝を食べました。私はちょっと苦手でした。それが終わったらまた山をくだりました。雨が降っていて友達と喋りながらゆっくり帰ってました。しんどいなって言いながら帰ってました。凄く楽しかったです。 それが終わったらお茶を買いました。それが終わってフェリーを乗って帰りました。フェリーを降りたらバスに乗って小学校に行きました。民泊の人がいました。それから民泊の家に行きました。いろいろみんな喋っていました。ご飯を食べながら喋りながら食べで凄く楽しかっです。みんなで喋りながら楽しく過ごしました。民泊の人に小学校まで送ってもらってもう民泊は最後だったのでお別れの時に民泊の人が涙目でこっちも凄く泣きそうになりました。泣いているこもいました。民泊の人にまた来てねって言われた時に凄くなきそうなりました。また機会があれば行きたいと思いました。お別れの時はほんまに凄く泣きそうになりました。バスに乗って一生懸命バイバイしました。 気仙沼高校生との交流会に行きました。班はくじ引きやって私は友達と離れたんですけど知っている先輩がいたので良かったです。そこでいろいろなゲームをしました。自己紹介をしたりポスターをしたいととかすごく楽しかったです。人間知恵の輪もしました。凄く楽しかったです。気仙沼高校生の人たちと仲良くなれて凄く楽しかったです。楽しすぎて時間が経つは早かったです。まだ一緒にいたかったって思いました。また機会があれば行きたいなって思います。バスに乗って気仙沼高校生の人にバイバイをしました。バスに乗って昼ごはんやお土産も買いました。凄くお土産を買いました。友達と選びました。凄く選んでる時は凄く楽しかったです。それが終わったらバスで帰りました。サービスエリアに着いていろいろ買いました。食べ物も食べました。凄く美味しかったです。 気仙沼ボランティアに行って気仙沼の人たちと関わって凄く暖かい人だと思いました。また機会があれば行きたいしまたいろんな話を聞きたいなって思いました。 |
|||
| 気仙沼ボランティアに参加して Tamura Suou 今年で3回目の参加でした。1年生のころは親に「言ってみたら?」と言われて参加しましたが2年生からは自分で親に行きたいと言いました。初めての参加の時に楽しかったのも1つの理由ですがまた来年の気仙沼の状況を知りたいと思ったからです。少しでも復興のお手伝いをして現地の方達のお役に立てたらなと思いました。そして今年も参加しましたが本当にいい経験になったなと思いました。 気仙沼1日目で今年が初めてのリアスアーク美術館に行きましたがすごく衝撃をうけました。山内さんが命懸けで撮った写真がたくさんありましたが1つ1つにその時の状況や山内さんが感じたことが書かれていたので自分もその時どんな状況だったのかと考えるきっかけになりました。特に当時津波に流された家の扉や木材などがそのままの状態で展示として置いてあって被害の大きさがよくわかりました。南海トラフ地震がきたら同じ状況になる可能性があるので他人事ではないしもっといろんな人に知ってもらいたいと思いました。山内さんが言っていましたが津波で流された家や壊れた家を瓦礫とは言わないでほしいと言っていて理由を聞くとすごく納得しました。元は自分たちの住んでいた町であり、家であったと。それは瓦礫ではなく自分たちの住んでいた場所だと言っておりました。 リアスアーク美術館の後は海辺の森を作ろう会で木を植えました。粘土土で成長しないで枯れてしまう木もあるそうで悲しいですが少しでも多く成長してまた以前のように戻ってほしいと思いました。成長した木をまた見にこれたらいいなと思います。去年は行きませんでしたが海の近くまで行き、命を救った木を見に行きました。1年の頃来た時とほとんど変わっていませんでした。なので懐かしいなと思いました。 その夜は佐藤さんのお宅に泊まりました。優しい方達でお話ができてよかったです。体を休めることができたので感謝の気持ちでいっぱいです。 気仙沼2日目は陸前高田に行きました。前に来た時よりもだいぶ盛り土が増えていました。ベルトコンベアも2年前は全然残っていて1年前は少し残っていたのが今年は全てなくなっていました。少しずつ復興してきているのを実感しました。12mほどの高い防潮堤を作ってると聞きビックリしましたが当時きた津波は15mなのでそれでも超えてくると思うとすごく怖いです。奇跡の一本松も毎年見に行ってますが目の前で見てみたいと思いました。 陸前高田の後は毎年お世話になっている大島の牡蠣の養殖場に行きました。行くまでの40分ぐらいの山登りがなかなかきついですが上からの眺めもよくて着いた時に海が目の前に見えるのでテンションが上がります。雨が降っていたので今回は牡蠣の入れる袋のシール貼りをやりましたが少しバイトしている感覚がありました。船に乗って牡蠣を見に行くのは毎年とても楽しいです。自分が住んでいる近くには海がないので余計だと思います。昔抱っこされていた子供がもう歩いていたので大っきくなったなと思いました。 大島に行った後は民泊先に戻りました。ご飯はとても美味しかったです。お米は自家栽培らしいです。2日と短い間でしたがとても楽しくて交流もできていい経験だと思いました。 気仙沼3日目は気仙沼高校との交流会でした。野球部がいなかったのは残念ですが試合に勝ったと聞いたのでとても嬉しいです。 交流会での班では仲の良い友達はいませんでしたがいろいろ話すことができたのでよかったです。方言の違いや手遊びで盛り上がりましたし、人間知恵の輪では手を繋いで喋りながらやらないとできないので交流するのにいいゲームだと思いました。気仙沼高校の方達はとても優しくて笑顔でいい人たちでした。短い時間ではなくもっと交流して仲良くなりたいと思いました。私は3年なので来年はもうないですがまた何かの機会で会いに行きたいと思います。お別れの時は少し悲しかったです。 お昼は海のいちに行き、マグロ丼を食べましたがすごく美味しくて去年も食べればよかったと思いました。 気仙沼ボランティアに毎年参加して本当によかったと思っています。もう被災してから6年経っていますがまだ復興があまりできてないところもあれば1年間の間でかなり変わっている場所もありました。去年は盛り土しているところで今年はもう盛り土が終わり新しいお店や道路ができているところがありました。そういうことは自分の目でみないとわからないことですし直接現地の方達とコミュニケーションをとることとテレビでみたりすることとは全然違います。なので3回とも参加したのはとてもいい経験ができたと思いますしまだ行ったことのない人たちや1回参加した人たちには是非続けて参加してほしいなと思いました。行きたいと思ってる人はとりあえず1回参加してみてほしいです。 |
|||
| 気仙沼ボランティア Motoki Aika 今回このボランティアに行くのは2回目やけど今回もいっぱい学んだことがたくさんありました。 まず1日目に震災のミュージアムに行って震災の写真や震災の体験談の話をしてくださって聞いてるだけでもとても悲しくなったし津波の恐ろしさを改めて実感しました。私たちはニュースだけでしか震災の被害を見たことがなかったけど、直接その場に行き話を聞くことでニュースとはまったく違う情報が聞けてよかったなと思いました。その体験談の話をしてくれた方は家に帰ろうとしたら家どころか町がなくなっていたと言っていました。話を聞くだけで悲しいです。 その後に木を植えに行きました。震災の時に木に捕まって助かった人が何人かいたということで、もしまた津波が来たときに木で助かるように「海辺に森を作ろうの会」というプロジェクトに参加しました。一生懸命植えました。そしてその後に海辺まで行って津波のときの話を聞きました。 それが全部終わってから民泊先の方々の家に行きました。民泊先の方々は温かくお出迎えしてくれてとても嬉しかったです。はるおさんとこうこさんはとても面白くてこの民泊先でよかったなと思いました。その日の夜ご飯はからあげと酢豚でした!すごく美味しかったです!! 2日目は朝から陸前高田市に行き、「奇跡の一本松」のところや道の駅、ガソリンスタンドに行きました。15mもの津波がそこにはきていたという印があって2回目やけど衝撃すぎて言葉が出ませんでした。 その後フェリーに乗りました。フェリーではみんなでカモメにかっぱえびせんをあげて楽しかったです。降りてから50分の山登りをして牡蠣の養殖の場所まで行きました。ついてから牡蠣を出荷する袋のシール貼り、草刈り、船に乗って養殖場まで行く、牡蠣試食をしました。大変やったけど牡蠣がめっちゃ美味しかったです!! そしてまた民泊先の家に行きました。その日の夜ごはんは焼肉でした!めっちゃ嬉しかったです! 3日目は民泊先の方々とお別れでした。はるおさんがお別れの時に泣いていてこっちまで泣いてしまいました。お別れするのがすごく辛かったです。めっちゃいい思い出になりました。お別れしてから気仙沼高校に行って気仙沼高校の生徒の方々とゲームをしたり話をして交流をしました。仲良くなって写真を撮ったり連絡先交換したりして楽しかったです。 その後にお昼ご飯やお土産を買いに行きました。海鮮丼が美味しかったです!!この4日間で色々な人と交流でき、震災のことも学べて行って良かったなとすごく思いました!また来年も行きたいです! |
|||
| 東北ボランティア Naka Emika 1日目のバスの中では東北に着き、バスの中から見える盛り土がすごく印象的で写真や当時のテレビで見てた瓦礫は一切無くて、衝撃的でした。それでもやっぱり移動して行くと、曲がったままあるポールや看板、人が住めるとは思えない傾いた家、ポツポツと見える木があり、震災の跡は残っている半面、復興に向かってたくさんの人が動いているということをすごく感じました。 リアスアーク美術館ではテレビでしか見たことのない瓦礫が自分の目で実物を見ることができました。震災について知らなかったことをこのボランティアの一番最初に知ることができてよかっだと思いました。千年に一度なんかじゃなくて津波は40年に一度あったことや、歴史を知ることで防げることがたくさんあるとわかりました。リアスアーク美術館にたくさんの思いがのせられていることがすごく感じれました。 次の植林活動では木を植えることの意味、木の偉大さを知ることができました。テレビで見てると木とかはもう津波で全て流されてるのかと思っていたけど、自分が思ってたよりも木に登って高くに居ることで助かった人が何人もいるということが分かりました。自然によって被災をしたけど自然によって救われることもあるんだなと思いました。堤防を高くして防ぐようにするよりも自然のままならこう津波は大きくならなかったかもしれないと知りました。 2日目の陸前高田の視察では実際に波が来た位置が記されていたり高田松原の駅が被災したときのまま残されていたり、写真でもテレビでもなく等身大を自分の目で真近で見てもし自分が震災当時そこに居たらと考えると恐ろしくてたまらなくなりました。情報館には未来の陸前高田のジオラマがあり東北の方のみんなが復興に本気だということをすごく感じました。ガイドの方からのお話は当時の情景が目に浮かび本当に心苦しくなりました。話を聞き、被災物を見て、震災当時のことや被災者・被災物のことを、本当に忘れてはいけないということ、後へ後へと正確に伝えるべきことだと実感しました。 亀山を登っている途中に聞いた震災当時の話は牡蠣処理場の方が本当に優しくて温かかったです。堤防を高くすれば安全というわけでもないし、堤防を高く作ることで作業場や家を壊さないといけなくなるかもしれない、そんな問題がたくさんあると知れました。 3日目の気仙沼高校との交流ではいっぱい交流できて本当に楽しかったです。アイスブレイクからはじまりポスターセッション、人間知恵の輪と1つ終わって行くごとに緊張は解けていったし、緊張が解ければとけるほど短い時間だったけど気仙沼高校の方の言葉の1つ1つに優しさがあって改めて優しさが身に染みました。 民宿の方には2日間お世話になりました。民宿は初めてでどうすればいいやろうとか戸惑うことはありました。でも民宿の方はとても温かく優しく賑やかで、時間を重ねるごとに帰りたくないまだここに居たいという思いが強くなりました。最後のお別れのときは寂しくてたまりませんでした。「もう帰るの」って言われたときは本当に帰りたく無くなりました。たったの2日間でも泊めていただき最高のご飯とお土産、そして温かさをくれた民宿の方に再び会いに行きたいと思いました。 今回たくさんの資料を見てたくさんの方からたくさんのお話を聞き、自分の今の生活からは到底想像のできないことがこの東北では起こったんだ、東北で踏んだ道も綺麗に積み上げられた盛り土がある場所も当時は被災物や海で埋まっていたと思うと本当に信じられなかったです。 震災から6年たった今私にできること、それは今回参加させていただいた『がんばろう!つばさネットワーク』のようにこうして現地に行きボランティアをすることや大阪に帰っても忘れることなく周りに伝えること、そして小さな一歩でも踏み出して少しでも力になれるように何か行動を起こすことだと思いました。これは何年たっても東北だけに限らなくても場所が違っても変わりないことだと思います。私には東北に来て、被災者の方から聞いたり見たりした責任があります。その責任を果たすために、また東北に自分の足で行き何かの力になりたいと思っています。自分にとってすごく大きな経験値になり、これまで、そしてこれからの自分の行動を見直す機会となりました。 |
|||
| 活動のふりかえり Yata Yufuna 今回活動するに当たってののテーマは、想像力。2日目、まだ何の活動もしていない私は藤井先生のその言葉の意味を分かっていませんでした。東北に来る前日までは事前学習として様々な震災に関わる施設を訪れてきました。それでも私は様々な震災の情報を知識としてではなく経験として実感できおらず、満足できていませんでした。しかし、1度街に入るとその意味を理解しました。 広範囲に広がったものすごい量の盛り土、その土の間にあった防災庁舎。未来の街の設計図や、新しい道路。それらを見た時、あまりにも今まで自分達が見てきたものと変わらなかったので復興しつつあるんだ、本当に津波の被害はあったんだろうか、とすら思っていました。しかし、被害の説明を聞くと同時にイメージすると自体の重大さを掴むことが出来ました。 続いて行ったリアスアーク美術館では、被災者の生の声を聞くことが出来ました。瓦礫ではなく被災物と呼んでいること、展示物の家の柱を家の一部として展示していることなど、お話の内容と合わせてとても心に残りました。もし私が震災の被害を受けていたなら、自分たちの大切な家を何の意味もない「瓦礫」と言われるのは嫌です。しかし、世の中では被災物という言葉を言わず、瓦礫と言っています。この時、社会と被災者個人の間にある差を実感しました。それを感じた後に命懸けの取材の写真や展示物を見たので、解説の文の撮影者の考えを読み取ることができました。そして、当時の事をイメージすることが出来ました。 また、セミの話も印象的でした。津波で地中のセミの幼虫が流されてしまったため、このあたりでは今は鳴いていないという話です。大阪に比べてやけに静かだなあと思っていましたが、まさか津波の影響だとは思いませんでした。自然災害は人間だけではなく、ほかのいろいろなものにまで影響を及ぼすことがわかりました。これが私なりに2日目に得たことです。 3日目の活動で1番印象に残ったのは、高田松原道の駅と情報館です。 目的地である道の駅についた時、気軽に外の風景に目をやった私は愕然としました。自分の知っている道の駅とかけ離れた物がそこにあったからです。出っ張った部分はきれいさっぱり無くなり、コンクリートの壁は剥がれ、コードは剥き出しになり、そして中には様々な破片や巨大な木がめちゃくちゃになっている道の駅がありました。大地震を経験していない私は初めて見た本物の被害を受けた建物に、言葉を失いました。そのとき頭では、映画のセットみたいだなあと思い、信じきれていませんでした。 しかし、情報館に入ってそれが現実だと認識し始めました。震災前と震災後を比較した写真はなかでも1番現実味を帯びていて、寒気がするほどでした。私が2日目の活動をもってしても分からなかった震災の実感を少しだけ感じることができました。だから私は全人類が私達のように被災地を訪れ、震災物を間近で見たならば、私達はもっと協力できるようになると思います。むしろそうするべきだと思います。 その後牡蠣の養殖場でお話を聞いて気づいたことがあります。高田松原でお話をして下さったガイドの方も、養殖場の方も「今地震がきたら」という話をしていた事です。やはり、被災者は私達と違って「知識」ではなく「経験」としてあの地震をとらえているから思いが違うのだろう、と気づき、まだまだ理解とやる気が足りていないのだと思いました。 活動3日目は、被災したという気仙沼高校を訪問しました。学校や生徒自体は普通の高校と変わらなかったけど、階段の途中にあった詩に目を奪われました。そこには震災を乗り越えようとする言葉が筆で大きく力強く書いてありました。気仙沼高校に被災したという実感がなかった私には、ここが被災地であることを実感させられました。そこでの活動は、3日間同じ時を過ごしたとはいえ初対面の人と一緒に行うものだったので、たくさんの人と接する術を学べました。 この活動で気づいたことは、私は被災地への認識を少し改めなけなければならないということです。被災地を震災当時のままだと思っていたり、いざ行ってみるとかなり復興工事が進んでいたりして、それを鵜呑みにすることは被災地の現状を正しく把握し見つめることの妨げになります。それに被災者の方々に暗いイメージをおしつけるのも違います。最初はみんな同じで、そこから自分たちとは違う体験をした人たちです。私たちがすべきことはそんのような人々の経験を知識ではなく経験としてしっかりと学び、これからにつなげていくことだと感じました。 |
|||
| 第四日 2017年7月17日(月)8:45 月舘小学校 八瀬森の学校のホスト家族とお別れ | |||
 (2) (Custom).jpg) |
|||
| 大阪府ユネスコ連絡協議会の坂口一美副会長からホスト家族の皆様への挨拶。この後、大上観光のバスで気仙沼高校へ移動。 | |||
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
八瀬 森の学校のホスト家族の皆さん 心温まるおもてなしありがとうございました。 | .jpg) |
|
| 私が東北で学んだこと Aburadani Nanaka 宮城に着いてまずリアスアーク美術館に行った。テレビや新聞では見れない写真が多くあった。写真の特徴は私たちがよく見る写真のような「安全な場所」から望遠レンズで撮ったものではなく「命をかけた」被災物のすぐ側から撮っているということだ。他にも地震で壊れたものや津波によって流されてしまったものを「ガレキ」とは言わず「被災物」と呼んでいた。なぜならそれらは被災した方々が大切に使っていた物だからである。その大切な物が「ガレキ」と言われるのはおかしいからだ。しかし多くの人は「ガレキ」と呼んでいる方々も多い、なのでこれからは「被災者」という言葉だけでなく「被災物」という言葉も伝えていきたいと思った。お話を終え次に数百枚の写真や被災物を見た。時間の都合上全てをじっくり見ることは出来なかったがその中でも私が衝撃を受けたものが二つある。 まず一つ目は南三陸町志津川戸倉・波伝谷の状況の写真である。そこには1993年に発生した昭和三陸津波被害を教訓とし、後世へ伝承するために設置された石碑が倒壊した写真だ。その石碑には「地震があったら津波の用心」と書いてあった。昔の人々の警告を私たちは受け止められていただろうかと書いてあり、意識一つで1人でも助かった命があったのかなと感じた。 二つ目は被災物で卒業証書だ。震災は3月に起こった。つまり卒業式をしている学校も多くあったのである。卒業式直前に震災が起こり2階に置いてあった卒業証書を念のために3階に移動させたそうだ。しかし津波は人々の予想を超え卒業証書は被災物となってしまったのだ。当たり前の生活、当たり前の毎日それが一瞬にして無くなってしまうんだと感じ、改めて自然災害の恐ろしさを知り当たり前とは何なのか考えさせられた。 リアスアーク美術館での体験を終え次に気仙沼市で海べの森をつくろう会の活動に参加させてもらいイチジクの木の植林をした。そもそもなぜ植林をするのかと言うと震災のとき多くの建物が津波に飲み込まれていく中、木に登った8人が助かったのである。1本の木が人の命を助けたのである。私たちはその8人の命を救った木を見に行った。すぐ近くには海があった。その木は約100年から150年前からある木だった。そして私がその木を見て思ったことと驚いたことがある。私はその木を見るまではすごく大きくて太くて…というイメージがあったのだが思ってたよりも細い木だったのだその細い木が人の命を救った事実を知り木の存在がどれだけ凄いことなのか知ることが出来た。「木が津波から人々の命を守った」だから海べの森をつくろう会の方々は木を植えているのだ。 植林を終え民宿先へと向かった。どんな人だろう初めは少し不安もあったがホストファミリーの方と顔合わせをしてすぐに優しい人たちだなと感じた。夜ご飯はホタテやサーモン庭で育てたキュウリなどのサラダなど自然の味がたくさんあってとても美味しかった。ホストファミリーのお2人はたくさんの趣味があって作品やコレクションを見せてもらった。その次の日の民宿では葉っぱの葉脈だけを残したものをしおりにしたり、木のキーホルダーを作ったり、チラシを使ってくす玉を作ったりもさせてもらった。どれもすごく良い経験になった。そんな2人とお別れするのはとてもとても寂しくて悲しかった。涙が止まらなかったけど絶対にまた会いたいと思った。先に民宿でのことを書いたので次に二日目三日目の事について書こうと思う。 二日目は陸前高田旧道の駅でお話を伺った。衝撃的な話が聞けた。特に自分を守った代わりに津波に犠牲になった人の事を一年以上家族にも言えなかった人の話は今でも忘れることが出来ない。 貴重なお話を終え次に私たちは大島に向かった。フェリーに乗って行ったのだが行く途中たくさんのかもめが私たちと一緒に飛んでいた。かっぱえびせんを分けて貰ってかもめにあげると食べに来てくれて嬉しかった。大島に着いて五十分ほど山登りをして牡蠣の養殖をしに行った。まず船に乗せてもらって牡蠣を見たり牡蠣を入れる袋にシールを貼ったり牡蠣を試食させてもらったりした。どれもとても貴重な経験になった。 三日目は気仙沼高校と交流会をした。アイスブレイクやポスターセッション、人間知恵の輪など様々なゲームをした。お菓子や飲み物を一緒に食べれて楽しかった。フリータイムのときは気仙沼高校の生徒が震災当時のことを話してくださった。その生徒は避難した先から津波に飲み込まれていく自分の家が見えたと言っていた。お別れするときは気仙沼高校の人たちがバスで遠ざかっていく私たちを走って手を振ってくれた。 今回の東北のボランティアで一番思ったことがある。それは宮城の人たちの心の温かさである。民宿のお父さんお母さん、リアスアーク美術館の方々、バスを運転してくれた方、牡蠣養殖の方々、海べの森をつくろう会の方々、ガイドの方、気仙沼高校の方々…他にもこの数日間でたくさんの方々と出会った。このことを忘れずに私は学んだことを多くの人に伝えたいと思った。震災への考え方が180度変わった。ほんとうにありがとうございました。頑張ろう東北。頑張ろう日本。 |
|||
| 気仙沼ボランティア Ikeda Ami 気仙沼でのボランティア活動は初めてだったので、緊張していたのですが、とてもいい経験になったと思います。バスで車中泊はとてもしんどかったです。 1日目の朝から疲れすぎて活動できるかなと思っていたけど、美術館を見てみると、想像より大変そうでかなりおどろきました。美術館で話をしてくださった方の飼っていた動物を助けに行ったら家が全部流されていたという話は、本当に悲しくなりました。自分も犬を飼っているので自分がそういうことになったら本当につらいなと思いました。どの写真でも、横に説明文がいっぱい書いていて伝えたいことがいっぱいあるんだなと思いました。どういう理由で撮ったのかよくわかりました。 その日は木も植えに行きました。いちじくとブルーベリーを植えました。大きい苗を植える時苗をいれている黒のビニールの箱みたいなものを苗から外すのがとても難しかったです。はやく元気に育ったらいいなと思いました。そのあと海まで歩いた時、津波の高さにとてもおどろきました。 2日目陸前高田に行った時にも店の壁とかに津波がきた高さとか線が引いてあったけど、とてもびっくりしました。こんなに高い津波がきたらもう逃げれないと思いました。15メートルは思ったより高かったです。地震から津波がきたのは40分後と聞いたけど、その間に逃げれた方もたくさんいたはずだけどたくさん被害にあった方がいて悔しいなと思いました。だから、自分のところに地震がきたらどうするか家族と話し合おうと思いました。一本だけ残った松は結構細かったけど残ってすごいなと思いました。語り部の人がたくさん話をしてくださって、特に印象に残ったのはその人の親戚の小学生の時に目の前で人が流されたという話です。小学生でそんなことを体験するなんてとても怖かっただろうなと思いました。他にも小学校の窓が3階までが割れていたりして津波の恐ろしさがよくわかりました。そういう経験をした人や家族を失くした人がたくさんいると思うと辛かったです。この震災を絶対に忘れてはいけないと思いました。 そのあとにフェリーで大島に向かう途中にカモメがたくさん寄ってきて、かっぱえびせんをあげるのがとても怖かったです。かっぱえびせんに向かってくるかもめの顔が怖かったです。顔を見なかったらあげれたらとても楽しかったです。カモメが飛んでるとこをみてたらなんかかわいいかったです。 大島ではいっぱい歩いて、汗だくになったけど、そのあとのカキの養殖場でカキを食べたりボートに乗ってカキを養殖しているところを見に行ったりしてとても楽しかったです。カキは大きくてプリプリでとても美味しかったです。庭の草むしりもできたので、力になれていたらよかったと思います。帰りのフェリーで外を見ていたら、結構離れたところに歩いたところが見えてこんなところまで歩いたのかと思ったら楽しかったです。 3日目は気仙沼高校の方と交流をしました。自己紹介などみんなでして楽しかったです。とても楽しかったのでまた行きたいなと思いました。民泊はとても優しいお家に泊まれてとてもよかったです。ご飯も美味しくて最高でした。お別れするときはとても悲しくて泣いてしまいました。また会いたいです。本当にいい経験をできて良かったと思います! |
|||
| 振り返り Yanagimoto Natsuho リアス、アーク美術館振り返り: 美術館では、震災当時の写真を見て、初めて知ったことは、急に学校の建物や家が壊れたので被災者の人は、とても大きなケガもあり、学生さんたちは、大丈夫かなあと思いました。もし、自分だったら死んでいたと思います。あと、卒業証書、ランドセルも津波で流されたりして本当に悲しいと思ったので、これからの将来も何が起こるのか分からないので、自分の身をしっかりと守っていきたいです。 植林活動振り返: 土で木を植えるのは、初めてでしたが、1本目は、なかなかうまくできない部分もありましたが、分からないことは、友達や先生に聞くことができてとても嬉しかったです。 シロツメ草抜き: 結構何回もやっているので、慣れて覚えてきました。簡単な作業ですばやく作業ができてとても嬉しかったです。 岩井崎の見学: 岩井崎周辺には、床下浸水も起こって、家の人が、被害を受けたり、子供まで死亡しているのがとてもかわいそうだと思いました。もし、自分なら生きていけないと思いました。あと、被災地の人は、食糧もなくて、生きていけないと思います。その人たちのことも考えて、これからもいっぱい学習していきたいです。 河野さんと合流振り返り: 東日本大震災の黙祷をしたり、いろいろ見学できて良かったです。河野さんの質問にも答えることができて褒められてとても嬉しかったです。崖もいっぱい落ちていて、まだ復興作業が進まないのかと、とても残念だと思います。 東日本大震災の聞き取り振り返り: 小松さんは、とてもわかりやすく説明して下さって震災当時のことは、上のほうに逃げることを学んだり、死亡した人が多く、マグニチュードも大きく行方不明も多くて、大変な地震だと思いました。 カキの養殖振り返り: 船に乗って、雨でいかだには乗れなかったことが残念だったけど、いかだの様子が見れたので、良かったです。 カキの試食振り返り: ふだん家で食べれないカキが食べれて良かったです。ぷりぷり感があり、とても味がしみて良かったです。 草刈り感想: 学校の農道清掃や、1日目のシロツメクサ抜きでも、経験しているので慣れてきて、スムーズにできたと思いました。 カキのシール貼り: これから、食べるひとの気持ちを考えてゆっくり貼るように意識したが、最初は、慌てて貼ってしまい少しずれたけど、慣れてきてだんだん上手になったと思いました。すごくできるようになってきてると先生から褒められてとても嬉しかったです。 気仙沼高校との交流振り返り: 交流では、アイスブレイク、ポスターセッション、人間知恵の輪をやりました。 アイスブレイクでは、自分のことを紹介して、みんな自分のことをわかってもらえて、嬉しかったです。コミュニケーションをとる上でも、自己紹介は、大事だと思いました。ポスターセッションでは、自分で意見を出し合い、意見をまとめたり、発表したりしてとても楽しかったです。 人間知恵の輪では、分からないことは、友だちに質問することができて良かったと思いました。 3日間貴重な体験が出来てとても良かったです。民泊の人とも、色々な話ができてとても楽しかったです。 また、機会があればボランティアに行きたいです。 |
|||
| 第四日 2017年7月17日(月)9:30 気仙沼高校 高校生交流 | |||
 (3).jpg) |
|||
| 気仙沼高校生徒会からの挨拶の後、ワークショップの説明 80名の生徒が交流を楽しみにしていた。 | |||
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
| 気仙沼高校、春日丘高校、松原高校、北摂つばさ高校の4校によるワークショップ、和気あいあい。 | 大岡団長から義援金12万円を手交 | ||
 (3).jpg) |
|||
| 大阪府ユネスコ連絡協議会の中馬弘毅会長夫妻を囲んで記念撮影 | |||
 (2) (Custom).jpg) |
|||
| ロマンス観光のバスに積んでいた横断幕で気仙沼高校の皆さんにエールを送る。この後、海の市で視察、昼食のあとバス14時間旅で大阪へ。 | |||
| 第五日 2017年7月18日(火)4:30 北摂つばさ高校 まとめ、解散 | |||
.jpg) |
.jpg) |
第9回気仙沼現地ボランティアを終えて 2017年7月18日 今回は、自分自身の参加が叶わず失礼しました。 大岡成樹団長、無事の帰阪、誠にありがとうございました。 今年は日本のユネスコ活動70周年ということで仙台での記念の全国大会のあと、大阪府ユネスコ連絡協議会から中馬弘毅会長ご夫妻、坂口一美副会長、が気仙沼に駆けつけ激励いただきました。ありがとうございました。 今年もバス1台50名で気仙沼現地ボランティアを開催することができましのも、春日丘高校、松原高校、北摂つばさ高校をはじめユネスコ協会ESDパスポート実践校の先生方が教育活動としての現地ボランティアを位置付けて取り組んでいただいているおかげです。 その意味でユネスコ協会の営みに感謝いたします。誠にありがとうございます。 気仙沼、陸前高田の様子もすこしずつ変わってきていることと思いますが、復興というにはまだまだである旨の報告を受けています。双方向の交流によって復興がさらに進むように、また両方の地域で高校生の心に親切や優しさの灯をともし続けられるように、この取り組みを続けたいと思います。今後とも、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 代表 松野 雅一 |
|
| 帰阪後、各校授業なので、万一に備えて4:00に到着、 まとめのあと、振り返りのパソコン入力。完了した人から解散となりました。 みなさん、本当にお疲れ様でした。 |
|||
| 気仙沼ボランティアを通して Wada Tsugumi 今回の気仙沼ボランティアでは1年間でどれぐらい復興ができているのかが分かりました。私は作年の気仙沼ボランティアにも参加させていただきました、そのときはなかった建物やたくさんの盛土がありました。震災が起こった年から6年ほどがたった今は元通りというわけではないですが、少しずつ復興しているのが見て分かりました。 まず、初日の15日に南三陸町に防災庁舎行きました。たくさんの被害にあった場所で、建物はほとんどありませんでした。高いところから見廻す南三陸町はたくさんの盛土ができていました。まだ、家などはなかったですが復興に向けて進んでいることが分かりました。次は南三陸町から気仙沼市に行きました。 気仙沼市ではリアス・アーク美術館を訪ねました。リアス・アーク美術館も被害を受けていましたが今は東日本大震災の記録を写真や被災物を展示していたり、リアス地域の歴史についての展示もしています。リアス・アーク美術館に展示されているものは自衛隊が動く前の写真や客観的ではなく主観的な解説が写真や被災物にされていて、人事ではないし、もし自分がそうなったらどうして、どう思うのだろうかなどを考えることができました。私は被災してなくなった家の煉瓦などを「ガレキ」と呼ばないで「被災物」と言うようにしているという話の理由にとても共感しました。他人から見た家の欠片はガレキでも自分からすれば大切な思い出がたくさん詰まったものだからガレキなんかじゃない、その言葉がとても深く心にささりました。 そして、初日最後は海辺の森を作ろうの会の皆さんと植林活動をしました。今回の植林活動で植えたのはイチヂクやブルーベリーです。この植えた木が大きくなって誰かの命をまた救うことができたらいいなと思いながら植えました。植林活動の後は実際にその木に掴まって助かった人がいたという木を見に行きました。その後は八瀬の森にて民泊先に行きました。 2日目16日はまず最初に陸前高田に行きました。陸前高田市も被害がとても大きくたくさんの方が亡くなりました。私たちは陸前高田旧道の駅に行きました。そこには道の駅の中に津波の勢いになぎ倒された松の木が1本入り込んでいました。普通ならありえない光景でした。それだけ津波の勢いが凄かったということを物語ってします。そしてその後は語り部さんの話を聴きながらバスで一本松を見に行きました。一本松はたくさんあった松の木の中から残った最後の松の木でした。ですが、どうしても木がだめになってしまったので今は葉っぱなど人工的につけているそうです。私も一本松はずっと残していってほしいと思います。陸前高田には津波の勢いを今見て分かるほどの損傷がある建物が残されています。けど、それはあの日のことを忘れないために必要だと思いました。 その次はフェリーにて大島の牡蠣の養殖所に行きました。今回はフェリーを使いましたが地域の方とフェリーの待ち時間の間話をしていたら、橋ができたからフェリーはなくなると聞いたので少し寂しいと思いました。フェリーでは大島へ行く他の方とも色々な話を聞くことができました。 牡蠣の養殖所までは歩いて山登りで行きました。着いてからは4班に別れて4つの作業をしました。まずは生食牡蠣用の牡蠣を入れる袋にシールを貼る作業でした。この作業は人手が足りないと時間が凄くかかると思いました。次に草刈りをしました。草刈りをした場所は斜面が少し急でちょっと危ないなと思いました。その次は船に乗って牡蠣がどのように養殖されて、どのように育っているのかを見に行きました。ひとつのロープにたくさんの牡蠣が着いていて、ワカメもたくさん着いていましたがワカメは自然と落ちるそうです。あと牡蠣は最初は雌雄があるらしいですが、途中から中性になると聞いて驚きました。次は船から降りて牡蠣の養殖所の方が作って下さった蒸しガキを食べさしてもらいました。その場で出来立ての蒸しガキを食べるのは家で食べるよりも美味しく感じました帰りも同じ道の山登りをしてフェリーで帰りました。作年はほとんどが草刈りだったので新しいことができてよかったですし、もっと何かしたいと思いました。 最終日の17日は気仙沼高校の方との交流会です。大阪と気仙沼では話していてもあまり変わらないですが、ゲームなどをすると言い方が違ったりして勉強になりましたし、面白かったです。班で行った交流では夏休みについてでした。私が1番驚いたのは学校帰りに海によると答えていたので、大阪ではまず無いなと思いました。あとは、アイスやお祭りなど私たちと変わりませんでした。今回の交流では知らなかったことを知ることができましたし、もっともっと力になってあげられたらいいなと思いました。 今回の気仙沼ボランティアで私は出来ることを探すではなく、私たちがやるべきことをするを心に思って参加しました。私は来年も参加しようと思っているのでもっと宮城の方力になれるよう頑張っていきたいと思います。 |
|||
| これまでの気仙沼ボランティアを通じて Etsu Yukino 一番最初に思ったのは前よりかなり風景が変わったなと思いました。2年生の時は1年前と変わってないと書きましたが、今回はかなり変わってました。特に今まで無かったスーパーやコンビニは勿論、土だけの所が嵩上げされて建物が建っていたりしていました。砂利道がちゃんと道路になっていたり、細かいところまで変わっていました。今回で復興した、という実感は見受けられました。 1日目はリアスアースで当時の気仙沼の写真などを見せて頂きました。1つ1つの写真に撮った人の解説、心情が書いてました。とても心にくるものがありました。今まで瓦礫と言っていたものを何故被災物というのか、それは1つ1つに愛着があり、本当に大切なものだったということです。普段使っているため、考えを改め直す機会にもなりました。もっと早くに訪れたかったです。 続きで、植林のお手伝いをさせていただき、1年、2年の時に植えた木を見ることができました。そして今回はご好意で梅の木も植えさせていただきました。3年はこの梅の花が咲くのを見ることができませんが、2年生に託しました。もっと木が沢山生えたら、もし津波が来てもこの私達が植えた木で助かる人が1人でも多くいれば、植えた甲斐があると思います。いや、その前に嵩上げなど行っていますので、津波は来ないでほしいです。津波対策のためにではなく、自然が多い街としていてほしいです。 2日目は奇跡の一本松の所に行き、講演会を聞きました。今年からまた松の木を植えて、震災前の姿に戻そうという話を聞き、それは一年前よりも前進していると思いました。木の成長とともに、人々も成長していく姿が見受けられました。50年後になるみたいなので生きてるうちに見たいです。綺麗な砂浜と海、ボランティア行ったときとは違うな、震災前の姿だなとこの目で見たいです。そして、いつもお世話になってる大島の牡蠣の養殖に行きました。娘さんが大きく育った姿を見てほっこりました。いつもよくして頂き、最後まで手を振ってお見送りをして下さりました。もう中々会えないので、せめて牡蠣の購入をしたいと思います。それが私ができるものと思いました。 3日目の朝、2日間お世話になったホストファミリーの吉田さんとお別れしました。3年になったため、もう気仙沼に行くこと、皆さんとなかなか会えないと考えたら心寂しかったです。しかし私達が行かなくてもいい時が来たら、それは復興したといっていいと思います。気仙沼高校さんとも交流をさせて頂き、明るい生徒さんが多く、大切なひと時となりました。お土産の笹かまを買う時、気仙沼高校の男の子が、友達が笹かまを作ってると聞き、そこで作られてる笹かまを買いました。それが少しでもものになればと思います。 今回で気仙沼ボランティアは私は終わりですが、気仙沼以外にも北九州のボランティアに行きたいと思います。その思いは何故出てきたのかといいますと、3年間ずっとユネスコ部として、1人の人間として役に立ちたいと思ったからです。これからボランティアは何処でやればいいのか分かりませんでしたが、箕面のユネスコ協会があると聞いて興味を持ちました。私がこれまで培った経験を生かし、更に役に立てればと思いました。 こうやってボランティアをするにあたり、人の温かみを知るのは大変素晴らしい機会となりました。もしどこかで誰が募金活動やボランティア活動を行っている際は、気持ち程度になるかもしれないですが、協力させて頂こうと思うようになりました。大学生になったら海外に留学に行きたいのですが、もし可能であれば海外でもボランティア活動をを行い、それを日本で伝え、日本でも日本で必要としているボランティアがあればそこに行きたいです。 それと、今回のボランティアに関係ないかと思いますが私が嬉しかったことがあります。それは後輩と沢山話せたことです。ボランティアを通じてこんなにも仲良くなれたのは大変喜ばしいことでした。そして後輩に来年も行くのか聞くと、行きますという声が多かったことです。3年間ずっと行ってきて、今回受験があるからやめておこうと思いました。しかし、民泊で寝る前にやったりして時間はあったので、3年間貫き通すというのが私の中ではとても大切なものになりました。今2年連続で行っている後輩には是非とも3年間行ってほしいですし、2年からの参加でも3年生になっても行ってほしいです。そして先頭を切って皆を引っ張っていってほしいです。 |
|||
| 旅 Uto Moe さて!始まりました東北への旅!私が見て、聴いて、感じたことを今からみなさんにお伝えしましょう〜! まず最初は北摂つばさ高校への道のりです。ここから私たちの旅は始まりました。満員電車でもみくちゃにされ、バス停が見つからずウロウロしたり今になればこれもまたいい思い出です。 いざ、宮城へついてみると見る限り平地!平たい!そしてベルトコンベアーなどの大きな自動車!7年たった今でも復興ってまだまだ終わらないんだなと初めて感じた瞬間です。同時に防災庁舎の低さにも驚きました。あの低さの建物が1番高い場所だったなんて大阪に住んでいる私たちからしたら信じられませんでしたね。 ちなみに私美術館大好きなんです。だから美術館に行けるってしおりで見た時すごく嬉しかったんですよ。リアスアーク美術館。とっても素敵な美術館でした。一つ一つの写真に解説があり、一つ一つの被災物に物語があり。頭の中にその情景が思い浮かぶような、不思議な感覚を体験させていただきました。子供用の自転車の被災物を見たとき何故かわかりませんが私は鳥肌が立ちました。 海辺の森を作ろう会では植樹を体験させていただきました。木の苗を植えるのは初体験ですごくワクワクしたんです。自然と触れ合うその瞬間がとても幸せな時間でした。実のなる木を植えることによって未来へと残すことができると聞いたとき感動しました。すっごく苦労してこの答えへと辿り着いたんだろうなと考えると私たちが植えた木の苗、大きく大きく育ってほしい。そう切実に思います。 植樹したあとに周辺を散策しました。歩きながらメンバーの1人と喋っていました。自分の想いだけでなく、人の想いも聞いてより一層想いが深まりました。8人の命を救った椿。椿も、椿に必死にしがみついた8人も絶対に生き残りたい!絶対に助かって家族に会うんだ!そんな想いがあったからこそ生き残れたんだと思います。海が人の命を奪い、木が人の命を救う。私たちは自然に生かされているのです。 話が変わりますが、みなさん民泊をしたことがありますか?そうなんですよ、私たち民泊をしてきたんです。民泊先のお母さん、お父さんがすっっごく素敵な方でしてね〜。沢山お話させて頂いたんですが、"意識を持って行動しないといけない"という言葉が心に残ったんですね。やはり、それなりに平凡に生きていくってのもいいと思うんですが、どうせなら人一倍楽しみたい!人一倍経験したい!と思うんですよ。だから何事にも意識を持って行動したいです。 お父さんは趣味が沢山あってですね、化石や工作などですね。私たちもお父さんと工作したり化石を触らせてもらったりしたんですが、私が1番楽しかったことは、葉っぱの葉脈だけを残して乾燥させて栞やらなんやらと作ったことですね。あとキーホルダーも作ったんですよ。お父さんのところへ民宿しないと体験できないようなことばかりです。 お母さんはなんと言ってもご飯が美味しい!もう絶品!大阪に持って帰りたいくらい…。自家製のお野菜もとっても美味しかったです。大っきなキュウリに味噌をつけてかぶりついたりもしましたよ。噛んだ時いい音でした。あとはお父さんと同じくお母さんも手先が器用なんですよ。手毬や、オリガミでくす玉、タオルで象さんを作ってたりと見てて楽しかったです。オリガミを私たちは教えてもらいました。大阪に帰ったらもう一度作ってみたいですね〜。お父さんお母さんありがとう! 奇跡の一本松ってレプリカなんですね〜。でもすごいですよね。あの津波から生き残ったんですよ。名前の通り本当に奇跡ですね。私のあの松のような生命力がほしいです。そうそう!私牡蠣って好きじゃないんですけど大島の牡蠣は美味しいですね。あんなに大きな牡蠣は初めて見ました。大阪にいるお母さんが牡蠣大好きなので食べさせてあげたい〜! 気仙沼高校での交流会でまアイスブレイクや、ポスターセッションをして交流を深めました。やることが松高と似ていて親近感が湧きすっごく楽しかったです。遠い土地で育った人たちでも同じ年代ってだけでこんなにもすぐ仲良くなれるなんて素敵だなって、この出会いを大事にしたいなって、そう思います。 さあさあ、みなさんお待ちかねのお土産タイム!たくさん買いました?大事な人たちへ買えました?もちろん私は買いましたよ〜!友達の分を買い忘れたなんて内緒ですよ。あとでサービスエリアでコソッと買います…。 正直、北摂つばさや春日丘の生徒のみなさんとここまでお話をしたり一緒にお土産を見て回ったりなんて出来ると思ってなかったのですごく嬉しいです。もっと長い期間一緒に過ごしたかったです。このような活動に参加させていただけてすごく感謝しています。ありがとうございました!最高!頑張ろう日本! |
|||
| 気仙沼ボランティア Dote Mimini 今回、私は2回目の参加だったけど、去年とは違うことを感じました。民宿先が違うってゆうのはもちろんあったけど、それ以外にもバスから見える風景とかがすごく変化しているなって思いました。去年は盛土してなかった所が、盛土されていたり、防潮堤が出来ていて海が見えなくなっていたりその他にもたくさんの場所が変わっていました。防潮堤で海が見えなくなっていたのはすこし残念でした。でも、また津波が来たらって考えたらやっぱり必要なのかなとも思いました。 去年は行かなかったリアス・アーク美術館に行った時に主観的な意見が載っていてその文章を読みながら確かにこんなことになったらそう思うなっていうものが多くありました。もし、震災が来て家が流されて家族がいなくなって…って考えたらすごく悲しいしもう立ち直れないなって思いました。なのでそんなすごい被害にあっているのに立ち直っているのがすごいなって思いました。でも、その展示の中で「内面と外面は違う」って書いてある文章があってそこに、「ボランティアに行った人達が被災地の人たちに元気をもらったと言っていました。」って書いてる文章があってその下に「でも、それは外面で、内面は違うこともある。」って書いてあって、やっぱりそうだろうなって思った。家族とか家がなくなったのにいくらボランティアで来てくれた人達だといってもにこにこした笑顔を振りまけるわけがないと思いました。自分やったら笑うことも出来なくなるだろうなって思いました。 「海辺の森を作ろう会」の植林活動では、去年とは違うところに木を植えて、去年の木が成長している姿を見ることができてよかったです。今年植えた木も来年行った時にどれだけ成長してるか楽しみです。民宿先では、家も広くてとても楽しく過ごさせてもらいました。美恵子さんと、お父さんとの交流もいっぱい出来て楽しかったです。みんなでトランプしたりとか色々学校の話とかして本当におばあちゃん家に来てるみたいで楽しかったです。ブルーベリーを収穫させてもらって、それを食べさせてもらって美味しいのとか酸っぱいのとかいろんな品種のものがあって美味しかったです。カモシカの話とかニホンジカの話とかもしてもらって色々知れました。ご飯もとても美味しかったです。また来てねって言ってくれて本当にまた行こうと思いました。本当に色々優しくしていただいて楽しく過ごせました。ありがとうございました。 3日目は陸前高田でガイドさんの話を聞き、奇跡の一本松を見たあとフェリーに乗って大島に行きました。大島の橋が完成したら、フェリーが無くなるから乗れるのはこれが最後になるのかな?って思いながらフェリーに乗りました。カモメにカッパえびせんをあげたら手を噛まれたりとかしたけど可愛かったし楽しかったです。牡蠣の養殖場は、雨が降っていたので去年しなかったシール貼りの仕事があって楽しかったです。でも、あの作業をずっとしてたら疲れるし飽きるだろうなって思いました。去年たべれなかった牡蠣が食べれて美味しかったです。牡蠣のイカダが竹のものよりプラスティックのものの方が7か、8倍の値段だって聞いた時は高!って思いました。その他にも牡蠣の事を知れてへぇーって思うことがありました。 4日目は気仙沼高校に交流をしに行きました。去年はなんかよくわからなくてどうしたらいいのか分からずみ、え?ってなりながら終わってしまってあんまりいい思い出じゃなかったけど今年はアイスブレイクの時からいろんな人としゃべれて楽しかったです。夏といえばって言うテーマでみんなで意見を出し合うやつはよく考えたら夏って言われて思いつくものってそんなにないかもって思いました。でも、みんな違う意見があって思った以上に夏についてのものがあってびっくりしました。方弁とかでこれわかりますか?とか言って遊んでる時にいっせーのーで!ってやるゲームの話が出て向こうではチュンチュンって言うって聞いてびっくりした。それで、9人でやってみたら思った以上に合わなくてなかなか終わらなかった。でも、合わないことが逆に面白くて楽しかった。今年は気仙沼高校との交流がいい思い出になってよかったなって思いました。 最後に、今回の気仙沼現地ボランティアで思ったことは6年ぐらい経って景色も風景も変わってただ、開拓してる街にしか見えないような感じだけど、行方不明の人もいるし家が流されてまだ自分の家に住んでない人もいる事がとても悲しいことだなって思いました。いくら復興してるって言ってもやっぱりまだまだ復興してないのかなって思いました。むこうの人が笑顔で話しかけてくれたり、震災のこととか教えてくれたりするけどその中にはまだ、傷が癒えていない人がいるんだなって思いました。これからも自分がなんの役に立つか分からないけど少しでも何かの役に立てたらいいなと思って色々なことに取り組んでいこうと思います。 |
|||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)