1.はじめに
新学習指導要領には,社会の変化に対応する教育として環境教育や情報教育などが重要な教育課題として挙げられており1),総合的な学習の時間などでも扱うこれらの教材開発や学習指導法の研究が必要となっている.
最近,環境を扱った理科と取り組む小・中学校の数は増えており,パックテストによる水質調査,気体検知管を用いた大気調査の他,本誌で紹介したコンピュータ計測による環境調査2)も行われている.
通常,これらの活動では,学校や校区内などの限定した範囲の環境を調査するのがほとんどである.しかし,環境教育の視点は「地球規模で考え,足もとから行動する」と言われるように,校区など「足もと」の活動から,他の校区・地域さらに日本へと考察する範囲を広げることが重要である.
インターネットは,文字情報をはじめ,動画や音声など様々なマルチメディア情報が取り扱えるので,測定された多種多様な環境情報の発信・受信が可能である.そこで,学校で得られた環境情報をインターネットで発信し,相互に活用することで情報の共有化を図った.この結果,環境調査を実施した範囲だけで環境問題をとらえるのではなく,インターネットによる情報交換を通じて,地域を広げて環境問題について考えることができる.
今回,環境問題において,このようなグローバルな視点の育成をねらいとするホームページを開設し,インターネット上で環境情報の交流を図る中学生の活動を試みた.インターネットで水質調査の結果を公開し,ネット上で他校との情報交換を図りながら,環境調査を通して生じた疑問への回答も得ることができた.本稿では,インターネットによる環境情報の活用をめざした指導法の実践を報告する.
2.インターネットによる環境情報の活用
(1) 環境情報の活用を図るホームページ
平成8年12月に開設した「子ども達が測定する大阪の環境」3),比色計とコンピュータを用いた環境調査の方法を紹介し,大阪府内の小・中学校での実践結果を掲載している4).このホームページに環境情報の交換を図る掲示板を追加し,各学校の測定データを送信してもらって公開する形式にした(図1).
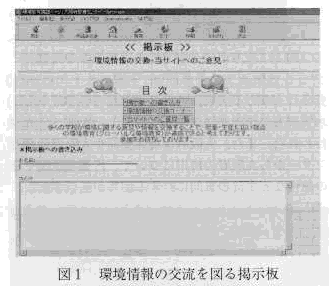
図1 環境情報の交流を図る掲示板
(2) 中学校での水質調査と情報発信
これまで3年選択理科で,校区の自然環境を調べる「環境コース」を設け,コンピュータ計測により大気中のNO2や,CODやNO2−などの水質調査を実施してきた.今回,1年の理科一分野の単元「身近な水を調べる」の発展学習として校区を流れる安威川の水質調査を行った.調査項目はNO2−である.測定したデータと,これまでのデータを合わせて,「子ども達が測定する大阪の環境」に測定情報を発信した(図2).また,調査活動を行う中で生じた生徒の質問を掲載し,広く他からの回答を求めた(表1).
表1 掲載した質問の一部
| ・なぜ下流に行くにつれて水は汚くなるのか。 ・日本で一番きれいな川と汚い川はどこか。 ・安威川は大阪では汚い方の川にはいるか。 ・なぜ大和川はこんなに汚れているのか。 ・安威川をきれいにする方法はなにか。 ・世界で有名な川の汚れの濃度はどれくらい。 |
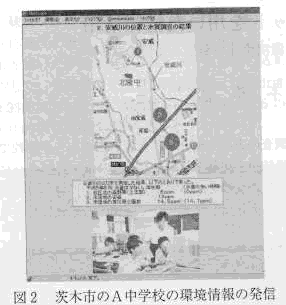
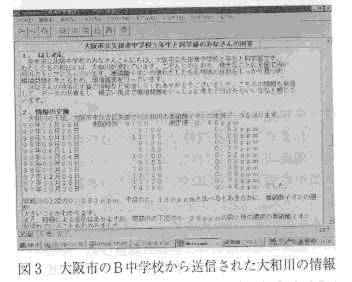
3.授業実践
(1) 全体の指導計画
実践した内容は次のとおりである.
第1次:安威川の水質調査(1時間)
比色計を用いたコンピュータ計測により,ザルツマン法で河川水のNO2−を測定する.
第2次:インターネットによる情報交換(2時間)
1限目は,ホームページの掲示板に測定情報を発信し,掲載した画面と他校の測定結果を比較・考察する。2限目は掲載した質問に対する回答や,外からの情報を見て環境問題に関する理解を深める.
なお,実践校では電話回線の設備がないため,固定ディスクにホームページを取り込み,プロジェクターで画面を拡大して学習を行った(図4).
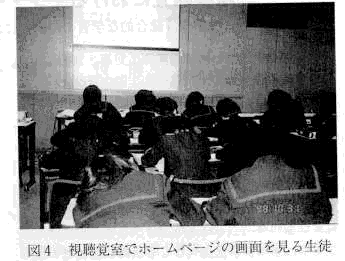
図4 視聴覚室でホームページの画面を見る生徒
(2) 実践結果
インターネットの活用に対する生徒の感想をアンケートで調査したところ,ほぼ100%の生徒がインターネットの活用に肯定的であり,何らかの形でインターネットとかかわりを持つことを期待していた.
また,自分たちの質問に対して,他から回答が返ってくることを大変喜び,意欲的に学習し,環境への理解も深まったと思われる.さらに,環境への関心も高まり,生徒の希望により水質調査に続いて大気中のNO2の測定も3学期に行うことになった.
4.まとめ
今回のインターネットの活用では,他校との環境情報の共有化や,公的機関からの情報受信により,環境についての広い視野の育成と環境への理解を深めるねらいは,ほぼ達成できたと判断する.高度情報通信社会を象徴するインターネットの普及はここ数年急速であるが,本実践ではインターネットが情報活用の手段として有効であることが分かった.
また,総合的な学習の時間の実施とともに,教科を越えた国際理解や環境・情報などの課題別の学習が必要であり,今後,インターネットはこのような学習活動の有力な手段の一つになると予想する.
付記:本研究は平成10年度日本生命財団研究助成(紺野)及び平成10年度文部省科学研究費補助金奨励研究B課題番号10907067(芝本)を受けている.
引用文献
1)文部省:小・中学校学習指導要領(1998.12)
2)紺野昇:大阪と科学教育,9,23(1995)
3)http://www2j.biglobe.ne.jp/~kankyo/kankyo0.htm
4)紺野昇:大阪と科学教育,11,9(1997)