1.はじめに
(1) コンピュータ計測による実験
ここ数年,社会構造は急激に変化しており,高度情報化の流れはますます進展し,複雑化している.これらの社会変化に対応する人材を育成するため,21世紀へ向けての教育改革のガイドラインである文部省の教育改革プログラム1)や新学習指導要領では,学校の教育内容の再構築の一つとして情報教育の充実を挙げている. 情報化に対応する教育は,特定の教科で行うのではなく,すべての教科で取り組む必要があることはいうまでもない.これまで,高校化学における情報化への対応として,化学の学習内容をより深め,生徒の情報活用能力の育成をねらいとするコンピュータ計測の教材を本誌で報告してきた2)3).これらの教材により,実験授業が効率よく進められ,生徒の実験への意欲も向上することが分かった.今回,化学反応速度を正確に測定する教材として,自作光電スイッチを用いたコンピュータ計測のシステムを開発したので報告する. 化学Ⅱの単元で扱う化学反応速度の実験は,化学変化の速さと反応物質の濃度及び温度との関係を調べるものである.従来,反応速度を測定する実験では,速度の値を求める実験結果の計算処理が煩雑で,その解析に時間がかかり,1時間の授
業の中で測定から考察まで行うのは困難で,実験結果の考察を深める余裕はなかった. コンピュータを実験の計測及び測定データの解析に用いると,実験の測定から考察までが1時限の授業の中でスムーズに行うことが可能になる.さらに,測定データのグラフ化などを行う専用の解析ソフトウェアを用いると,速さと濃度との関係や,速さと反応温度との関係がグラフで分かりやすく学習できる.この結果,生徒には実験結果の理解が容易になり,十分な考察が期待できる.
(2) 化学反応速度を調べる実験
化学Ⅱの教科書を調べると,現在掲載されている化学反応速度を調べる実験は次の3つのタイプに分類される.
①ヨウ素酸カリウム水溶液とデンプンを含む亜硫酸水素ナトリウム水溶液によるヨウ素デンプン反応(時計反応)
②チオ硫酸ナトリウム水溶液と塩酸による硫黄ゾルの生成反応
③各種触媒を用いた過酸化水素水の分解反応
このうち,③の過酸化水素の分解反応速度の測定は,本誌第8号で報告した. 今回,①と②の反応速度を測定するために,反応溶液の色変化を検知するコンピュータ計測用の自作光電スイッチと,その制御用プログラム及び測定データのグラフ化を行う解析プログラムを制作した.
2.実験方法
(1) 光電スイッチを用いる測定のねらい
上記の①及び②の反応速度を調べる実験では,化学変化の過程で起こるヨウ素デンプン反応の呈色や,硫黄ゾル生成による溶液の懸濁までの時間を計測する.そのデータ処理として反応の速さを計算した後,溶液の濃度や反応温度との関係を学ぶものである. 生徒実験では,①の場合,ヨウ素デンプン反応が急激なために色変化が突然起こり,反応時間の測定が間に合わない場合があった.逆に,②の硫黄ゾルの反応では,硫黄の生成がゆっくりで白濁が徐々に起こるため,どの時点の白濁を反応時期とするかの判断が困難で,個々の生徒の測定誤差(測定のバラツキ)が大きかった. そこで,ヨウ素デンプン反応の突然の色変化や,硫黄ゾルの生成反応で一定量の白濁を感知してスイッチが入る光電スイッチを自作した.これをセンサーとして,コンピュータ計測で行う化学反応速度の測定装置が図1である.光電スイッチは発光ダイオードの光を反応溶液に照射し,溶液の色変化や白濁が起こったとき透過光の変化を感知する装置で,コンピュータは感知信号を受けるまでの反応時間を測定する. この装置を用いると,②のようなゆっくり白濁する反応では,透過光の測定により一定量の白濁で光セ
ンサーのスイッチが入るので,反応条件の均一化が図られる.したがって,一定量の反応時期の判断ができるので,測定誤差が減り,正確な実験が可能になる.
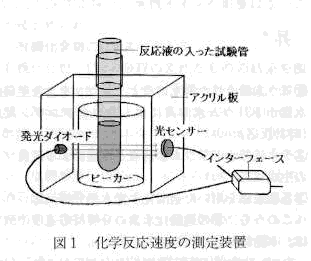
(2) 自作した光電スイッチのしくみ
今回の光電スイッチは,赤色高輝度発光ダイオード(GL5LR40)とCdS光センサー(p368)を,図1のとおり組み合わせて製作した.測定データは,デジタルデータとしてコンピュータのマウス端子またはシリアル端子から入力する.コンピュータと接続するインターフェ-スは,杉本4)の開発したデジタル入力方式の回路である(図2).したがって,A/D変換器を使用せず,安価で簡単に製作できた.このスイッチは,入力端子を変えることで,NEC-PC98系機種やDOS/V機など多くのコンピュータで使用できる.
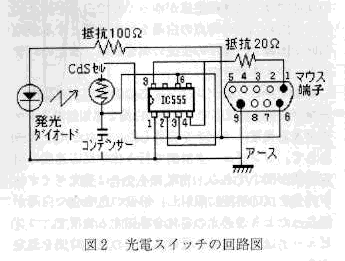
(3) 実験内容
a.ヨウ素デンプン反応(時計反応)
教科書に掲載されている次の手順で行った. 反応速度と溶液濃度との関係を調べる実験では,0.01・0.02・0.03・0.04・0.05mol・dm-3の5つの濃度のヨウ素酸カリウム水溶液を準備する.各5mlを試験管に取り,これを速度測定器にセットする.測定プログラムを起動させた後,この中にデンプンを含む
0.025mol・dm-3の亜硫酸水素ナトリウム溶液5mlを加え,ただちに測定プログラムを実行させる.コンピュータは,ヨウ素デンプン反応の着色が起こるまでの時間を測定する.濃度を変えて以上の実験を繰り返す. 反応時間を求めた後,濃度の異なる5つの実験結果をデータ解析プログラムでグラフ化し,反応速度と濃度との関係を学ぶ. 反応速度と反応温度との関係を調べる場合では,速度測定器のビーカーの中の水の温度を変え,しばらくの間両液をこの中に入れて一定温度にした後,両者を混合させて同様の実験を行う.
b.硫黄ゾルの生成反応 反応速度と溶液濃度との関係を調べる実験では,0.04~0.2mol・dm-3
の5つのチオ硫酸ナトリウム溶液10mlを試験管に取り,速度測定器にセットした状態で4mol・dm-3の塩酸5ml加え,直ちに測定プログラムを実行させる.白濁するまでの時間を実験a.と同様に測定する. また,反応温度との関係を調べる実験では,速度測定器内のビーカーの中の水の温度を変えて,同様に実験する.
(4) 反応速度を求める計算
化学反応における速度は自動車の速度と違って,反応溶液における濃度変化の速さである.本実験の結果より反応速度を求める方法は,教科書では反応溶液が着色または白濁するまでの時間(秒)を測定し,その逆数を反応速度としている. 最も簡単な近似として,ある物質Aが反応して物質Bになったとする.時刻t1
での反応物質Aの濃度を[A]1,変化した後の時刻 t2 での反応物質Aの濃度を[A]2
とすると,反応速度は単位時間に減少する反応物質濃度の変化量であるから,次式で与えられる.
[A]2 -[A]1
V=-─────────
t2 - t1
本実験では,([A]2 -[A]1 )が一定値に達したときに着色や白濁が起こり,反応速度は式の分母の項(t2 -t1) だけで求められることを前提にしている.したがって,(t2-t1)の項は着色または白濁までの時間で,その時間を測定し,逆数を求めて反応速度が算出できる. (5) 開発した計測及び解析のプログラム 測定プログラムは,光電スイッチで感知した光の変化を受信して,それまでの時間を求めるソフトウェアである.測定した時間は,数値で表示する他に経過時間を棒グラフで示して画面上に見やすくした(図3).これらは,N88-日本語BASIC(86) 言語で作成した.
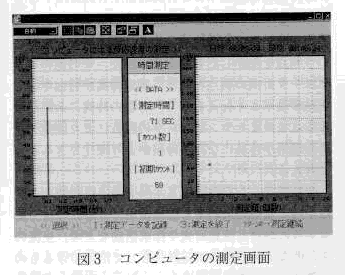
測定データの解析プログラムは,反応時間を入力すると,その逆数を計算して反応速度と溶液の濃度及び温度との関係をグラフ表示するソフトである.このとき,最小2乗法により反応速度と濃度との関係では回帰直線を画面に表示し(図4・6),温度との関係では非線形回帰分析により最も近似する曲線を表示する(図5・7). このソフトウェアにより,反応速度と濃度が一次直線の関係になることや,反応速度は温度上昇により比例関係以上に急激に大きくなることが容易に理解できる. なお,これらのソフトは無償で提供している.
3.実験結果
(1) ヨウ素デンプン反応(時計反応)
本装置を用いて,反応速度と溶液濃度との関係を調べる実験を5回行った.その測定値の平均が表1である.これを解析プログラムによりグラフ化したのが図4である.
この実験の相関係数は0.9986で,反応速度と濃度の関係には,たいへん良好な直線関係が得られ,反応速度と濃度との比例関係が容易に理解できる.表1
濃度との関係を調べる実験結果(5回の平均)
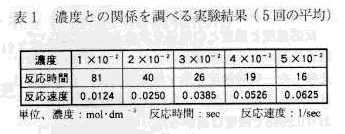
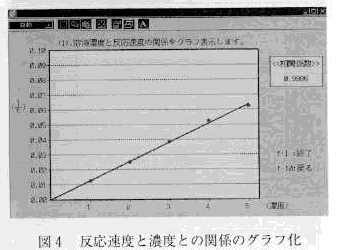
また,反応速度と反応温度(13~67℃)との関係を求めた実験の結果が表2である.この結果をグラフ化したところ図5のとおり,温度上昇により反応速度が増大する様子が分かった.
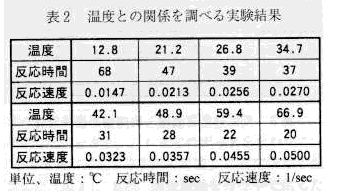
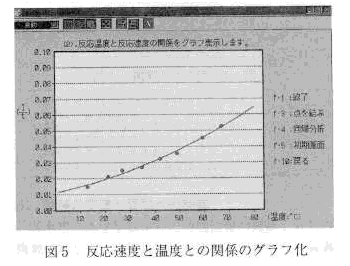
(2) 硫黄ゾルの生成反応
反応速度と濃度との関係を求める実験において,時計を用いた手動測定とコンピュータ計測の結果を比較した.実験精度を示す相関係数は,手動計測では0.9865であったが,コンピュータ計測は図6のとおり0.9948で精度は高かった.
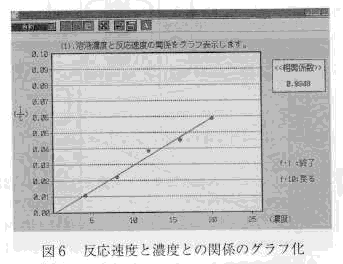
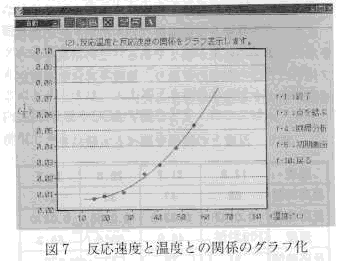
今回の白濁状況の判定をするような,あいまいさを伴う実験では,コンピュータ計測の有効性が認められる. 反応速度と温度との関係を調べた結果が図7である.15~55℃の間で,急激に反応速度が増大することが分かった。これにより,反応の種類によって温度の影響の仕方が異なることも学習できる.
4.おわりに
これまでのコンピュータ計測の教材をみると,温度センサーによる温度測定など,測定精度が高いという利点を生かしたものが多かった.その他のコンピュータ計測の利点として,測定時間が短縮できて実験が効率よく行えるので,考察の時間に余裕ができること,またコンピュータの解析により測定データの理解が容易になり,考察がより深化できることと考える. 今回開発した自作光電スイッチは,色の変化や沈殿が起こる他の反応でも広く使用できる.今後,高等学校における課題研究や探求活動などで,生徒の主体的な実験活動の測定教具として活用できるものと期待している.
引用文献
1)文部省:教育改革プログラム(1998.5改訂)
2)紺野昇・利安義雄:大阪と科学教育,8,27(1994)
3)紺野昇:大阪と科学教育,9,23(1995)
4)杉本良一:日本化学会 化学と教育,41,558 (1993)