
6-1 気体発生装置の種類
(1) フラスコを使った気体発生器
① 図22のように、三角フラスコ(または丸底フラスコ)を使って気体を発生させる。
② この場合、安定をよくしてフラスコが倒れないように気をつける。
③ 液体試薬は、固体試薬がつかる程度に入れるようにする。
④ 活栓付きロートを使用している場合で、気体の発生を一時中止するときは、まず活栓を開
き、次にゴム管をピンチコックなどでつまむ。
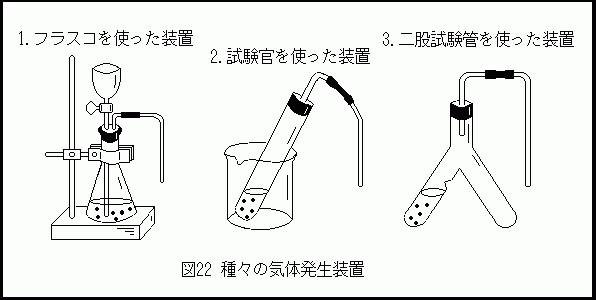
(2) 試験管を使った気体発生器(図22)
① 小規模の場合は、試験管を使って気体を発生させることができる。
② この場合は、気体の発生を途中で止められないのが欠点である。
(3) ふたまた試験管による気体発生器(図22)
① 試薬が少量の場合に適している。
② ふたまた試験管の2本の足のうち、くびれのある方に固体試薬を入れひっかけて固体が落
ちないようにして使う。液体試薬は、くびれのない方に入れる。
③ 左右に傾けて試薬を混合し、気体を発生させる。
④ 発生を中止するときは、試験管を傾けて液体と固体を分離する。
6-2 気体の捕集方法
(1) 下方置換法(図23)
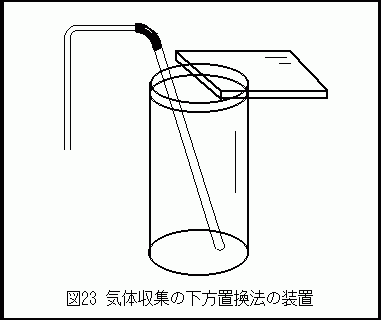
① 二酸化炭素、塩化水素など、水によく溶けて空気より重い気体を集めるときに行う。
② 集気びんの口を上にしておくと、空気は軽いのでびんから逃げやすくなる。
(2) 上方置換法(図24)
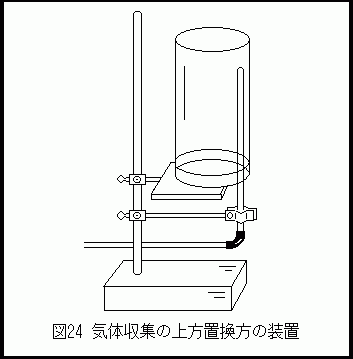
① アンモニアのような、水によく溶けて空気より軽い気体を集めるときに行う。
② 集気びんを逆に立てるので、軽い気体は上にあがり、重い空気が集気びんの口から逃げや
すくなる。
③ 気体を集めた集気びんは、蓋を下にして逆にしておく。
(3) 水上置換法(図25)
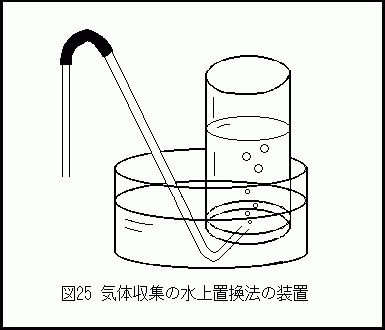
① 酸素、水素、二酸化炭素(下方置換法でもよい)など、水に溶けにくい気体を集めるとき
に行う。
② 水槽に水を入れ、水を満たした集気びんを逆さに立てる。この中へ、気体を導いてためる。
③ この方法は空気が混じりにくく、気体がたまっていくようすがよくわかるのが利点である。
④ アンモニアや塩化水素などは、水によく溶けるので、この方法は不適当である。
6-3 気体発生に関する実験上の注意事項
(1) 水素などの可燃性気体の爆発事故防止について
① 爆発事故の多くは、空気との混合気体が引火爆発する場合である。気体発生器から最初に
出てくる気体には空気が残っており、これに引火した場合に爆発を起こす。したがって、気
体の組成が下記に示す爆発範囲を越えるまで、流出してくる気体を捨てる必要がある。純粋
な気体を得るには、気体の種類などにより異なるが、発生器の容積の2倍以上捨てなければ
ならない。
| 可燃性気体の爆発範囲(空気中の体積百分率(%)) | ||
| 水素 4.0~75 | メタノール 7.3~36 | 一酸化炭素 12.5~74 |
| メタン 5.3~14.0 | エタノール 4.3~19 | アンモニア 16~25 |
| プロパン 2.4~9.5 | エ-テル 1.9~48 | ベンゼン 1.4~7.1 |
② 点火法による確認方法(図26)
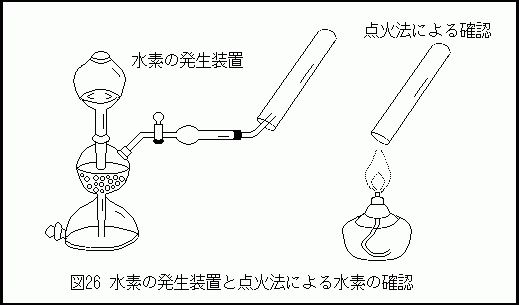
発生した水素を試験管にとって点火する。試験管中の水素が爆発範囲内の組成であれば爆
発が起こる。純粋な水素であれば、管口でポッと軽く点火して燃え、あと、試験管内に燃え広
がるが爆発しない。
(2) 酸素発生での注意事項
① 過酸化水素水(H2O2水)は、冷暗所(冷蔵庫がよい)に保管する。
② 高濃度の過酸化水素水をうすめるときは、できるだけ純水を用いて、手や顔にかからない
ように注意する。
③ 30%過酸化水素水をうすめた水溶液は、分解しやすいので、実験をする直前に調製する。
数ヶ月も同じ濃度で保存できると考えてはいけない。
(3) その他の注意事項
① 発生する気体が有毒である(アンモニア、塩化水素など)場合は、必要最小限の量だけとる
ようにするとともに、室内の換気には十分に注意する。また、発生器の吹き出し口に顔を近
づけないようにする。
② 発生器のゴム管などが折れ曲がったり、ねじれて気体の発生をさまたげたりすると、ゴム
栓が飛んだり、容器が破裂するなどの危険があるので、十分に注意する。
③ 可燃性気体を発生させるときは、引火爆発の危険を避けるために、発生器にバーナーやア
ルコールランプの火を近づけないようにする。
6-4 気体の乾燥
(1) 小・中学校で行う理科実験では、不純物を取り除く必要はほとんどないもし純粋な気体が
必要なときは、試薬の純度が高いものを選び、含まれてくる水蒸気は乾燥剤に通せばよい。
(2) 乾燥剤は、気体の種類に注意して選ぶこと。乾燥剤なら何でもよいというわけではない。
次の乾燥剤が適している。
◆水素、酸素、二酸化炭素 ・・・ 無水塩化カルシウム、シリカゲルなど
◆塩化水素 ・・・ 無水塩化カルシウムなど
◆アンモニア ・・・ ソーダ石灰、生石灰など
(3) 気体乾燥(洗浄)の方法
アンモニアや塩化水素の気体を発生させるときは、図27のように、濃アンモニア水や濃塩酸
に沸騰石を入れて加熱してもよい。ただし、三角フラスコの口には乾燥剤を付けておくこと。
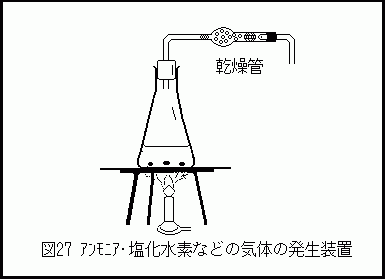
6-5 その他
(1) 気体発生装置を組まなくても、酸素、窒素、二酸化炭素などの気体は、市販の小型軽量ボ
ンベ(スプレー式軽量ボンベ)を利用できる。ただし、気体の発生は、化学反応させて気体
を得ることに意義がある。小学校で、はじめからボンベを使うのはよくない。
(2) 酸素や水素を多量に早く集めるには、酸水素発生用電解装置を自作するとよい。電極表面
積を大きくすると、たやすく得られる。