2.有孔虫類
石灰質の殻を持つ原生動物で,生存中は殻に開いた孔から擬足を出して食物を捕える.死後は殻だけが残り,海底に集積する.
殻は,旋回しながら次々と室が付け加わって成長していくので,多くの殻室に分かれ,一般に紡錘形になる.また,その構造は進化とともに複雑化しているので,分類の目安とされる.
有孔虫類の中では,特に,古生代後期のボウスイチュウと新生代古第三紀のカヘイセキとが示準化石として重要である.また,ホシズナは現生有孔虫の一種である.
(1) ボウスイチュウ(紡錘虫)
石炭紀初期末に出現してペルム紀末に絶滅した.約100属3,600種以上に分かれ,また,分布も汎世界的であったことから,紡錘虫化石帯は,石炭紀〜ペルム紀層の世界的な対比や細分に用いられる.
図-001:フズリナ[
Fususina itadorigawensis],石炭紀,愛媛県産.
aは標本全体を撮影したもの.フズリナは小さいので,注意深く見ないと分かりにくい.
bは標本の一部を接写したもの.
cは更に接写したもので,殻の断面が示されているが,小さく(目盛りは,各線間が1mm),構造も単純であることがわかる.
図-002:プセウドドリオリナ[
Pseudodoliolina pseudolepida],ペルム紀,カンボジア産.
aは標本全体を撮影したもので,風化によって周囲の砂泥粒子が剥脱されて,化石が浮き上がって見える.
bは標本の一部を接写したもので,殻の立体的な構造がよくわかる.
cは母岩から離脱した化石,
dはその1個体を接写したもの.
図-003:ヤベイナ[
Yabeina globosa],ペルム紀,和歌山県産.
aは標本全体を撮影したもの.ヤベイナの殻の断面が渦巻き状に見える.
bは標本の一部を接写したもの.殻の断面が示されているが,直径が1cm近くあって大きく,構造も複雑であることが分かる.
cでは母岩が風化されて,球状のヤベイナが浮き上がって見える.
図-004:モノディエクソディナ[
Monodiexodina matsubaishi],ペルム紀,宮城県産.北上山地特産で,非常に細長い形をしていることから「松葉石」と呼ばれる.
aは標本全体を撮影したもので,細長く開いている穴は松葉石の化石があった跡.
bはその一部を接写したもので,溶けずに残った化石が見える.
c・dは新鮮な標本なので,松葉石の殻の断面がはっきりと見える.
cは標本全体を撮影したもの,
dは1個体を接写したもの.
(2) カヘイセキ(貨幣石)
古第三紀の示準化石として重要な大型有孔虫で,その大きさと形が硬貨を思わせることから「カヘイセキ」と呼ばれる.エジプトのピラミッドに使われている石に含まれることでも有名.
図-005:ヌムリテス[
Nummulites oosteri],古第三紀,イタリア産.
図-006:ヌムリテス[
Nummulites boniensis],古第三紀,東京都産.
図-007:ヌムリテス[
Nummulites sp.],古第三紀,カンボジア産.殻の渦巻き状構造がよくわかる.
(3) レピドシクリナ
新第三紀の示準化石として重要な示準化石の1つ.円形ないし放射状の輪郭をもち,レンズ状.
図-008:レピドシクリナ[
Lepidocyclina sp.],新第三紀,和歌山県産.
aは串本港の近くで海岸近くの海中にある岩石から割り採った標本で,
bはその一部を接写したもの.
cは波によって海中の岩石から遊離して波打ち際に打ち上げられていた化石.
(4) ホシズナ(星砂)
現在生息している有孔虫の1種.低緯度の日本近海でも生息し,沖縄では西表島などの海岸には殻が多数打ち上げられている.放射状の棘を持つ殻の形が美しいので,土産物として売られている.
図-009:ホシズナ[
Baclogypsina spheaerulata],現生,沖縄県産.
aはホシズナ,他の有孔虫,ウニの棘などが集まってできた“砂”の様子を撮影したもの.
bはホシズナの1個体を撮影したもので,殻にたくさんの孔が開いていることが分かる.
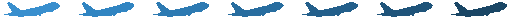
どこへ移動しますか?
ご希望のところをクリックしてください。
![]()