丂侾丏偼偠傔偵
丂戝榓愳偼丆偦偺尮棳傪撧椙導妢抲嶳抧偵敪偟丆弶悾愳偲側傝彫晇丒弶悾僟儉傪宱偰撧椙杶抧偵偍偄偰嵅曐愳丒帥愳丒旘捁愳丒晉梇愳側偳戝彫條乆側巟愳傪崌傢偣側偑傜惣棳偟偰偄傞丏偝傜偵丆抧偡傋傝抧偱桳柤側乽婽偺悾乿宬扟傪宱偰戝嶃暯栰偵擖傝丆愇愳丒搶彍愳丒惣彍愳傪崌傢偣偰惣棳偟丆戝嶃榩偵拲偄偱偄傞丏偦偺姴愳棳楬墑挿栺68km偵偍傛傃丆憤棳堟柺愊偼栺1071km2偺堦媺壨愳偱偁傞丏傑偨丆戝榓愳偼丆慡崙偺堦媺壨愳偺拞偱19擭楢懕墭戺搙儚乕僗僩俀偵懕偒丆俀擭楢懕儚乕僗僩侾偵側傝慡崙揑偵傕墭傟偨壨愳偺僀儊乕僕偑掕拝偟偰偄傞1),2)丏戝嶃傪棳傟傞戝偒側壨愳偺侾偮偱偁傞恎嬤側戝榓愳傪椺偵嫇偘丆側偤枬惈揑偵墭戺偑恑傫偱偄傞偺偐傪挷嵏偺僗僞乕僩偲偟丆忋棳堟偵徟揰傪峣傝娐嫬挷嵏傪峴偭偨丏偦偟偰丆戝榓愳悈宯慡懱偺條巕丆壨愳偺廲抐柺偺嶌惉丆壔妛揑庤朄偵傛傞悈幙偺暘愅丆尮棳堟偺抧棟揑忦審偺挷嵏摍偐傜壨愳娐嫬傪憤崌壢妛揑偵峫偊傞嫵嵽壔傪帋傒偨丏
丂俀丏戝榓愳悈宯偲壨愳偺廲抐柺恾
丂恾侾偼丆戝榓愳悈宯偺慡懱恾傪昤偄偨傕偺偱偁傞丏撧椙杶抧偵崀偭偨塉傪廤傔丆惣棳偟丆戝榓愳偺撧椙懁偱偺桞堦偱偺弌岥偱偁傞乽婽偺悾乿宬扟傪捠傝丆戝嶃暯栰偱愇愳側偳偺巟棳偲崌棳偟戝嶃榩傊棳傟崬傫偱偄傞丏恾俀偼丆恾侾偺弶悾愳棳堟晹暘傪奼戝偟偨傕偺偱丆挷嵏抧揰傪A1乣A8偱帵偟偨丏
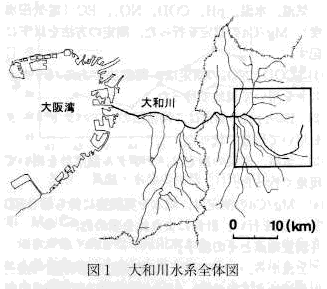
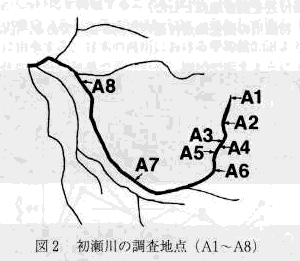
丂崙搚抧棟堾俀枩5000暘偺侾偺抧宍恾偐傜壨愳偺廲抐柺恾傪嶌惉偟偨偺偑恾俁偱偁傞丏壨愳偺孹幬偐傜丆暯栰晹丆抧宍偺媫弒偝丆宬扟晹丆杶抧丆僟儉傗屛側偳偑撉傒庢傟傞丏偮傑傝丆恖娫偺搚抧棙梡偺條巕側偳偑撉傒庢傟傞丏戝榓愳偼丆戝嶃暯栰丒撧椙杶抧傪側偩傜偐偵棳傟丆戝嶃榩偐傜栺50噏偺戝榓挬憅晅嬤偐傜孹幬偑戝偒偔側傝丆挿扟帥偱偼丆偐側傝媫弒側抧宍乽弶悾宬扟乿側偳傪棳傟傞丏搑拞偺悈暯柺偼丆弶悾僟儉偵傛偭偰偣偒巭傔傜傟偨乽傑傎傠偽屛乿偱偁傞丏偝傜偵忋棳偵岦偐偆偲孹幬偑彮偟備傞傗偐偵側傞強偑乽彫晇懞乿偱丆偙偺晅嬤偵恖壠偑廤拞偟偰偄傞丏廲抐柺恾偱孹幬偺媫弒側強偱偼帺慠壨愳偑尒傜傟丆壨愳偺忩壔嶌梡偑峴傢傟偰偄傞丏嵟忋棳晅嬤偺傎傏悈暯側晹暘偑搒孷懞偱偁傞丏暯抧偱偁傞偙偲偐傜偙偺晅嬤偼奐敪偑恑傒丆恖壠偑懡偔尒傜傟傞丏
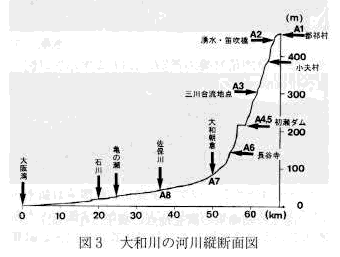
丂俁丏悈幙挷嵏3),4)
丂婥壏丆悈壏丆pH丆COD丆NO2亅丆EC乮揹婥揱摫搙乯丆Mg/Ca偺應掕傪峴偭偨丏應掕偺曽朄傪埲壓偵婰偡丏
(1) COD偲NO2亅偺應掕偼丆娙曋朄偱偁傞僷僢僋僥僗僩傪梡偄偰尰抧偱峴偭偨丏
(2) EC偲pH偺應掕偼丆実懷宆偺僐儞僷僋僩儊乕僞傪梡偄偰尰抧偱峴偭偨丏
(3) 婥壏丆悈壏偺應掕偼丆僨僕僞儖壏搙寁傪梡偄偰尰抧偱峴偭偨丏
(4) Mg/Ca偺應掕偼丆帋悈傪幚尡幒偵帩偪婣傝EDTA揌掕傪峴偄丆寁嶼偵傛傝斾傪媮傔偨丏
乵挷嵏抧揰偲偦偺條巕乶
丂忋棳偐傜丆A1搒孷懞丆A2揓悂墱媨揓悂嫶丆A3嶰愳崌棳抧揰壓庤偺嫶丆A4傑傎傠偽屛擖岥丆A5弶悾僟儉屛悈丆A6挿扟帥楢壧嫶丆A7戝榓挬憅丆A8悙曚嫶晅嬤傪挷嵏抧揰偲偟偨丏
丂弶悾愳偺挷嵏抧揰晅嬤偺幨恀偑恾係偱偁傞丏
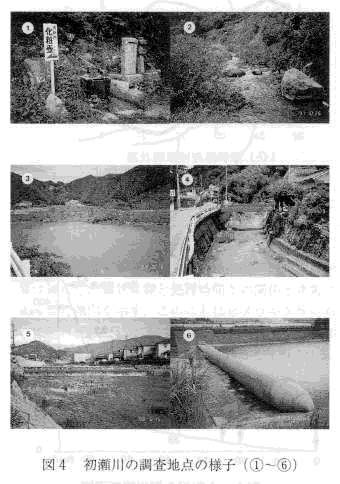
嘆偼丆A2揓悂墱媨揓悂嫶偦偽偵偁傞乽桸悈乿偱偁傞丏嘇偼丆A4晅嬤偱傑傎傠偽屛偵棳擖偡傞弶悾愳偺條巕偱帺慠偺忬懺偑巆偝傟偰偄傞丏嘊偼丆弶悾僟儉偱偁傝丆偙偺屛偑乽傑傎傠偽屛乿偲屇偽傟偰偄傞丏嘋偼丆A6挿扟帥墶偺楢壧嫶偱偁傞丏嘍偼丆A7戝榓挬憅晅嬤偺條巕偱偁傞丏嘐偼丆A8悙曚嫶晅嬤偺僑儉堜墎偱揷敤偺娏燆梡悈偲偟偰巊梡偝傟丆撧椙杶抧撪偺戝榓愳偱偼懡偔尒傜傟傞丏
丂係丏寢壥偍傛傃峫嶡
丂挷嵏擔偼丆埲壓偵帵偟偰偄傞偑丆戙昞揑側抣傪挷嵏擔偛偲偵乮仛丆仠丆仯丆仭丆仧乯偺婰崋偱昞偟丆恾俆乣俉偍傛傃恾10偵僌儔僼壔偟偨丏
(a)H9.8.13乮仛乯丆(b)H9.10.26乮仠乯丆(c)H9.11.10丆(d)H10.6.15乮仯乯丆(e)H10.7.1丆(f)H10.10.12乮仭乯丆(g)H10.12.23乮仧乯偺寁俈夞偺挷嵏傪峴偭偨丏側偍丆(c)H9.11.10偵偼丆弶悾愳廃曈偺懞偺悈棙梡偺暦偒庢傝挷嵏偲廃曈偺揤慠悈偺悈幙挷嵏傪峴偭偨丏傑偨丆(e)H10.7.1偵偼丆弶悾愳偵棳傟崬傓巟愳偲廃曈偺揤慠悈偵偮偄偰偺悈幙挷嵏傪峴偭偨丏
丂埲壓偵丆屄乆偺挷嵏崁栚偵偮偄偰娙扨側愢柧偲寢壥偺摿挜傪帵偡丏
(1) COD乮壔妛揑巁慺梫媮検乯
丂COD偼丆悈拞偺桳婡暔傪偼偠傔偲偡傞娨尦惈暔幙傪KMnO4偱巁壔偟丆偦偺偲偒偵徚旓偝傟偨KMnO4偺検傪巁慺検(ppm)偵姺嶼偟偰媮傔偨傕偺偱偁傞丏尮棳晅嬤偱偁傞A1偐傜丆偡偱偵墭悈偺棳擖偑擣傔傜傟偨乮恾俆亅仠仭乯丏壓棳偵峴偔偵廬偭偰抣偑忋徃偟偰偍傝丆恖堊揑側塭嬁偵傛傞傕偺偲峫偊傜傟傞丏A2偵偍偗傞挷嵏擔偵傛傞戝偒側堘偄偼丆應掕帪娫懷偺堘偄偲峫偊傜傟傞乮恾俆亅仭偼拫帪偺應掕乯丏A2偐傜A4偺拞棳堟抧揰偱偼丆抣偺夵慞偑傒傜傟偨乮恾俆亅仠仯仭乯丏偙偺尨場偼丆壨愳偺忩壔嶌梡偲嶳偐傜偺偵偠傒弌偟偺悈偵傛傞擇偮偺岠壥偲峫偊傜傟傞丏
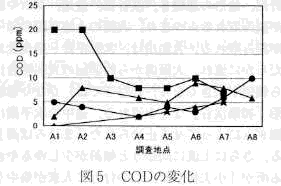
(2) NO俀亅乮垷徤巁僀僆儞乯
丂NO俀亅偼丆僞儞僷僋幙摍拏慺娷桳暔幙偑巁壔偝傟偨暔幙偱丆COD偺抣偑戝偒偄強傎偳NO俀亅偺抣偼戝偒偔側傞偲偄偆憡娭偑偁傞丏摿挜揑側椺傪乮恾俇亅仯仭仧乯偵偁偘傞丏COD偺曄壔偲摨偠偔丆尮棳晅嬤偱偁傞A1偺抣偑戝偒偄偙偲傗丆壓棳偵峴偔偵廬偭偰抣偑忋徃偟偰偄傞偺偼丆嫟偵恖堊揑側塭嬁偵傛傞傕偺偲峫偊傜傟傞丏
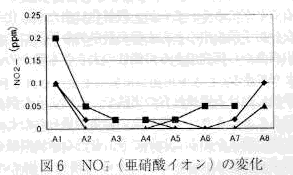
(3) EC乮揹婥揱摫搙乯丂
丂 EC偺抣偼丆悈拞偵梟偗偰偄傞柍婡僀僆儞偺憤検傪昞偡巜昗偱偁傞丏柍婡僀僆儞検偑懡偄悈偼揹婥傪傛偔捠偡偺偱丆扺悈偺応崌丆墭傟偨悈偲偄偊傞丏恾俈偱帵偡傛偆偵A1偍傛傃丆壓棳堟A6偐傜A8抧揰偱忋徃偟偰偄傞偺傕恖堊揑塭嬁偵傛傞傕偺偲峫偊傜傟傞丏
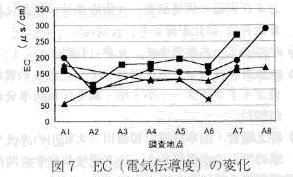
(4) pH
丂pH抣偼丆抧幙丒搚忞拞偺CO2偺梟夝丒怉暔偺岝崌惉嶌梡傗僶僋僥儕傾偵傛傞惗暔暘夝丒恖堊揑塭嬁側偳條乆側梫場偑娭學偡傞丏恾俉偱帵偝傟傞傛偆偵丆壓棳傊峴偔偵偮傟忋徃偟偰偄傞偺偼丆恖堊揑傑偨偼抧幙偺塭嬁偑峫偊傜傟傞丏
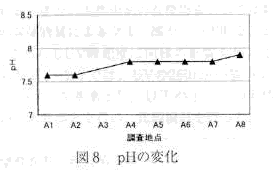
(5) 婥壏丆悈壏
丂壨愳悈偼丆偄偢傟偺帪婜偱傕忋棳偐傜壓棳偵峴偔偵偮傟丆悈壏偺忋徃偑擣傔傜傞丏恾俋偱帵偡傛偆偵丆偄偢傟偺應掕擔偱傕A5抧揰偱偼丆婥壏偲偺嵎偑彮側偐偭偨丏僟儉屛悈偱偁傞偺偱愳偺棳懍偑掅壓偟丆懢梲曻幩偵傛傞擬傪媧廂偡傞帪娫偑挿偄偨傔偲峫偊傜傟傞丏丂丂
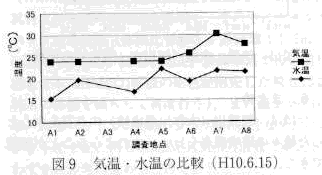
(6) Mg/Ca丂
丂塉悈偑抧壓悈傑偨偼壨愳悈偲側偭偰丆搚忞拞傪棳傟傞応崌庬乆偺僀僆儞傪梟偐偡丏傑偨丆壨愳悈偺梲僀僆儞擹搙偼堦斒揑偵丆Ca2+亜
Na+ 亜Mg2+偺弴偵側傞乮奀悈偼 Na+亜Mg2+亜Ca2+ 偺弴乯丏偦偙偱丆Mg/Ca偺斾傪應掕偡傞偙偲偵傛傝丆壨愳廃曈偺抧幙偑悇掕偱偒傞丏Ca2+傗Mg2+偼丆庡偲偟偰娾愇搚忞偵桼棃偡傞丏擔杮偺壨愳偵偍偗傞暯嬒抣0.58傛傝慡懱揑偵掅偄寢壥偱偁偭偨偑丆恾10偱帵偡傛偆偵忋棳堟偼抧幙揑偵壴浖娾偺傑偝搚偱偁傞偺偱傎傏梊應偝傟偨寢壥偱偁偭偨乮愇奃娾幙偱偁傟偽丆抣偼傛傝彫偝偔側傞乯丏
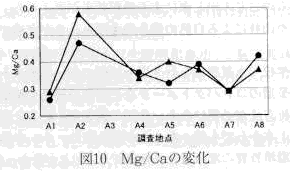
(7) 桸悈
恾11偱帵偡傛偆偵丆A2揓悂墱媨揓悂嫶晅嬤偵偁傞乽桸悈乿偺悈壏偲婥壏丆揓悂嫶偐傜偺弶悾愳偺悈壏傪應掕偟斾妑偟偨丏搤応偼婥壏偲偺嵎偑彮側偔丆壞応偼婥壏偲偺嵎偑戝偒偔側傞丏乽桸悈乿偼丆乽壞偼椻偨偔姶偠丆搤偼抔偐偔姶偠傞丏乿偲偄傢傟傞偺偼丆偙偺偨傔偱偁傞丏傑偨丆壨愳悈偺悈壏偵斾傋丆桸悈偺悈壏偼擭娫捠偟偰埨掕偟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丏桸悈偺悈壏傪嶳偐傜偺偵偠傒弌偟悈偺悈壏偲偡傞偲丆壞応偼壨愳悈偺曽偑婥壏偵傛傝壏傔傜傟傞偺偱桸悈傛傝崅偔側傞偑丆搤応偼媡偵婥壏偵傛傝椻傗偝傟傞偺偱壨愳悈偺曽偑掅偔側傞丏
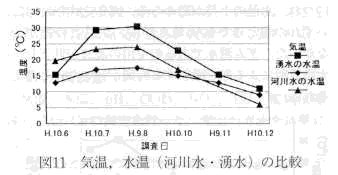
丂俆丏傑偲傔
丂崱夞偼丆弶悾愳乮戝榓愳尮棳堟乯偺悈幙傪拞怱偲偟偨庬乆偺娐嫬挷嵏傪峴偄丆師偺傛偆側偙偲偑妋擣偱偒偨丏
丂尰抧偱弶悾愳傪挷嵏偡傞偙偲偵傛傝丆戝嶃巗撪傪棳傟傞戝榓愳偺條巕偲偼堎側偭偨壨愳偺巔傪傒傞偙偲偑偱偒偨丏乽偦傟偼丆撧椙杶抧傪棳傟傞戝榓愳偱偼懡偔偺僑儉堜偤偒偑偁傝丆恖乆偑捈愙壨愳悈傪偐傫偑偄梡偵棙梡偟偰偄傞丏搑拞偵僟儉屛偑偁傝嶗堜巗偺堸椏悈尮偺堦晹偵側偭偰偄偨傝丆尮棳堟偱偼奐敪偑恑傒丆摴楬偑惍旛偝傟懡偔偺恖壠偑偁傞偙偲側偳偱偁傞丏乿偙傟傜偼丆尰抧傪娤嶡偡傞偙偲偵傛偭偰丆偼偠傔偰婥偯偔偙偲偱偁傝丆僼傿乕儖僪儚乕僋偺廳梫偝偑擣幆偱偒傞丏
丂偝傜偵丆悈幙挷嵏傪宲懕揑偵峴偆偙偲偵傛傝丆忋棳偱墭戺暔幙偺棳擖偑偁傞応崌偱傕丆搑拞偱COD抣摍偑夞暅偟偰偄傞帠幚偐傜丆壨愳偺忩壔嶌梡傗嶳偐傜偺偵偠傒弌偟悈偵傛傞婓庍岠壥偑峫偊傜傟丆壨愳傗嶳椦偵傛傞帺慠偺摥偒偺偡偽傜偟偝偑幚姶偱偒傞丏
丂妛峑偱悈幙挷嵏傪峴偆応崌偵偼丆僷僢僋僥僗僩傗実懷宆偺僐儞僷僋僩儊乕僞側偳娙曋側婍嬶傗娙扨側暘愅曽朄偑昁梫偵側傞丏崱夞偺挷嵏偱丆偨偲偊壏搙寁侾杮偐傜偱傕條乆側偙偲偑撉傒庢傟丆彫
丒拞妛峑偺娐嫬嫵堢偺幚慔偵廫暘妶梡偱偒傞偙偲偑暘偐偭偨丏
丂偙偺傛偆偵丆偁傞嫹偄抧堟偺娐嫬挷嵏乮椺偊偽丆戝嶃巗撪傪棳傟傞戝榓愳偺悈幙挷嵏側偳乯偩偗偱偼傒偊側偄偙偲傕丆戝榓愳慡懱偺悈幙挷嵏傪峴偆偙偲偵傛傝丆峀偄娤揰傪堢偰傞娐嫬嫵堢偺幚慔偑壜擻偱偁傞丏
埲忋偺偙偲傪憤崌揑偵敾抐偟丆條乆側懁柺偐傜丆壨愳娐嫬傪峫偊傞偙偲偵傛傝丆恖堊揑側帺慠傊偺塭嬁傗丆壨愳傗嶳椦偺帩偮杮棃偺帺慠忩壔偺摥偒傪峫偊傞偙偲偑偱偒傞丏偝傜偵丆嫵嵽壔偵摉偨傝丆壔妛揑側暘愅庤抜傪拞怱偲偟偨憤崌壢妛揑側庤朄偵傛傞壨愳挷嵏偐傜扵媶偱偒傞壜擻惈偺戝偒偝傕妋偐傔傞偙偲偑偱偒偨丏
丂妛峑偵偍偗傞娐嫬嫵堢偺幚慔偱丆偙偺傛偆側挷嵏傪峴偆偙偲偵傛傝丆梊憐偟側偄寢壥偑摼傜傟偨偲偒偺惗搆偺嬃偒傪抦傞偙偲偑偱偒丆恎嬤側娐嫬栤戣傪尒捈偡偒偭偐偗偲側偭偨丏偦偺徻嵶偼丆暿偺妛夛5)丆6)偱曬崘偟偰偄傞偺偱丆偦傟傪嶲峫偵偟偰傕傜偄偨偄丏
丂嶲峫暥專
侾乯撧椙導惗妶娐嫬晹娐嫬曐慡壽丂搚栘晹壨愳壽丒壓悈摴壽丗戝榓愳俽俷俽亅惔棳暅妶偵岦偗偰亅(1997)丏
俀乯嶳杮彑攷丗弶悾愳乮戝榓愳偺尮棳乯偺悈幙挷嵏偍傛傃廃曈偺娐嫬挷嵏丆戝嶃晎崅摍妛峑棟壔嫵堢尋媶夛
棟壔婭梫35崋丆p22-25丏
俁乯敿扟崅媣丗悈幙挷嵏朄丆娵慞(1971)丏
係乯戝嶃晎嫵堢僙儞僞乕丗偩傟偵偱傕偱偒傞悈幙挷嵏僈僀僪僽僢僋乕彫丒拞丒崅摍妛峑巜摫帒椏(1997)丏
俆乯堜忋惏婱丒嶳杮彑攷丗弶悾愳乮戝榓愳偺尮棳傪媮傔偰乯偺悈幙挷嵏俁丆擔杮娐嫬嫵堢妛夛
娭惣巟晹 戞俈夞尋媶敪昞戝夛帒椏廤(1998)丏
俇乯戝嶃巗棫栴揷撿拞妛峑壢妛晹丗戝榓愳偺悈幙挷嵏丆擔杮壔妛夛嬤婨巟晹 戞15夞崅摍妛峑丒拞妛峑壔妛尋媶敪昞夛帒椏廤p4-5(1998)丏