1.はじめに
児童生徒にとって最も身近な環境問題の一つとして,河川,湖などの水環境の悪化がある.河川の水質汚濁は,現在では生活排水が汚濁原因の80%を占めている.これは,台所や洗濯排水などが十分に処理されないままに河川に流出することにより,引き起こされるものである.そして下流に行くほど河川水の汚濁はひどくなっていく1).このような河川水の汚濁を調べるのに,有機成分による汚れとして化学的酸素要求量(COD)や生物的酸素要求量(BOD)を測定することが多い.種々の簡便法を用いて水質調査が行われているが,これらは精度や費用等に難点がある2)
.
また,紫外線を汚濁した水に通過させたとき,水中の有機物量に応じて光エネルギーが減衰する.そのため,CODと紫外線の吸光度(absorbance)の相関性が高く,人為的な有機物汚染の高い水質については有効な測定方法とされている3).そこでいくつかの河川でのKMnO4(過マンガン酸カリウム)法によるCODとの比較による検討を行い,さらに,代表的な無機イオンや有機化合物および合成洗剤や石けんの紫外(UV)スペクトルに対する影響も調べた.
2.方法
(1)天然水のCODとUV値との関係
生活排水におけるCODの増加の最も大きな原因は,石けんや合成洗剤の流入のためであると考えられる.合成洗剤として最も多量に使用されている直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(LAS)は芳香族化合物であり4),UVの芳香族特有の230〜270nmに吸収帯が表れる.したがって,その濃度に比例して,CODもUVの吸光度も変化するものと考えられる.また,天然由来の有機物質としては動植物等の腐植物質によるフミン酸やフルボ酸などがあり5),これらもUV吸光度に同様の影響を与えると考えられる.ここでは,UVの260nmの値(以下UV260と表す)を基準とし,以下の①〜⑥の天然水について水質測定を行い,比較検討を行った.
〔KMnO4法によるCOD測定〕:COD値の測定は,
試料水の上澄み液50mlを採取し,その中にホール
ピペットで希硫酸(体積比で水3:濃硫酸1)5ml ,0.002M-KMnO4 10ml を加え,沸騰水浴で15分間反応させる(KMnO4溶液の赤色が消失した場合は試料水の体積を減らして再度行う).まだ温かい内にホールピペットで0.005M-シュウ酸10mlを加え,ビュレットで上記と同じ0.002M-KMnO4溶液で滴定し,わずかに赤色に変わった所を終点とした6).
〔UV260測定〕:UV260は,ダブルビーム分光光度計(S社240)を用いて(10mm石英セルを使用し)試料水の吸光度を求めた.次の①〜⑥の 河川水等について,それぞれのCODとUV260の相関を調べるために,相関係数と回帰直線を求めて,測定データの検討を行った.
① 和田川(大阪府堺市)の河川水:1回目はH9.6.27に,2回目はH9.8.6に共に5か所から採水した.
② 石川水系の河川水(大阪府河内長野市):滝谷,汐ノ宮,太子町の3か所からH9.7.31に採水した.
③ 初瀬川水系の河川水(奈良県桜井市):上流域の支流を含む8か所からH9.7.1に採水した.
④ 飛鳥川水系の河川水(奈良県明日香村):最上流域の支流を含む7か所から,1回目はH9.7.17に,2回目はH9.8.27に採水した.
⑤ 槇尾川の河川水(大阪府和泉市):最上流域から下流域までの支流を含む10か所からH9.7.7に採水した.
⑥ 屋外水槽内の水(大阪市住吉区):河川水以外のものとして,当センターの敷地内にある屋外水槽内の水を4か所からH9.8.7に採水した.
(2)無機イオンのUVスペクトル
河川水のUV260に対する無機イオンの影響を調べるために,次の8種類の塩の無機イオンのUVスペクトルの測定を行った.
①NH4+(塩化アンモニウム)
②SO42-(無水硫酸ナトリウム)
③SO32-(無水亜硫酸ナトリウム)
④NO3-(硝酸ナトリウム)
⑤NO2-(亜硝酸ナトリウム)
⑥CO32-(無水炭酸ナトリウム)
⑦HCO3-(無水炭酸水素ナトリウム)
⑧PO43-(リン酸三ナトリウム,12水塩).いずれも0.1gを水に溶かして100mlとした水溶液を用いた.
(3)有機化合物のUVスペクトル
UV260付近の吸光度に対する影響を調べるために,次の代表的な7種類の有機化合物のUVスペクトルの測定を行った.
①シュウ酸,②酒石酸,③ベンジルアルコール,
④酢酸,⑤エタノール,⑥フェノール(水酸化ナトリウム溶液),⑦アニリン(塩酸溶液).各溶液の濃度は,①
②が0.1g/水100ml,③ ④ ⑤が1ml/水100ml,⑥ ⑦ が0.2g/溶液20mlである。
(4)フミン酸,合成洗剤,石けんのUVスペクトル
天然水と比較するために,以下のフミン酸,合成洗剤,石けん水溶液のUVスペクトルを調べた.フミン酸は,①腐葉土50gを水200mlに3日間浸けてろ過したもの,②フミン酸(試薬化学用−W社製)0.001gを水に溶かして100mlにしたもの(わずかに水酸化ナトリウムを加えてアルカリ溶液とした)を用いた.
合成洗剤は,粉末の洗濯用合成洗剤0.1gを水に溶かして100mlとした.その成分は,界面活性剤(24%)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムと高級アルコール系(陰イオン)の硫酸塩,アルミノケイ酸塩および炭酸塩,蛍光剤配合で弱アルカリ性のものを使用した.また,石けんは粉末石けん0.1gを水に溶かして100mlとした.その成分は,脂肪酸ナトリウム(純石けん分)75%の炭酸塩で弱アルカリ性のものを使用した.
3.結果
(1)天然水のCODとUV260との関係
採水した①〜⑥の天然水の特徴を以下に示す.また,そのUVスペクトルを図1に示す.この場合,UVスペクトルはそれぞれ天然水の代表的なものを選んだ.⑥の水槽内の水のスペクトルの形状は,他と少し異なっているが,①〜⑤の河川水についてはほとんど同じスペクトルであった.
① 和田川の河川水:すべてが河川水であり,同じ場所で二回採水した.回帰式はいくらか異なったが,採水日の違いによる影響はそれほどみられなかった.
② 石川水系の河川水:すべてが河川水であり,測定ポイントが3カ所と少なかった.
③ 初瀬川水系の河川水:すべてが河川水ではなく,一部湧水も含み,支流からの水も多い.結果は,多少バラツキもあった.
④ 飛鳥川水系の河川水:すべてが河川水ではなく,一部湧水も含み,最上流域の支流からの水も多い.結果は,多少バラツキもあった.同じ場所で二回採水しているが,採水日の違いによる影響はほとんど表れていない.
⑤ 槇尾川の河川水:すべてが河川水ではなく,一部湧水も含み,支流からの水も多い.結果は,多少バラツキもあった.
⑥ 屋外水槽内の水:屋外水槽の水の供給は雨水であり,それぞれ個別に水草が成育されている.また,合成洗剤の流入はなく,CODの原因はフミン酸等の影響が考えられる.
次に,①〜⑥の天然水の回帰式および相関係数を表1に示す(yは縦軸,xは横軸,rは相関係数を表す).また,①〜⑥のCODとUV260との回帰直線を図2に示す.いずれの場合も相関係数(r)は1に近い値を示し,CODとUV260の間には非常によい相関がみられた.ただし,同じ河川で異なる採水日では,わずかに回帰式がずれたが,概算値のCOD値を求めるためには,十分にUVの分光学的手段によってCODの推定が可能であることが分かった.
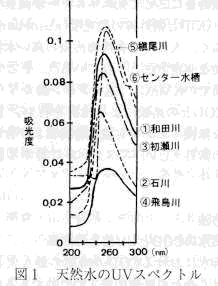
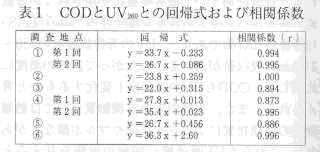
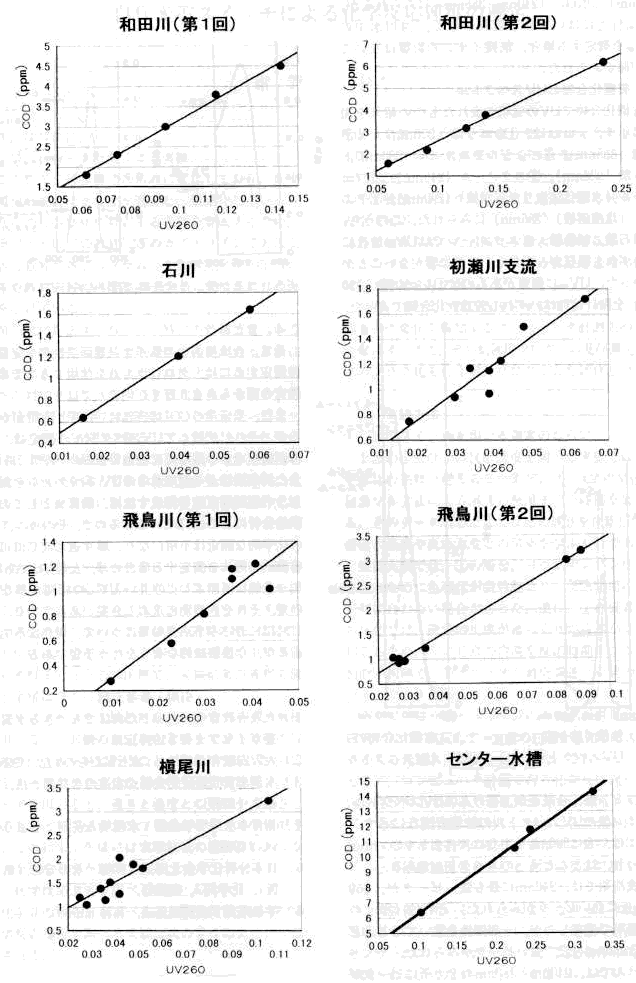
(2)無機イオンのUVスペクトル
①NH4+ ②SO42- ⑥CO32- ⑦HCO3- ⑧PO43-では,全く吸収がみられなかった.無機イオンでUVの吸収の表れたものの結果を図3に示す.λmaxは,③SO32-(240nm)④NO3-(240nm,300nm)⑤NO2-(240nm,355nm)にみられるが,UV260付近にはいずれも吸収がなく,河川水中のUV260を測定する場合,無機イオンの影響はないことが確かめられた.
(3)有機化合物のUVスペクトル
有機化合物でUVの吸収の表れたものの結果を図4に示す.λmaxは,①シュウ酸(250nm),②酒石酸(235nm),③ベンジルアルコール(280nm),④酢酸(238nm),⑤エタノール(240nm),⑥フェノール(水酸化ナトリウム溶液)(290nm),⑦アニリン(塩酸溶液)(285nm)にみられた.このうち,②酒石酸,④酢酸,⑤エタノールではUV260付近にはいずれも吸収がみられないので影響がないことが分かった.UV260に影響があるのは①シュウ酸(250nm)を除けば他はいずれも芳香族化合物であった.

(4)フミン酸,合成洗剤,石けんのUVスペクトル
フミン酸のUVスペクトルの結果を図5に示す.①,②は,共に260nmを中心にスペクトルのλmaxがみられ,ほとんど同一のスペクトルである.合成洗剤では,240nmに最も強いピークが,260nm付近に弱いピークがみられた.その他,多くの合成洗剤で測定したが,一部例外を除いてほとんどの場合260nm付近で強いピークがみられた.
石けんでは,240nmと280nmの2カ所にピークがみられた.
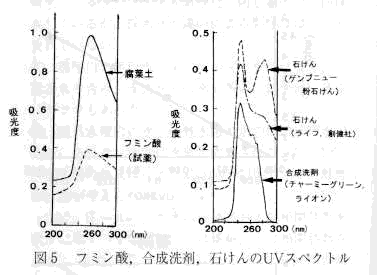
4.まとめ
通常,合成洗剤中の陰イオン界面活性剤を定量的に測定するには,クロロホルムを使用するので環境教育の面からあまり好ましいことではない.
また,公定法のCOD測定は,手間と時間がかかるが,それに比較してUVスペクトルの測定は,操作が簡単でかつ短時間に実施できるのが特徴である.また,本法により河川水中のUVスペクトルを測定し,一度回帰直線を作成すれば,概算値としての化学的分析によるCODと一致するので,その後のCODの化学的な測定は不用になり,繰り返し同じ河川の有機的な汚れを測定する場合には,大変有効である.
一般的に河川ごとにCOD−UV260の相関が異なるので,それぞれ個別に求める必要がある.また,同じ河川における季節変動等について,現在は不明であるが,今後継続的な調査を行う予定である.
引用・参考文献
1)大阪府教育センター:だれにでもできる水質調査ガイドブック(1997).
2)大阪府教育センター:水と私たちの生活(1995).
3)水道水質問題研究会編:水道の水質調査法,技報堂(1997).
4)(社)日本水環境学会編:水環境と洗剤,ぎょうせい,(1994).
5)日本分析化学会北海道支部編:水の分析(第4版),化学同人(1994).
6)半谷高久:水質調査法,丸善(1960).