

研修風景
中学校「理科」フレッシュ研修
◎8月25日(月)
●第1回 地学「太陽活動と天体望遠鏡の使い方」
●第2回 生物「昆虫教材に慣れる」
|
「昆虫教材に慣れる」と題して、背骨の無い動物の代表である昆虫教材に慣れることを目標にした研修を受けました。 秋に教材として使えるコオロギを用い、そのライフサイクルに関する講義を受けた後、形態の観察、行動の観察などを行いました。この研修を受けて昆虫一般に対する理解が深まり、また、興味がわきました。 右の写真は、コウロギの孵化直前の卵です。既に、眼ができているところが観察されました。 |
|
◎8月27日(水)
●第3回 物理「中学校2年における物理領域の基礎実験」
| 今年度は中学校2年生の物理領域、「電流と磁界」「電流の働き」の単元において、生徒の興味関心、理解を高める実験とものづくりを中心に行いました。 今回はデジタル教材「理科ねっとわーく」を利用しました。 その中にある「三次元でわかる物理電磁気学編」を用いて、磁石の周りの磁界の様子を三次元で観察することで、より磁界の仕組みを理解しやすくする授業方法を工夫し、「実験道場、ニュートンに挑戦!!」の「簡単モーターづくり」を利用してモーターづくりを行いました(右図)。 ※「理科ねっとわーく」を利用するには登録が必要です。 |
 |
●第4回 化学「化学変化と原子・分子」
| 酸素を充満させた集気びんを水槽に逆さに立て、その中でスチールウールを燃焼させました。水面が上昇することから、「燃焼における酸素の消費」を見いだしました。また、スチールウールの取り付け方などを各班で考え、よい実験結果が得られる方法を工夫しました(写真)。 そのほか、「質量保存の法則と元素」、「化学反応の量的関係(水素の燃焼)」についての実験を行いました。 |
 |
●第5・6回 「電子顕微鏡でタンパク質を見る」
| 京都大学大学院理学研究科生物物理学教室教授 藤吉好則先生の講義「人を分子レベルから理解するための構造生理学」と、研究室にある電子顕微鏡を使っての細胞の観察および研究室の施設見学を行いました。 最先端の科学に触れることができ、理科教育の大切さを改めて感じさせられました。 ※藤吉研究室のホームページへ |
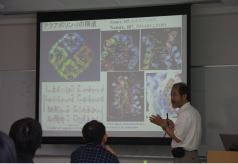 |
 |
このページの先頭へ
研修等の紹介へ
