|
|
|
|
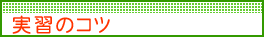 |
|
|
| ■ |
層に沿って小型の平タガネ(マイナスドライバーでもよい)をあてて金槌で軽く叩き、化石を含む層を露出させる。 |
| ■ |
化石の一部が隠されているときは、化石から少し離れた所にタガネ(釘など先の尖ったもの)を、面に垂直にあてて金槌で叩き、上にある石を取り除く。このときは、力を入れずに、ごく軽く叩く。 |
| ■ |
あまり無理をせず、化石の一部は隠れていてもよいと意識すること。もし壊してしまった場合は、木工ボンドで貼りつける。 |
|
|
|
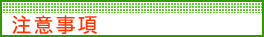 |
|
|
| ■ |
金槌やタガネなど危険な道具を扱うので、児童には悪ふざけをしないように十分注意を与える。 |
| ■ |
岩石破片が飛び散るので、目に入らないよう、顔を近づけすぎないように注意を促す。また、実験台の上にはあらかじめ新聞紙を厚く敷き、作業終了後には、岩石破片等を回収する。 |
| ■ |
産出化石は植物の葉が多いが、炭化した植物片(材の破片)、球果、昆虫などが見つかることもある。小さな物でも注意深くルーペで確かめること。また、植物化石は大部分が現生との共通種なので、出現状態がよければ図鑑などで名前を調べることができる。 |
|
 |
| 塩原湖成層の昆虫化石 |
|
| ■ |
参考資料として、化石観察のための簡単なデータベースを添付した。 |
|
|
|
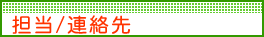 |
|
|
藤岡 達也・大橋 邦宏
大阪府教育センター 科学教育部 (電話)06-6692-1882 |
|
|
 |
|
|
このCDの画像・文章・デザイン等の著作権は大阪府教育委員会に属します。
|
|