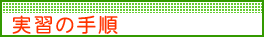 |
|
| <1>試料の採取 |
| 教室に川や海、地層の露頭から採取したれきや砂、粘土などを用意する。 これらの試料は遠足や林間学校の際に、子供たちに石ころや1つかみの砂を採取させるのが動機付けにはよい。それができなければ教師が用意する。大阪では、大阪層群といわれる未固結の、れき、砂、粘土の地層から採取できる。露頭の地層をスケッチしたり、写真に撮っておくとよい。
|
|
| <2>沈降実験 |
| 小さなれき、砂、粘土のまざった試料を適量ビーカにいれ、ガラス棒でかき混ぜそのまま放置し、粒子を沈降させる。粗いれきや砂は直ぐに底にたまるが細かい粘土はなかなか落ちてこない。上澄みは濁っている。しばらくすると上澄みの濁りは薄くなり、先に積もったれきや砂の上に細かい粘土の粒子がうっすらとたまる。粒の大きさによって沈降する速さが違い、れきから砂、粘土へと積み重なる様子を観察する。ビーカの代わりにペットボトル(500ml又は2L)を用い、その中に試料を入れ蓋をし、ボトルを振ったり逆さにしてれき、砂、粘土の重なり方を見るのも手軽なよい方法である(参照)。 |
|
|
 |
|
| <3>ふるいわけ |
| 粉体を扱う分野では"標準ふるい"というものが市販されており、目の開きが2、1、0.5、1/4、1/8、1/16mmのものを用意する。高価なので園芸用のふるいで代用してもよい。1mmより目の細かいものは入手しにくいので、料理用のざるやこし器などを利用し、正確でなくてよいから、段階的に細かくなるような大きさのふるいを揃える。2mmと1/16mm以下の2種類のふるいがあるとよい。後者は小麦粉のような、粒子のざらざら感が見えないような大きさの粒子がふるい分けられればよい。ふるいでふるって大きさごとに並べてみる。れき、砂、粘土は粒の大きさによって定義されており、れきは2mm以上、砂は2~1/16mm、粘土は1/16mm未満である。それぞれの大きさの粒子を順番に厚紙に木工用接着剤で貼り付け、れき・砂・粘土の粒度見本を作る。 |
|
|
 |
| かこう岩を粉砕しふるいわけたもの |
|
 |
| 地層の積み重なりの展示パネル |
|
|
|
|
|
|