3.サンゴ(珊瑚)類
一般には石灰質の骨格を有する腔腸動物で,死後は石灰質の殻が化石として残る.
造礁性サンゴ類の多くは,水温25〜29℃,塩分濃度36%前後,光線のよく通る清らかな海水,水深約90m以下といった限られた環境を好む.これは,軟体部に寄生する単細胞藻類ズーザンテラの光合成に必要な条件を満足させることにもよっている.したがって,造礁性サンゴ類の化石は示相化石としての価値が高い.また,古生代に栄えたショウバンサンゴ類やシホウサンゴ類には示準化石として重要なものが多い.
(1) ショウバンサンゴ(床板珊瑚)類
原始的なサンゴ類で,オルドビス紀〜ペルム紀に繁栄し,古生代末に絶滅した.
すべて海生で,種々の形の群体を形成する.各個体は管状で,多数の床板(水平横板)で仕切られ,隔壁(縦の仕切)はあまり発達してない.
我が国ではクサリサンゴ(鎖珊瑚),ハチノスサンゴ(蜂の巣珊瑚)が示準化石として重要.
図-010:クサリサンゴ[
Halysites sp.],シルル紀,愛媛県産.
aは標本全体を撮影したもの,
bはその一部を接写したもの.
図-011:クサリサンゴ[
Halysites sp.],シルル紀,スウェーデン産.
aは標本全体を撮影したもので,
bはその一部を接写したもの.
図-012:ハチノスサンゴ[
Favosites sp.],デボン紀,岐阜県産.
aは標本を上から撮影したもの.
bは横から撮影したもので,床板の様子が分かる.
図-013:ハチノスサンゴ[
Favosites sp.],シルル紀,岩手県産.
図-014:シノポラ[
Sinopora sp.],ペルム紀,カンボジア産.
aは標本全体を撮影したもので,
bはその一部を接写したもの.隔壁が無く筒状であることが分かる.
(2) シホウサンゴ(四放珊瑚)類
古生代後期に繁栄してペルム紀末に絶滅した古生代特有のサンゴ類で,示準化石・示相化石として価値の高いものが多い.
各個体内の隔壁が,最初の6枚の後は4を基本とした数で増えることから「四放(四射)サンゴ」と言われる.
我が国ではケイチョウフィルム,ワーゲノフィルムなどが示準化石として重要.
図-015・-016:ケイチョウフィルム[
Kueichophyllum yabei],石炭紀,岩手県産.「ケイチョウ」は中国の貴州の意味で,「貴州サンゴ」とも呼ばれる.石炭紀の示準化石とされる単体サンゴ.
図-017:ワーゲノフィルム[
Waagenophyllum sp.],ペルム紀,岐阜県産.ペルム紀の示準化石とされる樹状性または単体のサンゴ.
aは標本全体を撮影したもので,
bはその一部を接写したもの.
図-018:パラウェンツェレラ[
Parawentzelella sp.],ペルム紀,カンボジア産.
aは標本全体を撮影したもので,
bはその一部を接写したもの.
図-019:単体サンゴ[属種名不明],石炭紀,アメリカ産.
aは標本を横から撮影したもので,
bは上から撮影したもの.
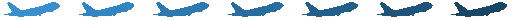
どこへ移動しますか?
ご希望のところをクリックしてください。
![]()