7.頭足類
古生代の初めから現在に至るまで栄えている軟体動物で,オウムガイやアンモナイトのように石灰質の殻を身体の外側に持つものと,イカやヤイシのように石灰質の殻が背骨のように体形保持の役割をしているものとがある.古生代のチョッカクセキ,中生代のアンモナイト・ヤイシなど示準化石として重要なものが多い.
(1) チョッカクセキ(直角石)類
オルドビス紀〜トリアス紀後期に生存し,古生代に栄えた.真直ぐかわずかに曲がった長円錐形の殻を持つ.全ての頭足類の祖先型で,現生のオウムガイ(鸚鵡貝)類は直系の子孫と考えられる.
図-046:チョッカクセキ[
Orthoceras sp.],デボン紀,モロッコ産.殻の縦断面が示されており,多数の殻室に分かれていることと,それらを貫く連室細管の様子がわかる.
図-047:チョッカクセキ[
Orthoceras sp.],デボン紀,モロッコ産.外側の殻は無くなっている.
aは横から撮影したもので,殻が隔壁で多数の殻室に分けられている様子が分かる.
bは
aの右側から見たもので,隔壁とその中央に開いた連室細管の様子が分かる.
図-048:オウムガイ[
Nautilus pompilius],現生,産地不明.
aは全体を撮影したもの.
bは殻の一部を切り取ったもので,殻が隔壁で多くの部屋に分かれていることと連室細管の様子が分かる.
(2) アンモナイト類
広義のアンモナイト類は古生代中期に出現し白亜紀末に絶滅した.特に中生代に栄え,重要な示準化石である.石灰質の殻を持っており,その表面装飾,巻き方,突起の有無,縫合線(殻を多くの部屋に仕切っている隔壁の端が殻の内側に接してつくる曲線)の形などで分類される.
図-049:アンモナイト[属種名不明]とチョッカクセキ[属種名不明],時代・産地不明.
aは標本全体を撮影したもので,
bはその一部を接写したもの.母岩は
図-046の標本と岩相が似ている.同じ地層のものだとすると,デボン紀のものなので,ごく初期のアンモナイトということになる.
図-050:ゴニアチテス[
Goniatites sp.]?,時代不明,モロッコ産.
aは標本を横から,
bは腹側から撮影したもの.外側の殻が無く,縫合線の様子がよくわかるが,その形は古生代後半に栄えたゴニアタイト類の特徴を示している.ゴニアチテスであれば,時代は石炭紀だと言える.
図-051:マクロケファリテス[
Macrocephalites sp.],ジュラ紀,マダガスカル産.
図-052:ペリスフィンクテス[
Perisphinctes sp.],ジュラ紀,ドイツ産.
図-053:ダクチリオケラス[
Dactylioceras sp.]?,ジュラ紀?,産地不明.
図-054:バロイシケラス[
Barroisiceras sp.],白亜紀,北海道産.
図-055:ガウドリケラス[
Gaudryceras sp.],白亜紀,大阪府産.殻の一部.
図-058:アンモナイト[属種名不明],白亜紀,マダガスカル産.
図-059:アンモナイト[属種名不明],中生代,モロッコ産.
図-060:アンモナイト[属種名不明],中生代,ペルー産.
aは標本を横から撮影したもの.
bは住房(生物体が住む最終殻室)の方から撮影したもので,波打つ隔壁の様子が分かる.
図-064:アンモナイト[属種名不明],ジュラ紀,イギリス産.殻の縦断面がよくわかる.
図-065:アンモナイト[属種名不明],中生代,産地不明.
aは殻の切断面側から,
bは殻の外側から撮影したもの.
図-066:アンモナイト[属種名不明],白亜紀,北海道産.殻が横に切断されているので,隔壁の褶曲が中央部では緩やかだが殻に近いところでは激しくなっていることがわかる.
図-067:バキュリテス[
Baculites sp.],白亜紀,北海道産.直線状の殻を持つ.
図-068:ポリプチコケラス[
Polyptycoceras sp.],白亜紀,北海道産.殻がトロンボーンのような形に巻く.
図-069:ディディモケラス[
Didymoceras sp.],白亜紀,兵庫県産.
図-070:ニッポニテス[
Nipponites mirabilis],白亜紀,レプリカ.
a・
b・
cはそれぞれ撮影角度が異なる.
(3) ヤイシ(矢石)類
石炭紀〜白亜紀に生存し,特にジュラ紀〜白亜紀に栄えた海棲動物.ベレムナイト類とも呼ばれる.イカと同じように,軟体部の中に石灰質の殻(矢じり状)を持つ.
図-071:ベレムニテス[
Belemnites sp.],白亜紀,ドイツ産.
図-072:ベレムニテス[
Belemnites sp.],中生代,イタリア産?.
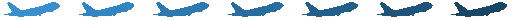
どこへ移動しますか?
ご希望のところをクリックしてください。
![]()