18.裸子植物
維管束植物で,種子によって繁殖し,胚珠が裸出しているもの.デボン紀後期に出現し,ペルム紀後期から白亜紀前期に繁栄した.
(1) シダ種子類
木本性で外形はシダ状の裸子植物.デボン紀後期に出現し,大部分はペルム紀末に絶滅した.中でもここに挙げたグロッソプテリスは,ゴンドワナ大陸を特徴づける植物として有名である.
図-131:グロッソプテリス[
Glossopteris brawniana]の葉,ペルム紀,オーストラリア産.
図-132:グロッソプテリス[
Glossopteris sp.]の葉,ペルム紀,南アフリカ産.
aは標本全体を撮影したもの.
bは1個体を接写したもの.
(2) ソテツ類
古生代に出現して中生代に繁栄したが,現在では残っている属種は少ない.
図-133:ディクチオザミテス[
Dictyozamites sp.]の葉,ジュラ紀,石川県産.
aは標本全体のほぼ半分を撮影したもので,図の上部にあるのはポドザミテス.
bは一部を接写したもの.
(3) 球果類
この類には松柏類など現在も広く分布しているものもあるが,基本的には中生代に栄えた.
メタセコイアは,球果目スギ科の植物で,白亜紀〜第三紀に汎世界的に繁茂したが,日本でも第四紀初期に絶滅した.三木茂は,大阪層群等に産する植物化石を基に,新しい属として1941年にメタセコイアを発表した.その5年後に中国四川省で現生種が発見され,話題となった.現生のメタセコイアは,1種が中国中部に分布するだけであり,“生きている化石”の一つである.落葉生高木で,葉は対生,線形,球果は円〜卵形,鱗片は十字対生.
図-134:ポドザミテス[
Podozamites sp.]の葉,ジュラ紀,石川県産.葉は,広くて平行脈があり,現在も春日大社の裏山などで見られるナギ[
Podocarps nagi]の葉に似ている.
図-135:メタセコイア[
Metasequoia sp.]の葉,第三紀,兵庫県産.
図-136:メタセコイア[
Metasequoia glyptostroboides]の葉,現生,大阪府産.
図-137:メタセコイア[
Metasequoia glyptostroboides]の球果,現生,大阪府産.
bは,このメタセコイアの全景で,左端のプレートは,このメタセコイアが三木茂博士に由来したものであることを記したもの.
図-138:ショウナンボク[
Calocedrus notoensis]?の葉,第三紀,石川県産.
aは標本全体を撮影したもので,
bはその一部を接写したもの.ヒノキ科の植物.
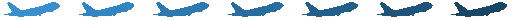
どこへ移動しますか?
ご希望のところをクリックしてください。
![]()