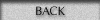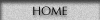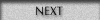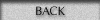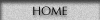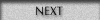被子植物門・単子葉植物綱
多くは草本で、木本性のもの(ヤシ、タケなど)も双子葉植物の樹木のように形成層による肥大成長はしない。茎の中心柱は多数の維管束からなり、不斉(ふせい)中心柱を形成する。葉は平行脈、ときに網状(もうじょう)脈でしばしば葉鞘(ようしょう、葉が茎を巻いて鞘(さや)や筒の形になること)をもつ。花は3数を基本とし、子房の仕切り壁から蜜を分泌するものが多い。ほとんどが単溝(たんこう)型あるいはその変形の花粉をもつ。子葉は1枚、主根は短命で側根が発達する。
(1)オモダカ亜綱
水生あるいは湿地生のオモダカ目・トチカガミ目・イバラモ目と、葉緑素をもたない腐生植物のホンゴンソウ目からなる。オモダカ目は虫媒花で、花被は3枚の緑色のがく片と3枚の白色の花弁からなる。雄しべは3〜多数、最もふつうには2本の雄しべが1枚の花弁に対生する6雄しべをもつ。雌しべは3〜多数。トチカガミ目トチカガミ科には用水路に棲息するクロモ・コカナダモ・オオカナダモが含まれる.ウミヒルモは砂地の海底をはう常緑の多年草である。イバラモ目アマモ科には、砂地の海底に大群落をつくる、アマモ・スガモがある。
オモダカ科 Alismtaceae
クワイ
池や沼のふちの泥土や水田に生える。葉は根生、長い柄があって線形からやじり形、横小脈がある。花序は輪生様総状花序又は円錐花序、まれに単生する。花柄は輪生し、苞(ほう)がある。がく片3、花弁3、雄しべ6〜多数、雌しべはふつう多数が離生。クワイの球塊上部に芽を出したものを「芽が出る、めでたい」にかけて、正月の縁起物として食べる。

トチカガミ科 Hydrocharitaceae
オオカナダモ
塩水又は淡水に生え、全体又は一部が水中にある。茎が短く、根生葉だけのものから、茎が伸びて分岐し茎葉をつけるものまである。花は茎の先に一個つくものが多い。がく片と花弁は3又は2数。雄しべは3、6、9、12個。