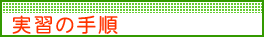 |
|
| <1>流水堆積実験器の製作 |
| ① |
ペットボトルの真中の太さの均一な部分を、その両端で輪切りにして切り取る。さらに縦に2つに切り割り、それらをセロハンテープでつなげて半円筒状の"とい"(流路溝)を作る。といの一端(最上部となるところ)には、ペットボトルの底を半分残した部分を用い、後で水を注ぐ時に水や試料があふれるのを防ぐ。 |
|
|
| ② |
ペットボトルの口の部分を切り取り、といの片端(最上部となる)の底部にセロハンテープでつけ、といに傾斜をつける。傾斜は1/10(高さ/長さ:2.5cm/25cm)位がこの程度の大きさの粒子を流すには適するが、傾斜をいろいろ変えて試すとよい。 |
|
|
| ③ |
これを底の浅い容器(バット)に置く。容器そのものにも片方の底部に厚さ1cm程度のものを挟み、ゆるい傾斜をつける。 |
|
|
| ④ |
といは真っ直ぐなもの、傾斜が不連続に変わるものなど、傾斜の形状をいろいろ変えて試してみるとよい。 |
|
| <2>流水運搬堆積実験 |
| ① |
作成した流路溝の頂部に、かこう岩の粉砕試料を適量(大さじ2杯位)のせる。 |
|
|
| ② |
この粉砕試料の上から水を注ぐ。始めはポリ洗浄びんの細い管の口から少しずつ注ぐ。 |
|
|
 |
|
|
| ③ |
管をはずし、びんから直接先ほどより多量の水を注ぐ。洗浄びんがなければ、ビーカーで水量をコントロールしながら注ぐ。 |
|
|
| ④ |
注水量が少ないと少量の、主に砂と粘土の細かい粒子が運ばれ、これらが流路溝の末端の容器の底に達すると、砂の粒子を多量に堆積する。より細かい粘土の粒子はさらに遠くまで運ばれる。れきは傾斜の急な流路溝でも流れにくい。傾斜が急なほど水の速さは大きく、より大きな粒子が流される。 |
|
|
| ⑤ |
注水量を多くすると、流される物質が多くなり、上の方ではれきの間を埋めるように残っていた砂の大部分と、小さなれきの一部が運ばれ、最後には数mmよりも大きなれきが残る。流路溝から容器の底に流れた砂や粘土はさらに遠くまで運ばれる。 |
|
| <考えてみよう> |
流れる水の力の大きさは、まず流水の量で決まる。同じ水量でも水路の傾斜が大きいと流れが速く、水の力は強い。傾斜がゆるいと流れは遅く、水の力は弱い。山間部を流れる川は傾斜が急で流れが速く、大きなれきがごろごろしている。平野を流れる川はゆったりと流れ、砂や粘土を堆積して平野を作る。水量が少ない時は、上流でもれきや砂、粘土さえ運ばれず水は澄んでいる。大雨になると水かさが増して濁り、れきや砂や粘土が運ばれ、上流では河床の岩盤が削られる。
人間の体以上も大きい巨れきは、数十年に1度の大洪水で動かされたものだろうか。いつ見ても同じ場所にあるように見える。山地と平野の境目は傾斜が急にゆるくなり、大量の土砂を堆積する。これが扇状地である。地図上で淀川や大和川の流路をたどり、川の流れやれき、砂の分布の様子を想像してみよう。 |
|
|
|
|
|