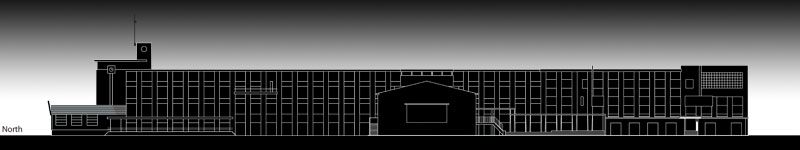岡野貞一を知っていますか
最近、童謡や唱歌が静かなブームになっていて、それらに関する本が何冊も出ている。そこに必ず登場してくる人物に岡野貞一がいる。この名前を聞いて校歌「六稜の星」の作曲者だとすぐにわかる人は、正真正銘の六稜生。愛校心も人一倍と誇ってもいい。すでに本誌11 号(1978 年)に「校歌“六稜の星のしるし”の作曲者岡野貞一氏は『春が来た』『水師営の会見』の作曲者!!」という記事があり、『日本唱歌全集』(音楽の友社、昭47 )に依って、その生涯が簡潔に紹介してある。ここでは、阪田寛夫氏の談を『どれみそら−書いて創って歌って聴いて』(河出書房新社、1995.1 )から紹介しよう(一部要約)。因みに阪田氏は「椰子の実」の作曲者大中寅二(28 期)の甥に当たり、自身も童謡の「さっちゃん」の作詞者でもある。
-
岡野貞一は故郷の鳥取教会で14 歳の時洗礼を受けそこで賛美歌と出会います。その後岡山に行き、岡山教会の宣教師からオルガンを習って音楽の才能を認められ、明治29 年東京音楽学校に入学しました。明治の末、彼は東京音楽学校の助教授になり、小学唱歌教科書の編集委員に任ぜられ、高野辰之らと組んで、大正初めまでに、少なくとも12 曲は作曲しています。「故郷」「朧月夜」「春の小川」「紅葉」「春が来た」など。彼は賛美歌育ちですから、メロデイにはファもシも入っています。『日本の唱歌』(講談社文庫)の前書きで、金田一春彦氏が、日本の唱歌は賛美歌が手本になっていると書いていますが、岡野貞一の曲がまさにそれです。(略)
岡野貞一は物静かな寡黙な方だったようです。クリスチャンですから、東京音楽学校を卒業すると、教鞭をとる一方で、本郷中央会堂という大きな教会のオルガン奏者を務め、聖歌隊を指導していました。以来、42 年間にわたって、昭和16 年に63 歳で亡くなるまで、オルガン奏者としての人生を過ごされたのです。ほんとに無口な方だったようで、近所に講道館の三船十段がおられて、二人で碁や将棋をよく指していたそうですが、三船十段も実に無口な人なので、向合って、し−んとしたまま延々と指していたとか。
阪田氏は、また日本経済新聞のコラム「プロムナード」にも「唱歌もみじ」と題して、岡野貞一のことを次のように書いている。
-
いわゆる文部省唱歌は、誰が書いたのか長い間公開されないままだった。今では「もみじ」は高野辰之作詩、岡野貞一作曲と分っているが、岡野の長男国雄氏からうかがったところでは、昭和16年の暮れに父君が亡くなるまで、家族の誰一人もそのことを知らないでいたそうだ。
高野辰之と島崎藤村をめぐって小説風に書かれた猪瀬直樹薯『唱歌誕生』(文春文庫)にも岡野貞一は登場し、鳥取から岡山に出て、教会に入るいきさつが詳しく述べられている。わが校歌の誕生の経緯は『北野図書館報』第9 号(1985.2 )「六稜外史フラグメンテ(5)」に「『校歌』誕生七十年−作曲者岡野貞一のことなど−」と題して柏尾洋介先生が書いておられるので次に転載する。
-
「今回大典記念の一として校歌撰定の議起り、土井第二高等学校教授に作歌を、岡野東京音楽学校助教授に作曲を依嘱し、十一月十日御大典祝賀式の際五年級一同は式場において新校歌を合唱せり」と校友会誌『六稜』46号が報じたのは大正5年(1916)3月のことであった。前年の11月に大正天皇の即位式があり、校歌はその記念行事の一環として制定されたことがわかる。『学校日誌』によれば、当日午後2時より講堂で祝賀式を挙げ、その最後−3時半すぎ−に校歌を歌っている。但し、おそらく合唱ではなく斉唱であろう。梶山延太郎校長着任3年目のことである。作詞者の土井教授とは、いうまでもなく『荒城の月』の詩人土井晩翠(1871〜1952)であるが、作曲者の岡野貞一(1878〜1941)につき簡単に紹介しておこう。
戦前の文部省唱歌「故郷(兎追いし彼の山)」「春の小川(はさらさら流る)」「朧月夜(菜の花畠に)」「紅葉(秋の夕日に)」や「水師営の会見(旅順開城約成りて)」「橘中佐(かばねは積りて)」「児島高徳(船坂山や)」、さらに「春が来た」「桃太郎」「日の丸の旗」などは彼の手になる。NHKテレビの名曲アルバム(故郷)で知った人もあろうが、鳥取藩士の家に生まれた岡野は岡山に遊学中、米人宣教師に楽才を認められた謹直な新教徒で、40年以上も本郷中央協会のオルガニストとして毎日曜日、礼拝の奉楽を担当した。岡野は神奈川大、旧制長崎中学校、函館中部高校などの旧校歌を作曲したが、いまも「現役」で歌われているのは、本校のみであるようだ。
さて、「六稜の星のしるし」に賛美歌の影響はありやなしや。音楽理論に詳しい方、研究されてはいかが。
参考●『六稜会報No.29』p.13 (1995)
 大阪府立北野高等学校
大阪府立北野高等学校