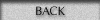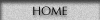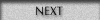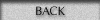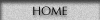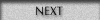(6)バラ亜綱
バラ目・マメ目・フトモモ目・ムクロジ目・フウロソウ目・セリ目など18目114科5万8000種を含む。種数ではキク亜綱とほぼ同数であるが、目や科の数ははるかに多く、被子植物の中でもっとも多様性に富む。果実を食用にするバラ科・ミカン科・ブドウ科はこのバラ亜綱に属する。
バラ科 Rosaceae
ソメイヨシノ
がく片と花弁は5、雄しべは花弁の2〜4倍、雌しべ1〜多数、葉は互生。子房の位置や数はヘビイチゴ属、サクラ属、バラ属など、属によって大きく異なる。サクラ属では、がく片5、花弁5、雄しべ多数、雌しべ1、子房1室と減数している。アンズ、ウメ、サクランボ、モモ、スモモ、リンゴ、ナシ、オランダイチゴは食用に栽培される。

マメ科 Fabaceae
フジ
がく片5、花弁5、雄しべ10、雌しべ1(子房1室)、葉は互生して複葉、ときにつる生。根に空中窒素固定能力のある根粒菌を共生させる、アカツメクサ、シロツメクサは牧草として、ゲンゲ(レンゲソウ)は水田跡に緑肥として栽培される。アズキ、エンドウ、インゲン、ラッカセイ、ソラマメ、ダイズ、それらのモヤシなどは食料としても重要。

アカバナ科 Onagraceae
メマツヨイグサ
葉は対生又は互生し、托葉はない、花は放射相称。花床(かしょう、花の基部)は子房と融合し、それを越えて筒状となる。がく片4〜5又は2、花弁はがく片と同数、雄しべは2、4、6、8、又は12、子房は2〜6室。マツヨイグサ属では、がく片4、花弁4、雄しべ8、雌しべ4、子房4室である。

トウダイグサ科 Euphorbiaceae
トウダイグサ
葉は互生、まれに対生し通常托葉がある、花は退化して単性。がく片はふく瓦状又は辺合状にたたまれ、ときに無いこともある。花弁は多くは無い。雄しべは1〜多数で、葯は2〜4室。子房は通常3室、胚珠は各室に1〜2個で下垂する。

ブドウ科 Vitaceae
ヤブガラシ
多くはつる性の木本、葉は互生し托葉がある、花序は集散状又は円錐状。がく片は4〜5個、花弁はがく片と同数、雄しべは花弁に対生、子房は2〜6室。ブドウは世界で最も広範囲に栽培されている。世界の生産量の80%はワイン原料に使われる。

カタバミ科 Oxalidaceae
カタバミ
がく片5、花弁5、雄しべ5〜10、雌しべ5(子房5室)、葉は互生又は根生、カタバミは全世界に分布する。スターフルーツは熱帯産のカタバミ科ゴレンシの果実。

フウロソウ科 Geraniaceae
ゲンノショウコ
葉は互生又は托葉がある。花は両性で放射対称又は左右相称。花弁5、雄しべ10まれに15、雌しべ3〜5をもつ。関東では白花型が、関西では紫花型が多い。薬草として知られ、その名は「現の証拠」に由来する。干した茎葉を1日7グラム程度、下痢の程度によって濃淡を加減して、お茶代わりに飲む。急性腸炎・扁桃炎・口内炎にも効く。

セリ科 Apiaceae
ヤブジラミ
葉は互生して多くは分裂する、花は小さく複散形花序につく。がく片は子房に融合して小さな5個の突起となる、花弁5、雄しべ5、雌しべ1、子房2室。陽当たりの良い草原に生育する。ミツバ、セリは食用にされ、ニンジン、セロリ、パセリは栽培される。キク科との類縁がある。