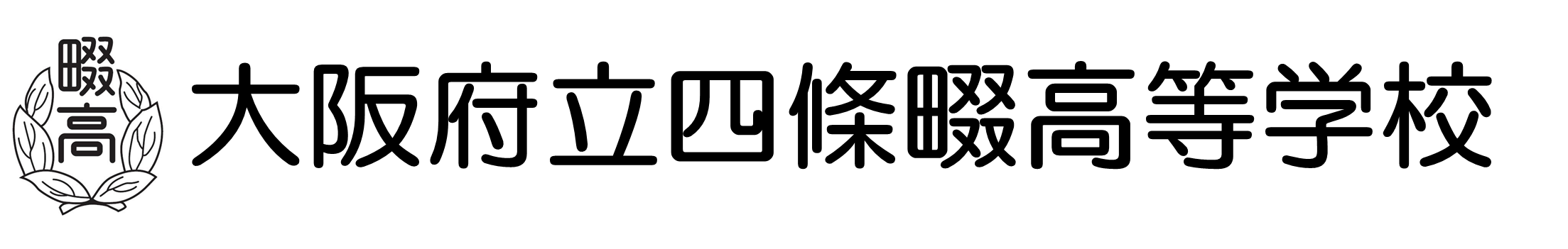SSH
生徒向けTOPICS
教員向けTOPICS
 日々の活動の様子をブログで紹介しています。
日々の活動の様子をブログで紹介しています。

これまで本校が培ってきた探究活動に関するノウハウを探究活動のすすめとして公開しています。
SSH(Super Science High school)とは
「未来を担う科学技術系人材を育てることをねらいとして、理数系教育の充実をはかる取り組み」を実施するべく、文部科学省が指定した高等学校です。 これらの高等学校では「先進的な理数教育を実施するとともに、高大接続の在り方について大学との共同研究や、国際性を育むための取組を推進します。 また創造性、独創性を高める指導方法、教材の開発等の取組を実施します。」
令和7年度は全国で229校が指定されています。
四條畷高校も平成24年年度からSSH指定を受け様々な取組みを実施しています。令和5年度からはSSH第3期の指定を受けました。令和7年度はSSH第3期の3年次となります。
本校での取り組み内容
社会に貢献できる科学技術系人材を育成する教育システムの深化と、地域への成果普及
これまでSSHの取り組みを通して培ってきた探究活動に関するノウハウを積極的に普及していきます。
成果普及のための取り組み
科学系オリンピックに向けた講座の公開実施
課題研究授業の通年公開
毎週金曜日5限目に実施している2年生の課題研究授業「探究チャレンジII」を通年で教員向けに授業公開しています。令和7年度の授業公開の申し込みはこちらからどうぞ。
探究チャレンジIIでは、令和7年9月19日(金)に「中間発表会」を、令和8年1月15日(木)に「成果発表会」を実施予定です。
北河内地区探究活動成果発表会・交流会(北河内サイエンスデイ(KSD))
北河内地区の高校生・中学生を対象とした探究活動成果発表会・交流会(北河内サイエンスデイ)を実施しています。令和7年度は1月31日(土)に実施予定です。日頃の授業や科学系クラブ、個人での研究などの成果や途中経過、取り組みの中での悩みなどをみんなで交流しましょう。文理融合的(学際的)なテーマも大歓迎です。 参加校の教員による交流会も実施します。日頃の授業での困りごとや、探究活動を推進するための組織作りなど、いろいろなテーマで交流会を実施します。北河内サイエンスデイを自校の課題研究の成果発表の場としてご活用ください。
数学探究合宿
今年度は令和7年8月17日(日)~18日(月)に実施予定です。
令和6年8月17日(日)~19日(月)に大阪府立天王寺高等学校と共催で「数学探究合宿」を実施しました。教材やカリキュラムの作成は本校が中心となって担当し、天王寺高校様には広報・生徒集めや宿泊の手配などの運営面全般を中心に担当していただきました。大阪府立高校の先生方を中心に、京都大学の先生、大学院生・大学生TAなど多くの方々にサポートしていただき、大阪府下の高校生48名が参加する一大イベントになりました。合宿では、数多くの数学オリンピックの過去問を題材の一部として扱い、時間にとらわれず仲間たちとじっくりと数学に向かい合う時間を共有しました。
数学探究学習日・SSH数学科合同教員研修(筑波大学附属駒場中・高等学校との連携企画)
令和7年度は令和7年8月22日(金)に実施します。詳細はこちらからご覧ください。参加はこちらのフォームからお申込みください。
令和6年8月23日(金)に、初めての試みとして筑波大学附属駒場中・高等学校と連携して「探究的な数学の授業」を実践する「数学探究学習日」を実施しました。
この取り組みのうち「授業」の部分は生徒への教育プログラムであると同時に研究授業としても位置づけ、他校の先生方への積極的な公開を行いました。府下の多くの学校からたくさんの先生方が参加して下さり、授業後の交流会も大いに盛り上がりました。
令和6年度は初の実施ということもあり、大阪府立高校を中心に広報を行いました。令和7年度以降は、同様の取り組みをさらに進化させて実施したいと考えています。実施の際には、ホームページ上でも情報提供させていただく予定です。多くの学校から多くの先生方と「探究的な数学」について一緒に考える場を提供したいと考えています。
SSH通信
2022年度(令和4年度)より、生徒1人1台端末を活用した直接広報(Classroomを通じた広報)が主となったため、SSH通信の発行が減少しております。ご了承ください。
<2022年度>
2022年度 第3号
2022年度 第2号
2022年度 第1号
<2021年度>
2021年度 第5号
2021年度 第4号
2021年度 第3号
2021年度 第2号
2021年度 第1号
<2020年度>
2020年度 第1号
2020年度 第2号
2020年度 第3号
2020年度 第4号
2020年度 第5号
2020年度 第6号
2020年度 第7号
2020年度 第8号
SSHの教育内容
探究チャレンジ
探究チャレンジI
1年生全員を対象として実施する学校設定科目。 探究活動の基礎となる手法をステップごとに実践的に学びます。 夏休みにはミニ課題研究活動で、さらに実践的に探究活動を学びます。年度末には、探究チャレンジIIに向けたグループ作りなどにも取り組みます。
探究チャレンジII
2年生全員を対象として実施する学校設定科目。 身近な課題を研究テーマに落とし込み研究に取り組む「課題探究」と、物理・化学・生物・地学・数学・情報・学際の7分野に分かれてより専門性の高い研究に取り組む「SS探究」から成り立ちます。
9月の中間発表を最初のゴールとし、以降は「原理や真理の追究」(Whyアプローチ)「仕組みやモノの創出」(Howアプローチ)のいずれかを意識してもう一度研究を見直し、1月末の成果発表会に向けて探究の深化を図ります。
探究チャレンジIII
3年生全員を対象として実施する学校設定科目。高等学校での探究活動を振り返り、将来にわたる自分の学びについて考える、という視点で探究活動を実施します。また、SSH全国生徒研究発表会をはじめとする校外での発表機会を目指して探究チャレンジIIで実施した探究活動を継続実施することもできます。
探究情報
3年間実施する学校設定科目。探究活動に必要なスキルのうち、情報分野にかかわりが深いものを教科「情報I」と関連付けながら、さらに深い内容まで掘り下げて学びます。探究活動を知識・技能的な側面から質的に底上げすることを目指します。
探究ラボ
参加生徒はもう一つのクラブ活動のように課外活動を行います。3年間を通して様々な学び・研修・探究・発表活動に取り組み、校内のSSH活動をリードする役割を担います。
インプット活動・アウトプット活動
興味・関心を育てたり、知識・技能を高めたりするために実施する講演会や見学会などを「インプット活動」、発表会など学んだ事を自らの言葉や文章などで表現する活動を「アウトプット活動」と定義し、3年間を通して積極的にこれらの活動に参加できるように情報提供を行うとともに、積極的な参加を促していきます。
その他の企画
国際性を育む取り組みや、科学オリンピックへの参加、また大阪府内のみならず、 全国のSSH指定校との交流活動など様々な企画を行っていきます。
令和6年度は京都大学数理解析研究所訪問研修や、情報オリンピックに向けたプログラミング講座、数学探究学習日、数学探究合宿などを、公開で実施し、多くの教員・生徒に参加していただきました。
SSH研究開発実施報告書
■第Ⅲ期
SSH研究開発実施報告書 第Ⅲ期2年次(2024年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅲ期1年次(2023年度)
■第Ⅱ期
SSH研究開発実施報告書 第Ⅱ期5年次(2022年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅱ期4年次(2021年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅱ期3年次(2020年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅱ期2年次(2019年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅱ期1年次(2018年度)
■第Ⅰ期
SSH研究開発実施報告書 経過措置1年次(2017年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅰ期5年次(2016年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅰ期4年次(2015年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅰ期3年次(2014年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅰ期2年次(2013年度)
SSH研究開発実施報告書 第Ⅰ期1年次(2012年度)