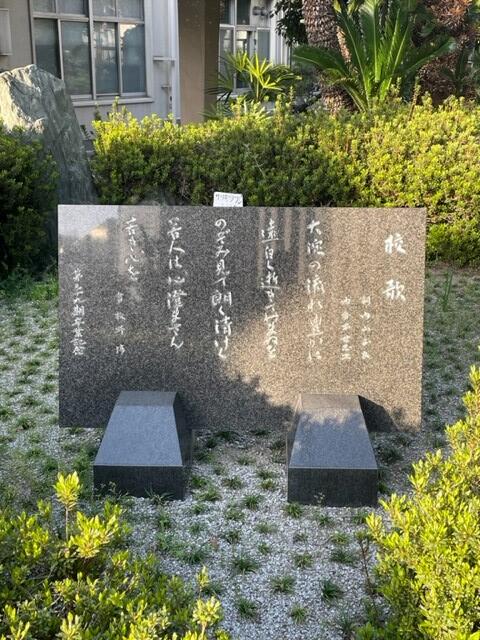4月10日(月)、午後1時30分より、第69回入学式を挙行いたしました。以下に、入学式の式辞(概要)をご紹介します。
桜舞い、草木の新芽が色鮮やかに照り映える今日の佳き日に、新入生及び保護者の皆さま方をお迎えし、第69回入学式を挙行できますことは、教職員一同大きな慶びです。保護者の皆さま方におかれましては、今日までご苦労を重ね、慈しんでこられましたお子様のご入学を、心よりお祝い申しあげます。誠におめでとうございます。
東淀川高校は、昭和30(1955)年に設立され、今年度69年めを迎えます。
平成29(2017)年度に、文系・理系と「看護医療」・「幼児教育」の二つのコースを設置する普通科専門コース設置校になり、この春、第四期生が卒業しました。また、同年度、日本語指導が必要な生徒選抜と、一般選抜を実施する学校になりました。今年度、日本語指導が必要な生徒選抜により、中国、朝鮮半島、ネパール、インド、パキスタン、ガーナにつながり(ルーツ)を持つ16人の生徒が入学をしています。本校は、日本語指導が必要な生徒選抜で入学した生徒と一般選抜で入学した生徒が、ともに学ぶ学校です。本校では、互いに違いを認め合い、誰もが安全で安心な学校生活を送れるよう、生徒一人ひとりに寄り添った教育を進めてまいります。
ただ今入学を許可しました281人の皆さん、入学おめでとう。
皆さんは、これまでの三年間、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けてきたと思います。日本の中学校に三年間在籍していた人は、三年間をとおして学習、学校行事、部活動等の制限があったり、進路選択についても苦労をしてきたと思います。困難な環境のもとで、努力を積み重ねてきた皆さんに、心から敬意を表します。
いよいよ本日から、東淀川高校第69期生としての高校生活が始まります。
高校生になるということは、ある意味では、大人の階段を一段あがるということです。そのような門出の日だからこそ、皆さんにしっかりと理解をしてほしいことがあります。皆さんは合格発表以来、多くの方から「おめでとう」と声を掛けられ、嬉しかったことと思います。ただ、この喜びは皆さんの努力の賜(たまもの)であると同時に、保護者の方、ご家族の方、小中学校の先生方、支援してくださった方など、多くの方々の深い愛情と支えがあったことを、決して忘れないでください。
また、今年も、残念ながら本校への入学が叶(かな)わなかった受験生がたくさん出ました。それだけに皆さんには、「この学校に入学できなかった人の分まで、高校生活を大切にする」という思いを持って、毎日を過ごしてください。
入学にあたって、文化人類学者の松村圭一郎さんの著書から一部分をご紹介します。
1 文化人類学とは何か
文化人類学とは、人間の生活のあり方を研究する学問です。研究方法として、数ヶ月から数年に渡って研究対象とする社会に滞在し、社会の構成員として生活しながら観察・調査をすることがあります。
2 松村さんとエチオピア
松村さんは、平成10(1998)年、大学生のとき、初めてアフリカの国エチオピアに渡航しました。エチオピアはコーヒーの世界的な産出国であり、農業が産業の中心です。松村さんは、初めての渡航以来、何度もエチオピアの農村に滞在して観察・調査を行っています。
3 著書『うしろめたさの人類学』について
平成29(2017)年、松村さんは、エチオピアと日本を往復しながら考えてきたことを、著書『うしろめたさの人類学』で発表します。この著書からから、松村さんが体験したことをご紹介します。
皆さんは、エチオピアと日本、どちらの社会での感情(気持ち)のあり方がよいと考えますか、考えながら聞いてください。
松村さんは、自分自身について、感情的にならない、冷めた人間だと思っていました。
ところが、エチオピアで今までと全く異なる体験をしました。農村での暮らしは、生活のすべてにおいて常に他人との関わりがあり、いい意味でも悪い意味でも刺激に満ちていました。
あるときはおじいさんの愉快な話を聞き、みんなと一緒に笑い転げたり、いざこざ(トラブル)が起きて、涙が止まらない日があるなど、毎日が喜怒哀楽に満ちていたそうです。
エチオピアから日本に帰り、関西国際空港から空港バスに乗った松村さんは、不思議な感覚に陥ります。バスのチケットを自動販売機で買うなど、日本では、人との関りの中で生じるめんどうなこと(トラブル)が取り除かれていたからです。日常生活に戻った松村さんは、日本においてはTVのCMにより物欲が掻き立てられるなど、特定の感情が刺激される一方、多くの場面では、自分の感情が抑制されている、日本は感情をコントロールしている社会である感じたそうです。
改めて、皆さんはエチオピアと日本、どちらの社会での感情(気持ち)のあり方がよいと考えますか。なお、松村さんは、エチオピアと日本、どちらかのみが「よい」とはいえない、と述べておられます。
皆さんは、これからの高校生活を想像してください。異なる中学校等、異なる家庭環境、さまざまな文化的背景のもとで育ってきた皆さんが、東淀川高校に入学してきます。また、皆さんが高校を卒業した後、生きていくこの世界は、自分と異なる考え方を持つ他者との出会い、異なる文化との出会いに迫られる世界でもあります。
皆さんには、何よりも、自分自身が豊かな感情(気持ち)を持つひとに成長してほしいと思います。また、自分とは異なる考えや感情(気持ち)のひとも尊重できるひと、そのうえで適切な行動ができるひとに成長してほしいと思います。
そのためにも、高校生活において、学習、学校行事、部活動、学校外の活動等に積極的に参加してください。その中で人と繋がったり、心を通わせる体験を積んでください。また、自分の思うとおりに人間関係が築けないときもあるかもしれません。そのようなときは自分の感情(気持ち)をふり返ったり、相手の感情(気持ち)を考えて、行動できるようになってしてください。
そのうえで、何か困ったことがあれば、いつでも先生方に相談してください。東淀川高校には、生徒一人ひとりの、ありのままの姿を受け入れ、成長に導く先生方が沢山います。
最後になりましたが、私たちが大切に考えるのは、お子様のかけがえのない未来です。保護者の方々と学校、そして地域社会が連携し、お互いの信頼関係のもとで教育に取り組むことが、子どもたちの健やかな成長を促す唯一の方法だと考えています。ご心配なことがございましたら、いつでも遠慮なくご相談ください。
私たち教職員一同、皆さま方のご期待に添うよう力を合わせ、281人全ての生徒が安心して学校生活が送れるよう、一人ひとりに寄り添いながら、「入ってよかった。行かせてよかった。」といわれる学校づくりに邁進してまいります。
何卒、ご理解とご支援をお願い申しあげ、式辞といたします。
令和五年四月十日 大阪府立東淀川高等学校長 森瀬 康之