急に寒くなりました。明日は一層寒くなるようで、僅か2~3日で日最高気温が10℃ほども下がりそうです。週末には小雪を迎え、いよいよ冬構えの時季が来たようです。

今日は4時間授業を見学しました。1時間めは1年1組「地理総合」の授業を見学しました。担当は日下泰一先生、ケッペンの気候区分における温帯の気候の特徴や該当する地域について学んでいました。はじめに、これまで学習したことの復習を兼ねて、写真や図表を投影しながら、いろいろな話をされました。上の写真は、イランの乾燥地域に見られる「カナート(地下用水路)」の断面図で、アフガニスタンやパキスタン、北アフリカ等にも同様のものがあり、例えば北アフリカでは「フォガラ」と呼び、地域によって言い方が異なると話されました。そもそも言語が異なるので、そうだろうなと思いましたが、日本にも三重県北部に「マンボ」と呼ばれる同様のものがあると聞きました。これは関大の入試問題に出題されたそうです。冒頭からとても勉強になります。
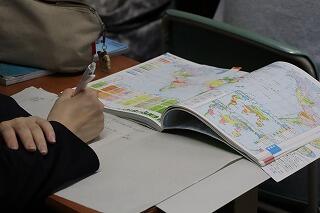
ケッペンの気候区分で温帯は、Cs(地中海性気候)、Cfa(温暖湿潤気候)、Cfb,Cfc(西岸海洋性気候)、Cw(温暖冬季少雨気候)に分けられています。前の授業でCsとCfaについて学習し、今日はCfbとCfcとCwについて詳しく学びました。
CfbとCfcはどちらも西岸海洋性気候と呼ばれて一緒に扱われることが多いようですが、CfbとCfcの決定的な違いは「農業ができるか否か」、できるCfbとできないCfcだと話されました。そこで、先生は、「温帯なのに農業ができないのはなぜだろう」と発問されました。思考力が問われています。
区分の定義は次のとおりです。温帯のうち1年を通して降水がある程度以上あり、月平均気温が10℃以上の月が4か月以上あるのがCfb、1か月以上4か月未満がCfcに分けられているとのことです。Cfcは夏が短く、農作物が十分に育たないのです。
「では、最暖月の平均気温が10℃以上の月が1つもないのは何気候ですか?」と続けて発問されました。ヒントは「これは引っかけです」(^^)/
「正解は寒帯。冷帯だと間違える人が多いので気をつけてください」と、教えられました。

次に、Cfcがある場所を地図帳から探し出し、アラスカの太平洋側とノルウェーの沿岸地域についてとても興味深い話をされました。どちらも高緯度なのに温帯になっているのは、暖流の影響を受けているからで、海は冬でも凍ることがなく貴重な「不凍港」があること、その港を利用して、例えばアラスカ北部のブルドーベイ油田で採取した石油を南部の不凍港であるヴァルディーズまでパイプラインで運び出していること、そのパイプラインは日本の企業がつくったこと、凍結防止と野生生物の移動の妨げにならないように1.5mの高さに設営したこと等、書き出せば切りがありません。
あっという間の50分、盛り沢山の内容を生徒たちは熱心に学んでいました。有難うございました。