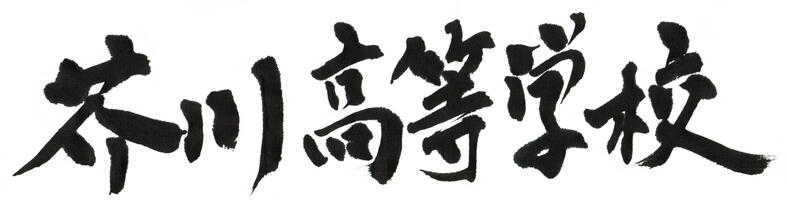1985年8月22歳の夏。インドでの井戸を掘るボランティアへの参加が決まったものの、インドの政情が不安定で外国人の入国が厳しい状況となり東京で数泊過ごした後、当初からの訪問予定であったスリランカへの渡航が決まった。
朝、昼、夜と本場のカレーを堪能し、水に十分注意していたにも拘らずジュースに入っていた氷に攻撃され、心身ともに少し疲れていた。全旅程の半分が過ぎ、上手に右手でカレー(と混ざったご飯)を食べることやお湯をもらうときにはHot WaterではなくBoiled Waterが適切であるということを学べ、何かこの国の力になれることはないかと思える余裕が出てきたころ、青年海外協力隊としてボランティア活動をしている男性と出会った。損得ではない「何か」を見つけるためにやってきたという彼の一言、一言が心に届いた。
その当時、日本ではコンピューターゲームを奪いあい、傷つけあうという痛ましい事件も起こっていた。ものの溢れる豊かさと心の豊かさのバランスが問われる時代であった。(そしてそれは今も変わらないかもしれない。) 私たちの折った十数羽の鶴を村の数十人の子どもたちは独り占めせずみんなで愛でてくれた。豊かな心と澄んだ瞳を持った子どもたち、彼(女)らは次々に日本人への好意を口にした。それは青年海外協力隊の男性が掛け値なしで村の人たちの暮らしを支えてくれているからだ。大したことができなかった私たちにせめてものお礼ですと言って彼は歌をプレゼントしてくれた。 ♬ 兎(うさぎ)追いし かの山~水は清き ふるさと ♫ 1番から3番まで淡々と歌ってくれた。 何かを語るのでもなく、想いを伝えるのでもないその時間に「形にならないもの」あるいは「形にならないこと」を私たちの心の中に携えてくれた。1985年8月 22歳の夏 JICAの方に始めて触れた。もしかしたら私が国際交流に携わるようになった原点はこの時にあったのかもしれません。「JICA国際協力出前講座」に参加するみなさんにとって2021年7月12日がそんな瞬間になることを心から願っています。