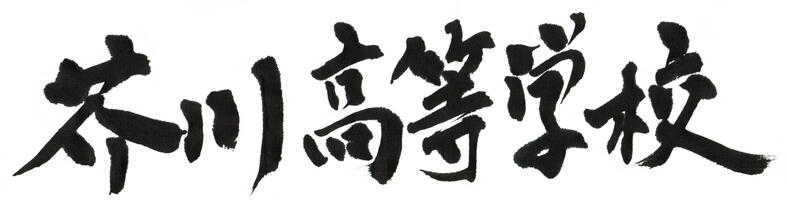1月27日(木)5時間目、1年生の教室でいい時間を過ごさせてもらいました。世界史の研究授業でした。以前、模擬試験について、当日だけじゃなく、受験までの準備、そしてそのあとの解説を読みながらしっかり復習をすることが大事であるとブログで書いたのと同様に研究授業もこの5時間目だけではなく、それまでの準備、そのあとの研究協議が非常に大切なのですね。生徒の皆さんは一生懸命活動していたのでわからなかったかもしれませんが様々な教科の十数名の先生方が教室の内外で授業を見学しておられました。研究協議の中では教授内容はもちろん教材の提示の仕方、教材研究の在り方など専門的な見地からいろいろなご指摘があり、白熱した意見交換が行われました。それぞれの教科・科目で真摯に「教える」「学ばせる」ということに向き合っている先生が多数いることに心強さを感じました。
専門的な知識が乏しいので、ここでは授業の中で見た生徒の皆さんに驚いたことを紹介します。この授業でみなさんはでどれくらい頭を働かせましたか?考えるというところに力点を置けばおそらく90%近くの時間を費やしていたのではないかと思います。ジグソー法で行われた授業の中で、常にTaskと向き合い、アウトプットを意識しながらインプットをする、つまり文章の中身をほかのメンバーとどう共有し、どう伝えるかを考えながら読んでいたということです。そして次の段階では中身を知らない人への説明です。一つ階段を上り、伝え方に工夫が必要です。そして最後全体に向けての発表です。思考力と表現力をつける協動的な学びです。段階を経ながら、生徒の皆さんの発表のスキルが上がっていくのが見て取れました。
何よりもうれしかったことは、みんな嬉々として取り組んでいたことです。当然、得意不得意、巧拙があって当たり前なのですが、その中でそれぞれが、そのままでいいという多様性を認めている姿勢に感銘を受けました。あるグループの人の会話です。「誰もやらんねやったら発表するわ。」「うわ、助かる。私人前でしゃべるん苦手やから、文考えるな。」役割を自然に分担し、それぞれの得意分野で自分を生かすということが自然にできていること。授業の教授内容以外に様々なスキルを身に着けることができ、なおかつ自己実現する機会を設ける授業。さりげなく、トランプを配り、1から13までのグループが出来上がる。まだまだ改善点はたくさんあるかもしれませんが、繰り返しやる中で、授業の中で生きていく力を身に着けていくことが可能だということを示してもらった授業でした。
 生き生き学ぶ姿を見せてくれた生徒の皆さん。多くの可能性を示してくれてありがとう!見学に来て、研究協議やその他の場面でご教示いただいた先生方、ありがとうございました。そして何より、チャレンジしてくれた吉田先生、一番大きなお土産をもらったのは先生です。お疲れ様でした。そしてありがとう!
生き生き学ぶ姿を見せてくれた生徒の皆さん。多くの可能性を示してくれてありがとう!見学に来て、研究協議やその他の場面でご教示いただいた先生方、ありがとうございました。そして何より、チャレンジしてくれた吉田先生、一番大きなお土産をもらったのは先生です。お疲れ様でした。そしてありがとう!