10月25日(金)2時間めに3年5組の「論理国語」の授業を見学しました。題材は文化人類学者で東京外国語大学名誉教授の今福龍太氏の評論「エコロジーのミューズを求めて」、担当は高岡先生です。

教科書の筆者紹介に「中南米地域を中心にフィールドワークを行い、文化が融合する境域に生きる人々の思想について追究する」とあるように、今福氏の論拠は「フィールドワーク」にあると言えそうです。「エコロジーのミューズ」ということばの生誕は、筆者が目の当たりにしたアメリカ・インディアンが、「私はまわる/大地のへりを/長い羽根の翼をつけ/舞いながら......。」と踊り歌うことばが、「土地の棲息者」である感覚を語るための限りなく研ぎ澄まされた「詩」として認識した瞬間に由来しているのではないかと推察できます。

近年、学校教育の現場で「探究的学習」が脚光を浴び、本校でも「未来探究」と称してフィールドワークを取り入れた活動を実践していますが、筆者の言う「現在のエコロジー思想の表層的な展開」と同様の行動様式に留まっていないか検証する必要があります。この評論を読んで、これまで取り組んできた「未来探究」について、「フィールドワーク」が自身にもたらした影響について再考させられた生徒も少なくなかったのではと思います。
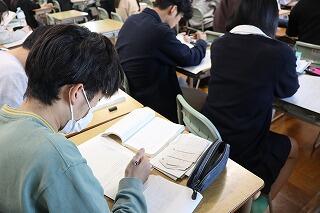
「政治」でもなく、「ビジネス」でもないエコロジー、それは、言語的アートとしての精緻な表現能力を与えられたエコロジーだけが、21世紀に向けて生まれ始めている新たな「主体性」と「自然」との関係をめぐる倫理学を、真の生態学的叡知(エコソフィア)へと導いていくことができるのである。と筆者は結んでいます。
先生の発問と導きにより、生徒たちはよく考えていました。有難うございました。