今日は、2時間めに3年「文学講読」、4時間めに1年「論理・表現Ⅰ」の授業を見学しました。「文学講読」は本校独自の学校設定科目で25人が選択しています。また、「論理・表現Ⅰ」は1年次英語の必修科目で週2時間全員が履修していますが、同時2クラスを3展開して行っているため、1講座26~27人で授業を行っています。日本語と英語、どちらも「ことばを学ぶ」授業です。

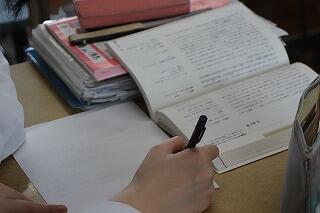
2時間めの「文学講読」は、森鷗外の「舞姫」を読んでいました。「舞姫」は、近代日本文学において、夏目漱石と双璧をなす森鷗外の1890年に発表された短編小説です。鷗外は私のちょうど100歳上の1862年生まれですから、「舞姫」は28歳の時の作品で、鷗外が現在も生きていたら163歳になっていることになります。私が生きる100年前に生きた作家の小説に綴られたことばは、現在小説のことばとは随分違うことを思うと、私が生きる100年後に生きる作家は、どのようなことばで綴られるのでしょう。人から人へと伝わることばは、絶えず変化していく生きもののようなものかもしれません。
28歳という若さで「舞姫」を発表した鷗外は、19歳と5か月で現在の東京大学医学部を卒業したというのですから相当な秀才であったには違いないでしょう。高雅な文語体で綴られた「舞姫」を読み解くのは簡単ではありませんが、じっくり味わいながら熟読したいものです。
授業では、第1段落から第2段落へ、舞姫であるエリスが出てくるのはもう少し先になります。生徒達は先生の説明を聞きながら、しっかりと読み解き熱心に学んでいました。


4時間めの1年「論理・表現Ⅰ」英語の助動詞の用法について学んでいました。助動詞は伝える言葉の細やかなニュアンスを言い表す重要なことばです。日本語でも、「ちょっと話できる?」、「ちょっと話できへん?」というように、Can~? か、Cannot~?か、でその場面に応じて伝えたいニュアンスが正確に伝わるように、自然と使い分けています。あるいは、肯定文から始まる付加疑問文や、否定文からから始まる付加疑問文も同様で、助動詞と組み合わせることで、ニュアンスの幅がより広がるでしょう。
can, may, must, have to, will, would, shoud,..., いろいろな助動詞が動詞をどのように「助け」て、伝えたいニュアンスを引き出すのか、このことをマスターして会話の中に入れることができるようになれば、グンとネイティブが使う英語に近づけそうな気がします。そう思うのですが、私にはまだまだ遠い道のりです。
もう一つ、英語は、時制に気を付ける必要があります。折角適切な助動詞を使えても、時制が誤っていればうまく伝わらない場合があるでしょう。ここが学習のポイントだと、先生が強調されていました。

自分で書いたり、ペアワークで会話をしたり、ネイティブの会話をリスニングしたり、英語で必要なReading, Writing, Listening, Seaking の4技能を伸ばす時間を確保してテンポよく進められていました。4時間め、お腹が空く頃なのに、よく頑張っているなぁと思いました。この調子で頑張ってくださいね。