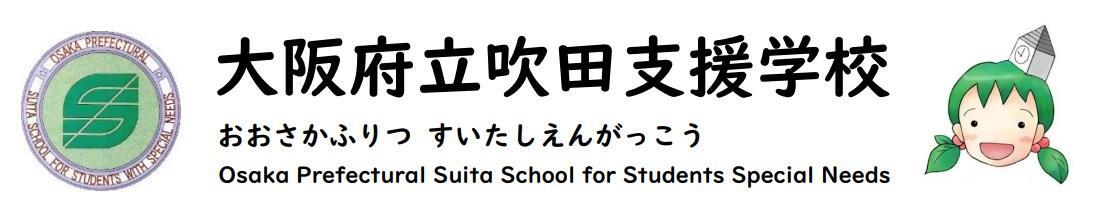2月5日(金)5・6時限 於美術室2に、高等部1年生の美術の授業で『授業研究』の研修が行われました。
プランナーは美術科の谷口先生です。
生徒はいろいろな方が見に来られていることで、いつもと違う雰囲気を感じ、はじめは緊張していましたが、段々と授業が進んでいくうちに先生の授業の世界に入っていきました。
単元「コラージュ もしも3部作 第2 もしも相田みつをを旅したら」
(第1 もしも名画を旅したら)
(第2 もしも相田みつをを旅したら)
(第3 もしも自分で描いた線を旅したら)
*コラージュとは画面に印刷物・写真・布きれ・木の葉などを貼り付けて特殊な効果を生み出す
絵画の技法。糊付け。
学習内容は以下の通り。
①始めのあいさつをする。
②名前を呼ばれたら返事をする。
③前回制作した作品をみてコラージュ制作を思い出す。
④今回のタイトル「相田みつをを旅したら」を聞き、相田みつをについて知る。
⑤手順どおり制作をする。
No.1 台紙をもらう。(以前に墨で制作した作品)
No.2 マスキングテープを貼る。
No.3 動物の写真を貼る。
No.4 シールを貼る。
No.5 自分の写真を貼る。
No.6 相田みつをの詩を貼る。
No.7 裏にタイトルを貼る。
No.8 ラミネートする。
⑥完成した作品を鑑賞する。
⑦片付けをする。
⑧終わりのあいさつをする。

花熊先生からは、「授業をよくお考えになって用意をなさった。」とことばをいただいた上で、
次のようなコメントをいただきました。
・生徒さんが「自分がしている」、「先生にやらされている」、どう感じるか ― いかに子どもがやったという感じを持てるか工夫し、仕掛けていくかがポイントである。やらされた感じではなくやり遂げたと思えることが大事である。
・サブの先生Aは、生徒に押し付けることなく辛抱強く上手に接している。『した』という実感が得られている。教師が手で持つ画用紙に何かを貼る場合、バインダーなどが後にあれば、手ごたえを感じられ、自分がしたというように思える。
・生徒が落とした茶色い封筒を先生Bが拾った場面があった。生徒が1枚落としたことに気がつかなくてはいけない。気がつけば、拾う・持って行くことができる。うまくいかないことを自分で修正して行うとやり遂げ感が出る。
・すごいパワーを持っている生徒さんには、そのパワーを生産性の方向に持っていくのがよい。重みのある両手で押すゴムスタンプを使い、1枚押すたびに「ご苦労さん。」と言うように。
数々のヒントをいただき、これからの生徒との関わり方に生かしていきたいと思いました。