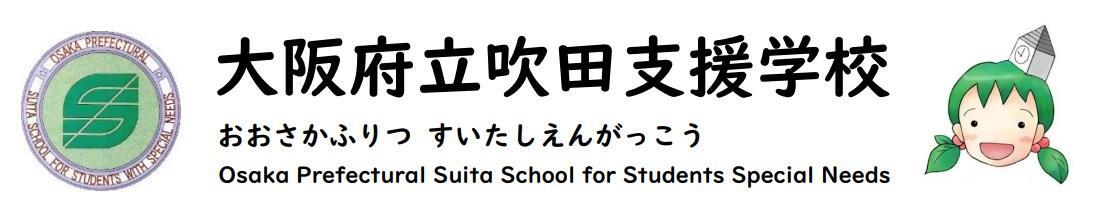「発達支援のためのアプローチ ~からだを通したコミュニケーション~」
3月も中旬となり、いよいよ春という感じですね!
さて、このブログでは今回から数回にわたって、1月に実施された実践交流会の分科会の様子を報告したいと思います。まずは、B分科会についてです!
分科会B「発達支援のためのアプローチ〜からだを通したコミュニケーション〜」
講師 中野弘治先生(こころとからだの発達相談塾MADA代表)
B分科会は本校図書室を会場にして行われました。外部の方も含めて30名程度が参加し、2時間にわたって講義と実技が行われました。
講師には「こころとからだの発達相談塾MABA」の代表である先生をお迎えし、心理療法の一つである臨床動作法の観点から障がいをもつ児童・生徒の発達支援のためのアプローチについてお話いただきました。

学校や園の中でよく目にする子どもたちの様子や先生がライフワークとされているカンボジア支援で出会った子どもたちのお話など、具体的な事例から障がいのある子どもたちの心の様子と姿勢の関係について、とてもわかりやすくご説明いただきました。参加者もメモをとりながら先生のお話に興味深く耳を傾けていました。
講義の随所では実技も行われ、ペアになった参加者が先生役と生徒役に分かれて「肩のリラクセイション」や「躯幹のひねり」などを行いました。

はじめはお互いに手探りながらも、それぞれが自分の身体に感じる感覚や、相手から伝わってくる感覚に身を任せて身体を動かしていくことで、だんだんと身体がリラックスしていくのを体験したり、相手の身体のようすを手のひらを通して感じとったりすることができました。自分の感じた身体の感覚を参加者同士で報告し合ったりするなど、実技に熱心に取り組む様子が見られました。
講義の最後に行われた質疑応答では、時間いっぱいになるまでフロアから活発に質問が出され、今回の講義への関心の高さがうかがえました。内容の濃い2時間となりました。