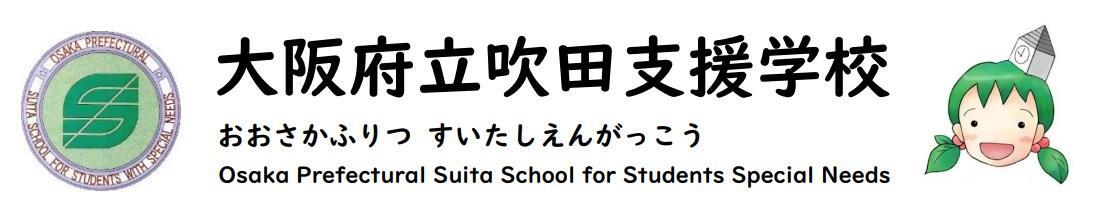5月15日、本校にて、第1回校内学習会「アセスメント①(行動観察と記録)」を実施しました。
個別の支援計画・指導計画を作成するための、児童・生徒の実態把握の方法(行動観察と記録の取り方)について、本校コーディネーターの藤城先生から講義をしていただきました。また実際に担任している児童・生徒について、どう記録するかそれぞれ考えました。

① 行動とは?
・人間や動物の観察可能(見てわかる)で測定可能(回数・時間など)な行為
・生きている個体にしかできないこと
・人の思いや考えも内在的言語行動である。
・「~ない」ではなく「~ある」で記述される。
(例「学校に行かない」ではなく「家でゲームをしている」)
② 行動の測定方法
・頻度(例:授業中に自分の席から立ち上がる回数)
・強度(例:泣き声の大きさを5段階で評価する。)
・時間(例:教室を飛び出してから戻ってくるまでの時間)
*行動の記録をつけるときは上記の観点を踏まえて記録を取る。
支援・指導を通して頻度・強度・時間を減らす(増やす)ことができたか検証する。
③ 指導・支援の対象となる行動とは?
・多すぎる行動(減らしたい行動)
例:自分の頭を叩く、独り言を言う、ベランダから物を投げる
・少なすぎる行動(増やしたい行動)
例:枠からはみ出さずに文字を書く、自分からあいさつをする
④ 行動の記録
・頻度
例)授業中に自分の座席から立ち上がる回数(高頻度行動)
日時 場所 チェック欄 合計回数
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5/14 1時間目(国語) 1年1組教室 ○○○○○○ 6回
5/14 2時間目(算数) 1年1組教室 ○○○ 3回
・頻度(回数)を数えるときは、ポケットにカウンターを入れておく、おはじきを右から左のポケットに移動する、ビデオに撮ってみるなどの方法がある。その時にできる無理のない方法で行う。
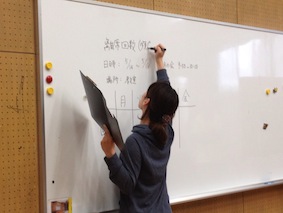 ⑤ 機能分析(ABC 行動分析)
⑤ 機能分析(ABC 行動分析)
A:直前のきっかけ → B:行動 → C:結果
例)
日時・場所 直前のきっかけ 行動 結果 考えられる機能
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5/14 先生がプリントを配る プリントを破る 先生が叱る 注目要求
1時間 課題からの逃避
1年1組教室
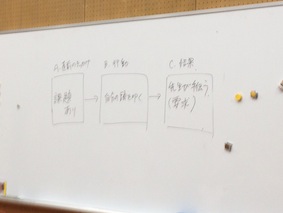
*④と⑤について各自、記録を取り、次回の研修会で「個別の指導計画」を立てることになりました。