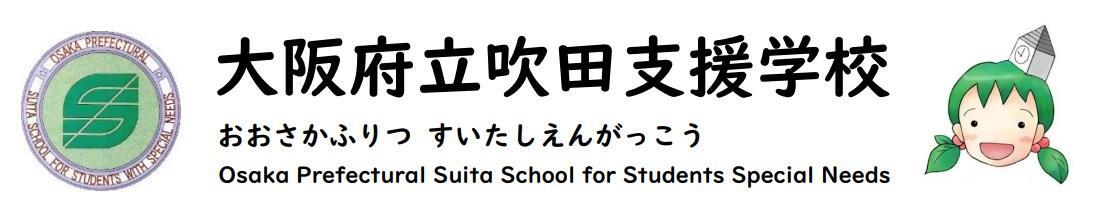分科会Aの講師を担当していただいたのは、大和大学教育学部准教授でいらっしゃいます、井上和久先生です。
井上先生は、知的障がい児教育、発達障がい児のアセスメントと支援、早期からの相談支援、特 別支援学校のセンター的機能などを主な専門・研究分野とされていて、LD学会や日本発達障がい学会 など、所属されている数々の学会の機関紙などで研究発表をされています。
H26年1月『障がい者の権利に関する条約』が批准され(発行は同年2月)、H28年4月『障がい者差別 解消法』が施行されます。
『障がい者の権利に関する条約』第二十四条には
・障がい者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質が高く、かつ、無償 の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。
・個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
と、あります。
『障がい者差別解消法』が施行まで3ケ月を切ったという状況の下、井上先生に「インクルーシブ教育と 合理的配慮」という題で講義していただきました。
インクルーシブ教育システムとは:人間の多様性の尊重の強化、障がい者が精神的及び身体的な能力等を 可能な最大限度までに発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障がいのある者と障がいのないものが共に学ぶ仕組みである。(国立特別支援教育総合研究所HPインクルDBより)
合理的配慮とは:障がいのある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障がいの ある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものをいう。 学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面に均衡を失した又は過度の負担を課さないものとあります。
基礎的環境整備とは:障がいのある子どもの支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村で、教育環境の整備を行う。これらは「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶ。
基礎的環境整備と合理的配慮とは区別しなくてはいけない。
資料に沿って1時間40分の講義があり、その後質疑応答にうつりました。次々と質問が上がり、皆さんの関心の高さが窺えました。
講義及び質疑応答の時間を通して、先生が言われたのは、「支援学校はインクルーシブ教育システムのセンター的役割を果たす。」「組織的に考え進めていかなくてはいけない。」ということでした。今以上に、相互理解、共通理解を深めなければならないと感じました。
「大和大学(吹田駅近く)からは、自転車で15分くらいです。お手伝いできることがあればはせ参じま す。」という心強いお言葉をいただき、分科会を終了しました。