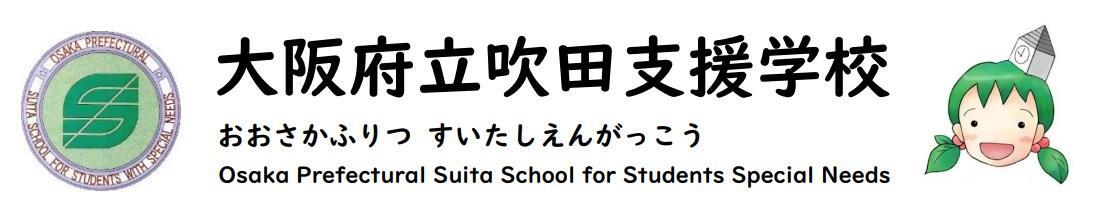8月3日(金)視聴覚室にて、講師に本校中学部コーディネーターの福田先生を迎えて「実際に使っている視覚支援の例とその効果について」の高等部の研修を行いました。
中学部で使っている例は以下の通りです。
①スケジュール(時間的構造化)--- 時間割・カレンダー・授業の流れを表で提示されることにより生徒は見通しを立てることができます。個別対応カードもあります。修学旅行についても、時系列に写真を提示して、知らないところに行く不安を和らげることができ順調に旅行できました。
②場所の構造化 --- 図書室前の壁に上靴の絵を貼り床に足の形を貼る →一目でどうすればいいのかが理解できます。
③視覚的構造化 --- 朝のランニング時に何周したか分かるように自分用の数字カードを持っています。
④コミュニケーション --- 発語のない生徒が、感情を表すカードを指さし、自分の今の気持ちを伝えたり、絵カードを指し必要なものを伝えます。
⑤行事 --- 学習発表会では、自分の出るタイミングや言うセリフが分かるよう生徒の写真入りのPower Point を使って事前学習をします。
⑥授業 --- 理科では自分の体を知ろうと食べ物が体の中に通って行く道筋などをPower Point を使って示したりふくわらいなどのゲームも行います。

視覚支援で大切なことは、理解できる形式(文字・写真・イラスト・大きさ・種類等)は対象の生徒が分かりやすいものを使用して効果のある形式(見通し・自信・自立)のものとすることであるとのことです。
講義の後は、ワークショップを行いました。二人1組になって話し合い、アンケートに記入していただきました。
<1、紹介された活用例で高等部の生徒にも活用できそうなものを挙げて下さい。2、視覚支援になるものを考えて下さい。>
講義内容を振り返り、自分の新たな物を考えるきっかけとなりました。
視覚支援の仕方を熟知した上で、「視覚支援は一つの方法である」と話す講師の先生の姿勢が素晴らしいと思いました。生徒をよく知ることの大切さを改めて感じさせられる有意義な研修となりました。