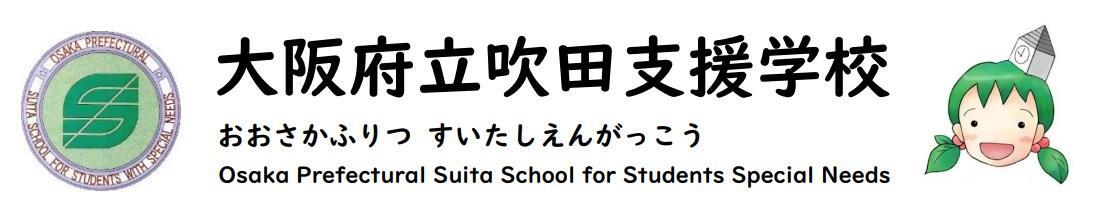本校高等部では、12月17日16時より、『発達障がい児の感覚運動あそび』についての研修を行いました。
講師は、神戸親和女子大学准教授の森田安徳先生。先生は特別支援教育を専門にされ、読み書き障がいの評価と支援方法・発達障がい児の感覚運動遊びについて研究されています。
まずは、Power Pointで説明をしていただき、後半実際に行っている感覚運動遊びの数々をDVDで見せていただきました。先生のお話や資料から抜粋しました。

高等部の生徒にとっては、感覚運動あそびが余暇スキル・身辺自立・学習や仕事をしていく力へと発展していく。教室で字を書くことは、座位の姿勢保持・肩肘の固定・両手の協調・黒板を見るための視力・形の認知視聴覚および聴覚的な注意の集中といったことができて成り立つ行為である。
①聴覚(聞くこと)/②前庭感覚(重力と運動)/③固有感覚(筋と関節)/④触覚(触れる)/⑤視覚(見ること)の感覚が統合され、様々な段階を経て発達していき、最終的に集中力/組織力/自尊心/自己抑制/自信になっていくのである。
この考え方に基づいて、様々な遊びや運動・遊具などが考えられている。
②前庭感覚とは、耳石器・三半規管より入力される感覚を言い、この感覚運動のための遊具は、公園の滑り台・ブランコ・鉄棒、そしてトランポリン等多くのものが挙げられる。
③触覚の発達に課題のある子どもは、触られることを嫌がる・極度に痛がったりまったく痛がらなかったりする・触られた体の部位がわからない等の反応を示す。この感覚の遊びとしては、どろ遊び・水遊び・ボールプールあそび・マットあそびなどが挙げられる。
④固有感覚とは、筋肉や関節、膝から入力される感覚を言い、発達に課題のある子どもは、力を抜くことが苦手だったり、適切に、均等に力を入れることがむずかしい。この感覚の遊びとしては、綱引き・そりあそび・棒引き・壁逆立ち・スクーターボード押し等が挙げられる。
①⑤視覚や聴覚は「遠位感覚」と呼ばれる、視覚や聴覚が入ると、認知的要素が大きくなる。ゲームでは、視覚・聴覚を協調する活動が増える。フルーツバスケット・バンブーダンス・ケンパで赤円を加え、「赤円は飛び越す」あそび等が挙げられる。
①②③に関連して、腹筋や背筋で体感を支えられれば両手が自由に使え、姿勢バランスの保持が図られる。①②③の統合の結果である。この感覚の運動としては、そんきょ・スクワット・タイヤ歩き・タイヤのぼり・平均台・いろいろな道歩き等が挙げられる。
お話を伺った後、こういった遊びや運動の数々をDVDで見せていただき、実際に運動している様子・子供たちの表情を見ることができました。最初、こわごわと始めた子供が、だんだんできるようになり、できた~という表情をそっと見せるのがとても印象的でした。
子供たちの行動や反応を観察して、課題を把握して、課題をみんなと一緒にやっていく。その中で各々の状態に応じて先生が工夫をしていく個別対応を行っている素晴らしさがわかるDVDでした。
私たちが参考にできることが満載の研修でした。自分たちの携わっている教育活動にどう活用していくかは私たちに問われるところです。