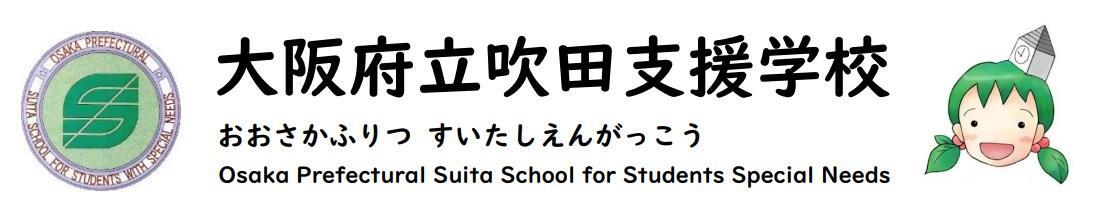実践交流会の報告の続きです。
分科会Bは中野弘治先生による「発達支援のためのアプローチ~からだのリラクゼーションを中心に」というタイトルで、心や体の緊張により生活に支障が出てくる部分を「体の動きを通した療法」により望ましい方向に変化するように援助をする動作法について体験しました。

「動作法」を2人1組になって体験
柔軟体操
痛いという恐怖体験があるので、力を入れて体を防御するため曲がりにくい。後ろの人は手を背中に添えるだけで本人が自分自身で体を左右に揺らす、傾いたときにおしりを後ろにずらしていくという動作で、無理なく前屈できるようになってくる。
・あぐらで座り背中を丸くする

手の操作性に影響が表れるということを知る。
ここぞというときに背中をまっすぐにできるかということが大切。
(しかしずっとまっすぐにしておかなくてはいけないということではない)
・肩の上げ下げ
胸、肩辺りの緊張を和らげる。
後方から肩を包み込むように支持し、肩を上がる方向に力を入れさせ、数秒間緊張を保持してから、肩の力を抜くように援助する。
・仰臥位での腕の上げ下げ
仰臥位でゆっくり腕を上げ下げする動きを通して肩周辺の緊張を緩めていく。
毎日の児童生徒の動きを観察し、体が緊張していると気づいたら紹介したようなストレッチをして緊張を緩めてやると児童生徒に落ち着きがみられるようになるとのことでした。
みなさん、熱心に取り組んでおられました。