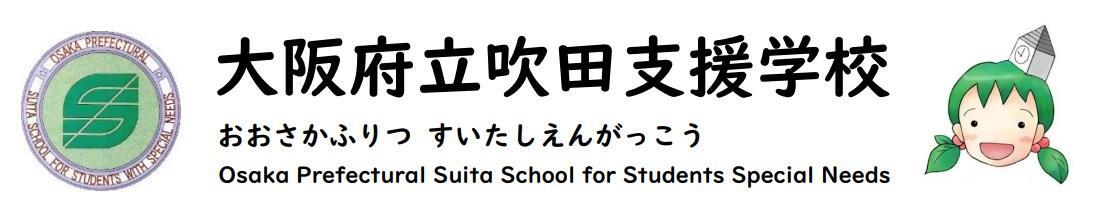分科会C タブレットPCを利用した知的障がいや発達障がいのある児童生徒に対する支援」
視聴覚室にて、岡本崇志先生(大阪府教育委員会)をお招きして、「タブレットPCを利用した知的障がいや発達障がいのある児童生徒に対する支援」というタイトルでの研修を実施しました。

最初に、イントロダクションで2つのテーマの提示がありました。1つ目は「個々の特性に合わせた利用」で、一人ひとりの個性に合わせ、その子が使える支援を作っていくことが大切であり、記憶型の支援では「メモ」や「ボイスレコーダー」、時間型の支援では「タイムエイド」などの支援方法の例を紹介していただきました。2つ目は「授業内での利用」で、「教員がICT活用」から「児童生徒がICT活用」へシフトしていくことが必要であり、また同時に他の教材教具がいらなくなるわけではなく、必要に応じて適宜利用すればよいとのことです。
後半は、各学部の先生から一人ずつ実際の授業で取り入れているICT教材を発表していただきました。
1.小学部での活用・・・「ひらがな」のアプリ
小学部1年の「ことば」の授業で使用。この授業では学習能力に個人差があるため、個別学習として、またひらがなの理解度確認のために活用されています。ひらがななぞりやかるた、単語作りなど活動ごとにレベルも選べ、短時間でいろいろ学習でき、間違えてもすぐやり直せるため、教師も生徒もストレスが少なく学習できるそうです。発表後、岡本先生より「アプリの使い方は教師がいかに使うかにかかっている。アプリも万能ではないので教師の技量にかかっている。」とのコメントをいただきました。

2.中学部での活用・・・「Pages」のアプリ
中学部2年の「国語英語」の授業で使用。この授業では将来就職する時に必要であろうパソコンの文字入力を学習するため、このパソコンのワード版であるこのアプリを活用されています。見本の文章を見ながら生徒が入力していったり、インタビュー活動でインタビューしたことを入力して整理したり、学習発表会の感想文を入力したりと活用方法はさまざまで、今後の課題として写真もつけて文章を完成させたいとのことでした。岡本先生より、「いきなり長文ではなく、最初のとっかかりとして写真に対してコメントを書くなどし、それをAir Drop(iPad同士での転送機能)でクラスメイトと共有したり、卒業制作など共同で一つの物を作るのはどうか。」とのアドバイスをいただきました。

3.高等部での活用・・・「Google Earth」のアプリ
高等部2年の「社理」の授業で使用。「iPadで世界を旅しよう」というテーマで、『世界の建物20』の建物の名前が書かれたくじを引いて場所を選び、その場所を入力し地球がぐるぐると回ってその場所に訪れることを楽しむことができます。また、別アプリでキーボードを使いタイピングの練習も導入しています。岡本先生より、「建物だけでなく、それがどのような建物なのか調べ、発表につなげたり、決定した実習先を調べてみるのはどうか。」とのアドバイスをいただきました。
最後に岡本先生より、「iPadか紙のどちらがよいかは個々の特性に合わせて考え、個々の興味、将来の出口を意識した取り組みが必要で、家庭でも使えるように家庭との連携も必要である。」とまとめていただき、今回の研修は終了しました。