風が涼しさをもたらしてくれるようになると、「おもしろい」の範囲が広がり、学びが深くなるような感じがする
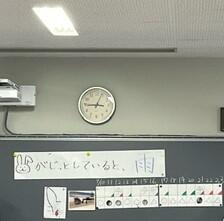
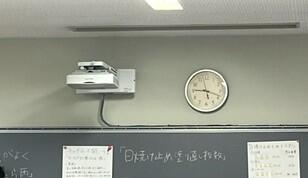 。
。 


9月17日から24日までの一週間で3つの授業を拝見した。今日24日は地学のグループ発表「新しい観天望気と天気予報」 ― 蚊柱、わたがみ、水筒、ウサギ、衛星放送、チャイム。自然界や人間が生み出したもの、普段の生活だけをしていると見落としているようなものに着目することでお天気を占う指標を次々に示していった。何より心強いのは、研究の成果がカッパ着用、水筒持参、ケープ使用法、日焼け止めの使用量、綿菓子の味わいなど実生活を豊かにするヒントが満載だったことである。もう14年の時が経過したがカナダのアルバータ大学の教授が「科学にはロマンがいっぱいだ。自分が好きなことを追求することで人々の生活が味わい深い豊かなものになる。こんな素敵な学問ある?」軽くウインクして、肩をポンと叩いた。

1年生の化学の授業の実験の中でもロマンが味わえた。授業のテーマのヒントが「後鳥羽院宮内卿」の歌で示され、化学発光、ルミノール反応についての実験がなされた。どうやったらスムーズに導入でき、みんなの常道を揺さぶり、心に火をつけるかが考えつくされた授業であった。9月18日に心に飛び込んできた「あかり」が今後の人生の中で光り輝く日が楽しみだ。
その前日の9月17日大阪中の様々なところからから先生方が英語の授業見学にお越しいただいた。英語で英語を教える。ずっとテーマになり、賛否両論あり、何が一番いい形なのかがずっと注目されている。私事になるが、2001年にオーストラリアから帰国し、日本語を日本語で教えることができるのなら、英語で英語を教えることにも挑戦しようと取組みを始めた。24年の歳月(オリンピック7回分)が流れた。この日、複数の学校の先生方から「勇気をもらえた、教科として取り組んでいることがうらやましい(素晴らしい)」という言葉を頂いた。先生がたが研究授業をし、授業者の立場で語るという形は一般的だが、複数学年(1年、3年)が実施し、メンターがスーパーバイズし、質問の仕方、作り方や問いの立て方、その種類についてまで言及する研修に出会える機会はそう頻繁にあるものではない。授業を示した先生も、見学した先生も、全部見通して立案、計画、実施した先生も授業を受けた生徒もみんな何かを得て明日に向かう力となっていれば幸せだ。(英語で英語の授業を受けると一回、一回の授業でその実感を得ることは難しいというのが今まで取り組んできたものの実感だ。→大学に入り、国際交流に携わり、仕事で英語を使う状況に至った生徒には例外なく感謝される。毎回の授業のfeed backの中ではなかなか見いだせない。)
携わって来られたみなさまの多くの時間と労力をかけてここまでたどり着いたことに感謝と敬意を表したい。先生がたも生徒のみなさんも前期末考査ですね。日々の努力が実を結びますように!