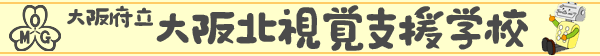前回、本校を卒業後、筑波大学理療科教員養成施設から研究者への道を紹介しましたが、今回は施設名にもある「理療科教員」の話をしたいと思います。
生徒と話をしていると、時々「先生は何で治療家じゃなくて教員になったの?」と聞かれることがあります。
実は私は最初教員になることを全く考えていませんでした。でも3年生になっていろいろな人に進路のことを相談しているうちに「教員」というものに自分なりのこだわりがあることに気づいて、「こだわりがあるならとりあえず受けてみるか!」と決断しました。そんな人間なので、教員養成施設を受験するときも志望動機を聞かれて「教員に向いているかどうかを確かめるために受験しました」みたいな生意気なことを答えた記憶があります。
で、合格できたはいいものの、入学してから自分の知識がいかに表面的で実際には使えないものだったかを思い知らされることが何度かありました。なので教員になってからは、生徒の皆さんが自分と同じ轍(てつ)は踏まないように、生徒の皆さんが患者を目の前にしたときに適切な判断ができるようにと思い、例えば解剖学や生理学を教える時には、正常な構造や機能が異常になったらどうなるか、あるいは病理学や臨床医学を教える時には解剖学や生理学の知識を踏まえて、なぜその症状が出現するのかを考えさせるなど、大事なところは深い学びが得られるようにと心がけて授業を行うようにしています。
ちょっと話がそれますが、昔好きで読んでいた医療系の漫画(テレビドラマにもなっていました)の中で「無限の樹形図」という言葉が出てきます。この漫画の中では「子どものいのちを救うことはたくさんの未来を救うこと」という意味で使われています。私の場合、この無限の樹形図を「自分は治療家として直接患者を癒すことはなくても、自分たちが送り出した生徒が治療家として立派に歩んでくれれば、自分一人が治療するよりも多くの人を治療することにつながる」ととらえ、後付けではありますが、今はそれが教員という進路を選択した理由だと生徒には説明しています。
今は全国の盲学校・視覚支援学校の生徒が減少していることもあって、筑波大学理療科教員養成施設に進学する人も少なくなっています。そのため近い将来、全国の盲学校・視覚支援学校で理療科教員が不足するときがくるのではないかと危惧しています。でもこれってこれから理療科を受験する、特に若手の方にとっては朗報かもしれません。以前と比べると受験倍率は低くなっているということなので、進路の現実的な選択肢が広がることになりますから...
皆さんも「未来の大治療家」を育てられるかもしれない、このやりがいのある理療科教員への道をめざして、大阪北視覚支援学校の理療科を受験しませんか?