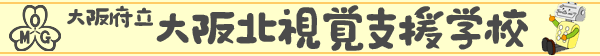年齢が高くなってくると、新たな外来語についていけなくなってきます。例えば最近「ダイバーシティ」って言葉を時々聞きません? 日本語にすると「多様性」という意味になるそうで、それなら最初から「多様性」って言えばいいじゃん!って思うのは私だけなんでしょうか...
さてこの「多様性」、理療系学科にぴったりな表現です。
まず生徒の皆さんについて。
入学条件の一つに高校卒業というのがあるので、下18歳から上は60歳を超える方まで年齢層も様々です。ですから理療科教員をしていると、自分より年上の方に教えるということもよくあります(私も50代半ばを超えてきたので、だんだんその数は減ってきましたが...)。
入学するまでの経歴も様々で、最近は社会人経験者も多く、中には会社を経営していた方とか、大企業の管理職だったという方もいらっしゃいます。ですから人生経験豊富な生徒の皆さんから我々教職員が学ばせてもらうことも多いです。
さまざまな経歴の方が生徒にいらっしゃるということは、そこから進学して理療科教員になる人の中にもいろんな経歴の者がいます。幼稚部から専攻科理療科まで本校を通い、教員になって再び本校で働き始めたという、幼児児童生徒の時代から教員の時代も含めると本校に所属している年数が約50年という強者もいれば、先天性の視覚障がい者だが、高校まで一般校に通い、それから理療系学科に入学してから教員になったという者、高等部普通科まで盲学校を通ってから一般の大学に進学し、卒業後盲学校に戻り理療科に進学し、それから教員への道へ進んだ者、理療科を卒業してから、一旦治療院就職、治療院経営を経験してから教員への道へ進んだ者などなど...。そういう私は一般企業に勤めてからこの世界に入った一人。前職は銀行員でした。
こんな多様性あふれる学科なので、新学期になると、新転任の教職員や新しく入学した幼児児童生徒の保護者の方にとっては、理療系学科の教職員や生徒をみたときに、『めだかの学校』の「だ~れが生徒か先生か~♪」というフレーズがきっと浮かんでいるんじゃないかと思います😅
こんな多様性あふれる大阪北視覚支援学校の理療系学科に皆さんも通ってみませんか?