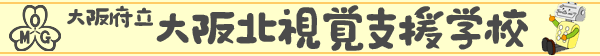あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師になるためには、視覚障がい者は視覚支援学校などに、晴眼者の場合は専門学校や大学に行かなければなりません。それでは、視覚支援学校と専門学校・大学にはどんな違いがあるのでしょうか。これから6回に分けて、同じ3年間通う専門学校との比較を中心に視覚支援学校の特長をお話しします。
第1弾は「視覚障がい者に配慮された授業時間数が設定されている」です。
視覚支援学校も専門学校や大学もそれぞれの学科を設置するためには法律で定められた基準にあった授業設定をしなければなりません。この基準に合致する授業時間数の最低ラインがあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の養成学校の場合、卒業までに1,485時間。おそらく専門学校の多くはこの数字にかなり近い時間数でカリキュラムが組まれていると思います。それに対して本校は3年間で3,150時間。授業時間だけでも2倍くらいの時間をかけてることがわかります。視覚支援学校の方が、授業時間が2倍も多いと聞くと、デメリットに聞こえる方もいらっしゃるかもしれませんね。
もともと理療系学科は、高等部専攻科理療科、高等部専攻科保健理療科というように「高等学校」の枠組みの中で、1日当たり50分授業が6コマ設定されているため、計算するとこのような時間数になるのですが、視覚に障がいがあって、学習にハンディのある方たちに慣れない専門用語や医学用語が出てくる勉強を理解していただくためには、この時間が必要であると私たちは考えています。
例えば普通に見えていれば、模型や図を見せて「ここが...」「それが...」などの、いわゆる「こそあど言葉」=指示語を用いて説明をしても理解できますが、視覚に障がい者にとってはそれだとどこを指示しているのかわからないので、極力指示語は用いず、常に具体的で丁寧な説明を心掛けています。
また模型を用いて説明する場合には生徒一人ひとりに実際に模型に触ってもらいながら説明を行い、知識が定着しやすいように心掛けています。
実技の手順を説明するときにも、手元や姿勢が見えない生徒に対しては、教員の手や体を触ってもらったり、教員が生徒に実際に実技を行ってみたりして、実技の方法がイメージできるようにしています。
このように具体例を読むと、視覚障がい者に配慮した授業を展開するためには、それだけの授業時間数が必要だとご理解いただけるのではないでしょうか。