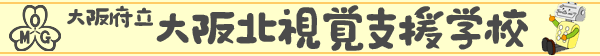前回から間が空いてしまいました。
「続きを早く読みたい!」と熱い要望をいただき、遅筆なことを猛省中です。
さて、第1回では、個別の教育支援計画・指導計画の歴史についてお話しました。 第2回では、個別の教育支援計画・指導計画の役割についてお話し、本校の個別の教育支援計画について説明いたしました。
第3回となる今回は、「個別の指導計画の役割」についてお話させていただきます。
少しおさらいです。 まず、「個別の教育支援計画」は他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画を言い、学校が中心となって保護者と協力しながら、乳幼児期から学校卒業までの一貫した長期的計画を指します。
「個別の指導計画」は指導を行うためのきめ細かい計画のことをいいます。幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画です。
そして、授業の年間指導計画(「シラバス」といいます)に沿って授業が展開されます。
大阪府内の全府立学校ではすべての授業で策定され、府立高校ではすべてインターネット上で公開されています。 府立支援学校ではインターネットに公開はしておりませんが、すべての学校で策定しておりますので、必要に応じて担任の先生に見せてもらってください。(公開資料ですので、特別な手続きは必要ありません)
「シラバス」に基づいて授業が実施され、「個別の教育支援計画」の長期的・短期的目標に従いながら、すべての授業において「個別の指導計画」が策定されます。 「シラバス」と「個別の教育支援計画」をつなぐ役割が「個別の指導計画」だと考えると分かりやすいですね。
さまざまな個別の指導計画の例が、文部科学省のWEBに掲載されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298214.htm
どのような個別の指導計画の様式を使用するかは、その学校独自の考え方などが反映されていますので、一概に「これでよい!」と言うことはできません。
個別の指導計画は「子どもの実態に応じた支援をするために作成されるもの」ですから、子ども一人ひとりに個性があるように、支援のしかたやねらいも個々で異なります。
次回は「個別の指導計画における目標と支援・評価」についてお話いたします。