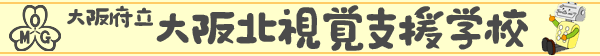今日は「節分の日」です。そもそも、「節分(せつぶん、せちぶん)」とは、何なのでしょうか?

節分とは、雑節の一つで、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことを言います。節分には「季節を分ける」という意味も含まれています。江戸時代以降は特に立春(毎年2月4日ごろ)の前日を指すことが多いです。
一般的には「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆(煎り大豆)を撒いて、年齢の数だけ(もしくは1つ多く)豆を食べて厄除けをします。家の玄関には、邪気除けの柊鰯などを飾ることもあります。これらは、地方や神社などによって異なっていて北海道・東北・北陸・南九州の家庭では落花生を撒き、寺社や地域によっては餅や菓子、みかん等を投げる場合もあるそうです。
では、節分と厄除け・邪気除けはどういった関係性があるのでしょうか?
季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると信じられていたため、それを追い払うための悪霊ばらいが必要だったそうです。宮中では年中行事として豆撒きが執り行われ、無病息災を願っていました。それが近代になって庶民に採り入れられたころから、当日の夕暮れ、柊の枝に鰯の頭を刺したもの(柊鰯)を戸口に立てておいたり、寺社で豆撒きをしたりするようになったそうです。
ちょっと勉強になりましたね。

今日の大阪北視覚支援学校のお友だちのところにも「鬼」が現れました!幼稚部には赤鬼が、小学部・中学部の教室には赤鬼と緑鬼が乱入!教室の扉をガタガタと鳴らして入ってきて、金棒を振りかざす姿は本当に怖かったですね。


怖くて泣きたくなるのを我慢して、新聞紙などで作った豆を手に、お友だちと力を合わせて鬼を退治!みんなの姿はとっても勇敢でした。
みんなで力を合わせて鬼を退治できたので、1年間、けがや病気をすることなく元気に過ごせることでしょう。
(教頭 吉田)