令和6年度大阪府教育センター研究フォーラム第8分科会では「未来を創る力の育成~「わかった!」「できた!」を実感できる学びを求めて~」をテーマに、参加者の皆さんとともに、資質・能力の育成が子どもたちのウェルビーイングの向上にどのようにつながっているのかについて考えました。
今回は、各ブースにおける実践報告の内容について、ご紹介いたします。
枚方市立枚方小学校の実践報告では、 「一人ひとりの子どもたちに寄り添った算数科の授業づくり」と題し、子どもたちの実態に応じて授業改善に取り組む実践についてご報告いただきました。「単元を通してつけたい力を明確にすること」「子どもたち全員が一歩踏み出せるように見通しを持たせること」「自分の考えを説明することの意義や目的を実感させること」について、具体的な実践をもとにお話しいただきました。参加者は、学習したことを次の学習で活用できるようにするための単元計画の流れや、子どもたちが自分に合った方法で学習を進められるようにするための手だて、対話的な学びの意義を子どもたちに実感させるための学習活動の工夫などについて理解を深めておられました。
「一人ひとりの子どもたちに寄り添った算数科の授業づくり」と題し、子どもたちの実態に応じて授業改善に取り組む実践についてご報告いただきました。「単元を通してつけたい力を明確にすること」「子どもたち全員が一歩踏み出せるように見通しを持たせること」「自分の考えを説明することの意義や目的を実感させること」について、具体的な実践をもとにお話しいただきました。参加者は、学習したことを次の学習で活用できるようにするための単元計画の流れや、子どもたちが自分に合った方法で学習を進められるようにするための手だて、対話的な学びの意義を子どもたちに実感させるための学習活動の工夫などについて理解を深めておられました。
大東市立大東中学校の実践報告では、「子どもの体験に関連した『データの活用』領域の授業づくり」と題し、中学校数学科における「データの活用領域」の実践についてご報告いただきました。 「統計的探究サイクルを回すこと」「身近な題材をもとに問題場面を設定すること」について、具体的な実践をもとにお話しいただきました。参加者が、データが示すことをもとに根拠を明確にして自分の考えたことを表現するための手だてや、ペアや班単位での対話的な学びの工夫、またそれらを支えるための1人1台端末の効果的な活用などについて考え、「データの活用領域」の学習の魅力について理解を深める様子が見られました。
「統計的探究サイクルを回すこと」「身近な題材をもとに問題場面を設定すること」について、具体的な実践をもとにお話しいただきました。参加者が、データが示すことをもとに根拠を明確にして自分の考えたことを表現するための手だてや、ペアや班単位での対話的な学びの工夫、またそれらを支えるための1人1台端末の効果的な活用などについて考え、「データの活用領域」の学習の魅力について理解を深める様子が見られました。
摂津市立鳥飼小学校の実践報告では、「協働的に学ぶ校内研究」と 題し、子どもたちの資質・能力を育むために、小学校において組織的な校内研究をどのように推進させていけばよいのかについてご報告いただきました。校内の先生方が協働的に学び合うために、鳥飼小学校の年間計画や校内研修の具体的な内容、校内研究を活性化させるためのツールの活用などについてご紹介いただきました。研究主任をはじめとした推進組織を中心として、他の教員と協働しながら学校全体で校内研究を推進するための手だてについて理解を深めることができました。また同僚の先生方も実践発表にご参加いただき、鳥飼小学校のチーム力を実感することができました。
題し、子どもたちの資質・能力を育むために、小学校において組織的な校内研究をどのように推進させていけばよいのかについてご報告いただきました。校内の先生方が協働的に学び合うために、鳥飼小学校の年間計画や校内研修の具体的な内容、校内研究を活性化させるためのツールの活用などについてご紹介いただきました。研究主任をはじめとした推進組織を中心として、他の教員と協働しながら学校全体で校内研究を推進するための手だてについて理解を深めることができました。また同僚の先生方も実践発表にご参加いただき、鳥飼小学校のチーム力を実感することができました。
吹田市立第六中学校の実践報告では、「表現する力をつける~子どもが主体的に表現する授業づくり~」と題し、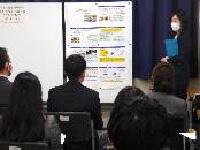 中学校における校内研究の実践についてご報告いただきました。教科の壁を越えた校内研修の在り方や、校内全体で取り組む「子どもの学習の振り返り」などの取組みについて、具体的な実践をもとにお話しいただきました。参加者は、教科を越えて授業について語り合うことの大切さや、校内の先生たちを巻き込んでいくための手だて、子どもの姿をもとに授業改善を考える「指導と評価の一体化」について、理解を深めておられました。
中学校における校内研究の実践についてご報告いただきました。教科の壁を越えた校内研修の在り方や、校内全体で取り組む「子どもの学習の振り返り」などの取組みについて、具体的な実践をもとにお話しいただきました。参加者は、教科を越えて授業について語り合うことの大切さや、校内の先生たちを巻き込んでいくための手だて、子どもの姿をもとに授業改善を考える「指導と評価の一体化」について、理解を深めておられました。
八尾市立南高安小中学校の実践報告では、 「『主体的』『対話的』で『深い学び』が起こる研修デザイン〜生徒のワクワクがとまらない英語授業をめざして〜」と題し、中学校外国語授業づくり研修の取組みについてご報告いただきました。「学びの連続性」「やりとりを中心とした授業」「『ほんもの』を意識した目的・場面・状況」「内容面と言語面の指導の往還」「評価のありかた」のテーマについて、具体的な取組みをもとにお話しいただきました。参加者は、研修づくりの本質は授業づくりの本質と同じであること、「ほんもののコミュニケーション」は、「一生懸命」「丁寧に」「誠実に」を続けていくことで少しずつ生み出されることなどについて、理解を深められていました。
「『主体的』『対話的』で『深い学び』が起こる研修デザイン〜生徒のワクワクがとまらない英語授業をめざして〜」と題し、中学校外国語授業づくり研修の取組みについてご報告いただきました。「学びの連続性」「やりとりを中心とした授業」「『ほんもの』を意識した目的・場面・状況」「内容面と言語面の指導の往還」「評価のありかた」のテーマについて、具体的な取組みをもとにお話しいただきました。参加者は、研修づくりの本質は授業づくりの本質と同じであること、「ほんもののコミュニケーション」は、「一生懸命」「丁寧に」「誠実に」を続けていくことで少しずつ生み出されることなどについて、理解を深められていました。
どのブースにおいても、報告者と参加者との間でディスカッションを重ねながら、お互いに学びを深め合っている様子が見られました。
各ブースにおける実践報告の内容のご紹介の続きは、次回の更新をお待ちください。