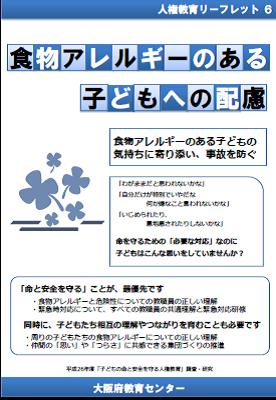食物アレルギーのある子どもへの配慮
平成24年、学校給食終了後に食物アレルギーによるアナフィラキシー・ショックの疑いにより子どもがなくなるという事故が発生しました。それ以降も、学校給食によるアレルギーの報告は後を絶ちません。
本来子どもたちの命と安全を守るべき学校でなぜ事例が続出するのか?その背景には、アレルギーに対する配慮が、他の子どもや保護者から「特別扱い」と思われ、それが「いじめ」や「差別」につながるのではないか、という不安感から、アレルゲンとなる食物を食べてしまうことが多くあります。
食物アレルギーのある子どもの気持ちに寄り添い、事故を防ぐ
◆みんなと同じ様にはできないつらさを理解するとともに、その思いに共感できる感性を養う。
◆他の人の心の痛みを自分のことに引き寄せて考えることができる想像力を育む。
◆互いに配慮し、支え合い、安心して生活できる関係づくりに取り組む。
◆食物アレルギーをはじめとしたアレルギー疾患についての理解を促すとともに、なぜ特別な対応が必要なのかについての理解を深める。
◆最重症の場合は、命に関わることであることを理解し、仲間の命を守る行動について学ぶ。
◆アレルギー疾患のある子どもの保護者からの聞き取りや、栄養教職員・調理員等からの聞き取りを通してその願いや思いを知る。
「命と安全を守る」ことが、最優先です
同時に、子どもたち相互の理解やつながりを育むことも必要です
(リーフレット本文より)
人権教育研究室では、平成25・26年度の2年間にわたり、「子どもの命と安全を守る人権教育」をテーマに調査・研究をおこなっています。
その研究成果を教職員向けの資料として「人権教育リーフレット・シリーズ」を作成し、順次、紹介しています。
今回はNo6、「食物アレルギーのある子どもへの配慮」を扱ったものです。
※リーフレットは大阪府教育センターホームページよりダウンロードできます。
(人権教育研究室)