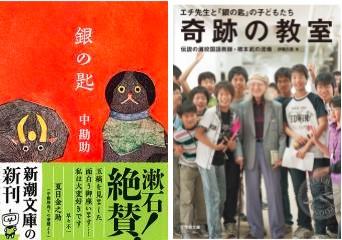伝説の国語教師 橋本武先生を描いた「奇跡の教室~エチ先生と『銀の匙(さじ)』の子どもたち~」を読んだ。先生は教科書を一切使わず、一冊の薄い文庫本、中勘助著『銀の匙』を中学校の3年間かけて読むという授業をおこなっていた。
『銀の匙』は、明治時代後期の少年が主人公の私小説で、少年の心の描写とその周辺で起こる出来事や当時の社会風景が繊細かつ丁寧に描かれている。明治時代ということもあり、わからない(もの)や(ことば)がたびたび登場する。橋本先生は、少しでも分からないことがあれば、プリントで解説を加えながら生徒との学びを進めていく。
私たちが本を読む時、時代背景等の描写に疑問をもちながらも、何となく先に読み進めてしまうことが多い。橋本先生の授業は、分かったつもりにならないで、少しでも疑問に感じたことは、立ち止まり徹底的に調べあげるという形態で進められたようだ。
この姿勢は、橋本先生が若い時に『大漢和辞典』の編集に携わったことによるところが大きい。世に出す辞書の記載は、何となく分かったでは済まされない。一つひとつの言葉や事象と向き合いながら、徹底的に調べる姿勢を身につけた。
橋本氏は(国語を)学ぶということについて、こう言っている。
「国語を学ぶことは、季節のうつろいに気づくというセンスを学ぶこと。そして、深く考えるということを通じて、人は壁を階段にする力を身につけていく。すぐに役立つものはすぐ役立たなくなるのです。」
教師として、(学ぶ⇒生徒とともに考える)そんな姿勢が求められている。