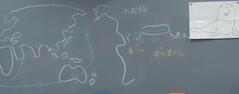4/12(金)に、昨年度の2年「地学特講」の授業で、「新生代第四紀(現在)の次の時代に繁栄する生物について」というテーマでグループ発表を実施した 77 期 30 班の中から、6つの班を代表として選出し、「地学グループ発表 特別編」を開催しました。
当日は、『リアルサイズ古生物図鑑』(技術評論社)、『地球生命 無脊椎の興亡史』(技術評論社)、『生命の大進化40億年史』シリーズ(講談社)など数々の書籍を執筆しているサイエンスライターの土屋健先生を講師としてお招きし、生徒や先生を招待して発表を見ていただきました。
以下、発表を終えた各グループ代表生徒のコメントです。
~~~①『主役はワレワレだ!生き残ったヒーローたち』~~~~
地学のスペシャリストである土屋先生が、専門的な視点での様々な指摘を私たちにも理解しやすい言葉でしてくださり、とても参考になりました。それだけではなく、目のつけ所などを褒めていただいたことが大きな自信に繋がりました。他班の発表を聞き、レベルの高いディスカッションを体験できたことも貴重な経験になり、今後の地学の勉強に興味が湧きました。忙しい中、私たちのために茨木高校に来て発表を見てくださりありがとうございました。

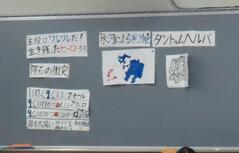
~~~②『初心者でもカンタン!大量絶滅の起こし方!』~~~~
半年前の発表では、面白さ、見やすさ、手際の良さの点で課題が残ってしまいましたが、春休み中に集まって黒板に貼る紙を短い言葉に作り変えたり、新たに小道具を作ったりして、大きくパワーアップした発表をお届けできたことを嬉しく思っています。質疑応答では茨高生からの的確な指摘に「そこは触れないでくれ〜」と何度も叫びたくなりましたが、そこからちょっとした議論に発展したり、今後の展望について新たな視点を得られたり、とても有意義なものになりました。土屋先生は、私たちの発表と質疑応答を優しく見守ってくださった上で、最新の研究者の見解や進化の考え方をたくさん紹介してくださいました。発表方法についても身に余るお褒めの言葉を頂いて、すごく光栄でした。


~~~③『久しぶりに日の目を見るモグラ』~~~~
私にとって年間2回の発表と代表としての発表はとても貴重な経験になりました。特に代表の発表からは、非常に多くのことを得られたと思います。私たちは聴衆を楽しませることを第1に考えて発表の準備をしてきました。放課後や休日に集まって原稿を考えたり、小道具を作ったりしました。僕自身こういうものに積極的に参加するタイプではなかったので、1から何かを考えることにとても苦労しました。その一方で、発表を終えたあとの達成感は筆舌に尽くしがたいものでした。また他の代表グループの発表は卓越したもので、そのアイデアは僕たちが全く考えもしなかったものでした。加えて、発表後の質疑応答もとてもレベルの高いものだったので、あの場であの空気感を味わえたことは非常に良い経験になったと思います。このような機会を設けていただきありがとうございます。


~~~④『海底撈月 海月無双』~~~~
まず班員共通の感想として、土屋先生からお話を聞けてよかった、というものがありました。本やネットで調べ学習を進めていると、どうしても得られるデータや知見は数年前から、ものによっては数十年前のものになってしまう上に、学会のなかでのその知見の地位がどれほどのものなのかわかりませんでした。しかし、この知見は、何十年代に研究が進んでいた、今、最も有力なのはどれどれだ、と昔から今まで研究の最前線にい続けている土屋先生の超貴重なお話を沢山聞けて、本当に勉強になりました。また発表内容だけでなく、発表方法そのものを評価され、人を惹きつける発表の大切さを感じました。何より、知識を活かした具体的で的確な評価、指摘をし、そして1番に賞賛、尊重の気持ちを忘れない、発表に対する聴き手の姿勢の見本というものを土屋先生から学びました。
他の班の発表を聴いて感じたこととしては、うちの班員から他の班の発表に直接質問するということはなかったのですが、それぞれの発表を否定せずにしっかり聞き、質問して、ディスカッションし合うことで、自分のグループの至らなかった点や、新しい考え方を得ていくというのがとても楽しく、学べたことも多かったです。自分の研究を発表し、他の班のユニークな発表を見ることで、こんな視点もあるんだと生徒同士で刺激し合えたし、新たに自分の視野を広げることができたと思います。
私の班は、前々から不安でいっぱいで、発表が終わった後もどうにか乗り越えたぞ、という気持ちばかりだったのですが、他の班の発表、土屋先生のお話を全て聞き終わった後で、班員全員にとって大きな学びを得られた発表会だったな、と心から感じました。
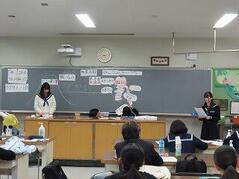
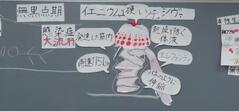
~~~⑤『サソリ無い針引き籠り 〜颯爽とサソリが誘う新種発見の旅🦂〜』~~~~
今回は私達にこのような貴重な発表の機会を与えてくださって、本当にありがとうございました。拙い発表ではございましたが、より最前線で科学に携わっておられる土屋先生を始めとして、より多くの方にご覧いただけたことは非常に有意義な体験になりました。
今回の発表では、土屋先生のアドバイスを受けて自分たちの調査が如何に甘かったかを痛感いたしました。しかし同時に、我々の発表を「センスがあって飽きないものになっている」と評価していただいたことは非常に嬉しく、大きな自信となりました。これから何度かあるだろう研究発表をより良いものに出来るよう、この経験を活かして精進していきたいと思います。
春休みが終わり、新年度が始まる時分、福本先生は、私達とは比べ物にならないほど御多忙であったと存じますが、そんな中でも私達のことを常に気に掛けてくださったこと、感謝いたします。
ここからは班の代表としてではなく、私個人としての所感のようなものになりますが、正直なところ、私は誰かの前に立つことが総じて苦手なので、今回の発表にも少なからず憂鬱な思いはありました。ですが、終わってみれば「やって良かった」と思えるものになりました。これにはいくつか理由があって、既に書いたように土屋先生が私達の発表を褒めてくださったこと、発表を見に来てくださった先生方や生徒の皆さんから頂いた感想が大変暖かいものであったこと、そして福本先生に個別にメッセージを頂けたことも、その内容自体も大変嬉しかったことがあります。
1回目の発表の感想でも書きましたが、ここまで良い発表に仕上げることができたのは、本当に同じ班の2人によるものが大きいと思います。あの内容を考えてくれたのはほとんど彼女たちでした。感謝してもしきれません。残念ながら、3年「地学」の授業では別々になってしまいましたが、今回の発表を胸に日々の学校生活を頑張っていきたいと思います。


~~~⑥『ザ・マグナムポーカ ~深海からこんにちは~』~~~~
私たちの班は、昨年度秋に構想を練り始めた頃、近い未来に起こる環境変動はどのようなもので、生態系にどのような影響があるのか、という視点で考えていました。当初は隕石が降ってくるとか、火山が大噴火を起こすといったスケールの大きくて、予測がつきにくいものをピックアップしようとしていましたが、そのような大きいスケールで、ヒトも滅んでしまうような「環境変動」に繋がるものは、私たち素人にはもはや生物が生き残るかどうかも怪しく思えたので諦めることにしました。では、どのような「環境変動」なら考察を進めやすいか......そのように考えると、やはり地球温暖化が最も先行研究も多く、そのために考察も多角的に進めやすいだろう、ということから、温暖化が進んだ世界で何が起こるか、を調査することにしました。とは言っても、時間は限られていましたので、全ての文献を調べ、確度の高い研究を抽出してと言う訳にはいきません。私たちは、ここでは少々のロマンを求めて「熱塩海流の停止」をピックアップする事にしました。これは、中長期間的に寒冷化を引き起こすと言われていて、私たちは、大型動物や中高緯度の生物に影響がでるだろうと考えました。逆に言うと、陸上、海洋共に大量絶滅が発生するようなものではない可能性がある、という懸念があったのです。今考えてみれば、1℃の温暖化で大きな環境変化が訴えられている現実を考えれば、温暖化→熱塩海流の停止→寒冷化の流れを前提にしている以上、大量絶滅は十分起こり得るはずですが。とにかく、そのような懸念を持った私たちは、大量絶滅というよりは「食物連鎖の頂点の変化」が起こり、その結果、新たに頂点に立つであろう生物を発表することにしよう、ということにしました。正直なところ、アザラシの選定は、その観点と、「可愛かったから」という理由から行いました。そこから話題を展開する事自体は特に困ることはありませんでしたが、今考え直してみれば、単純に天敵を排除する、という思考でホホジロザメの生態を調べなかったのは今回の大きな失敗でした。
発表1回目は、とにかくリハーサルを行わなかったのが問題でした。10分の時間制限があるのに時間計測をして、班員とすり合わせることを怠ったために本番に時間が足りず、伝えたいことを伝えきれませんでした。
その反省を生かして2回目は、時間に特に気を使いました。そのおかげで時間は十分に足り、黒板の管理もうまく行きましたが、私自身としてはタイトルコールをミスしてしまったのが心残りです。
ただ、発表は2回とも声が通っていた点で多くの方から良い評価を頂くことができました。地学とはあまり関係がありませんが、やはり発表をするなら、きちんと声を張って、ゆっくり丁寧に発音すると良い印象を持って頂けるので、これからも心掛けたいです。
研究活動として、心残りはありましたが、発想になかったような新しい視点を得られた貴重な機会になりましたし、プレゼンテーションは全体を通してみると十分上手く行ったと思います。